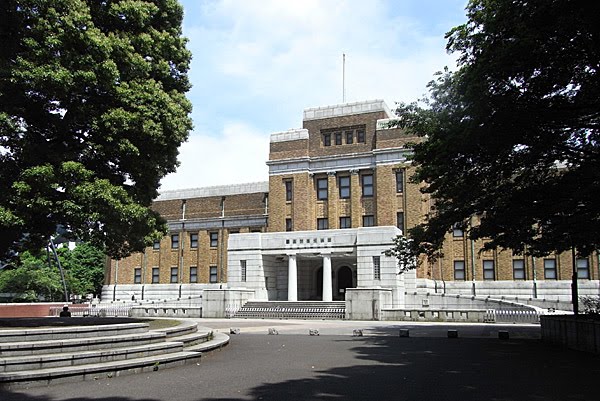このたびの角界「野球賭博事件」は今後、どのような展開を見せるのか。筆者の直感では、テキトーなところで、なんとなく曖昧な幕引きが行われると思っている。その推定根拠は以下のとおり。
(1)角界と一体化した「相撲記者クラブ」
本件、そして朝青龍事件が同一の週刊誌報道から発覚したことは何度も当該コラムで書いてきた。つまり、週刊誌が報道しなければ、直近の2つの角界の不祥事が世の中に報じられることはなかった可能性が高い。
ご存知のとおり、相撲業界に関する「公式報道」は、「相撲記者クラブ」を本源とする。同クラブは政界・官界における記者クラブと同質で、大新聞・TV等以外の雑誌、フリーランス、ウエブ等のジャーナリストは入れない。同クラブの「相撲記者」は相撲協会幹部・力士と接する特権をもっていて、力士に最も近い位置で取材ができる。ということは、このたびの事件、過去の諸々の角界の不祥事を取材しやすい立場にあるはずなのだが、前出のとおり、本件、朝青龍「暴行」事件、薬物事件、若手力士暴行事件等を報道してこなかった。本件と朝青龍事件は同一の週刊誌のスクープだ。
すなわち、「相撲記者クラブ」は角界に都合の悪いことは報道しない。彼らは相撲人気を煽り、相撲ファンを増やし、相撲報道を独占する特権的地位を確保し、相撲ニュースを独占販売する利権集団なのだから。もちろんNHKもその1つで、「相撲記者クラブ」が増幅する相撲人気を基盤とし、相撲中継で安定した視聴率を稼いでいる。相撲はNHKの優良なコンテンツになっている。であるから、角界と一体化している「相撲記者クラブ」が角界追及を本気で行うはずがない。
(2)有識者も特殊性論で角界を「援護」
一部の有識者は、本件を含めて角界について達観するシニシズム的傾向をもっている。この傾向を大雑把に言うと、日本国そのものが闇社会を包摂した存在なのだから、相撲界だけに浄化を求めても無駄だと説明しているように聞こえる。
戦後日本に民主主義体制が確立したにも関わらず、日本の政治家・大企業は闇社会と深く結びついていた。60年安保闘争と右翼テロ、政治家と街宣車、大企業と総会屋、金融業と債権回収、不動産業と地上げ、芸能界と興行権・・・等々に闇社会の影がちらついていた。相撲が芸能である以上、地方巡業と興行師の関係は否定しようもない。だから、いまさら、角界と闇勢力が「野球賭博」を介してつながっていたとしても、昔からのことなのだから騒ぐに値しないと。
このような達観傾向の一部は、当たっている。戦後日本の国家機能に闇勢力がビルトインしているという指摘は正しい。とりわけ、日本の保守勢力が闇勢力を駆使して問題処理に当たっていたことは否定しようもない。だが、近年、企業においてはコンプライアンスが徹底され、株主総会から総会屋が排除されている。日本社会がその筋との関係を完全に清算・根絶できないまでも、排除に努力する姿勢を強めているなかにあって、角界は「しょうがない」という論法はいただけない。一部の有識者の角界達観視が、本件の追及を阻害している。
(3)本気になれない文科省
本件発覚の後、相撲協会が公益法人であるところから、その監督官庁である文科省を攻撃する論調が盛り上がった。公益法人については公益法人制度改革に係る3法が2008年12月1日に施行されていて、すべての公益法人は、その日から5年以内に新制度に準じた新しい法人に移行しなければならない。現在のところ財団、社団といわれている法人は、その定款、寄付行為等を見直し、「一般」か「公益」を選択し、法施行から5年以内に内閣府(認定委員会)に再申請をする。再申請先が内閣府であることは、すべての公益法人が各省庁の所管から離れることを意味する。いま現在とは、各公益法人が「一般」か「公益」か選択して移行する期間に当たっている。
相撲協会は現に財団法人と呼ばれているが、相撲協会に限らず概ねすべての公益法人は、法的には特例民法法人であって、同協会はいずれ、「一般」「公益」を選択していずれかに移行するはずである。そして、そのときをもって、相撲協会は文科省の所管から外れる。文科省にしてみれば、極めて近い将来、自らの所管から外れる法人のトラブルに関心を持てないのではないか。新公益法人の申請を審査する認定委員会の委員の人事についても文科省の関与はない。
前出のとおり「財団法人日本相撲協会」という法人は法的には存在せず、いま現在は新公益法人への移行期とはいえ、移行が完了しない間は、相撲協会が文科省の監督下にあると考えられるから、本件に関する文科省の指導・監督責任は厳しく問われてもいい。
また、現に相撲協会の寄付行為第3条に、「この法人は、わが国固有の国技である相撲道を研究し、相撲の技術を練磨し、その指導普及を図るとともに、これに必要な施設を経営し、もって相撲道の維持発展と国民の心身の向上に寄与することを目的とする。」と、「相撲道」が「国技」である旨を定めている。
新法施行前の公益法人制度では、所管官庁の文科省が相撲協会の寄付行為を認可したことになるから、国が「相撲道」を「国技」と定めたとみなしていい。よって、“協会が勝手に相撲を「国技」だといっているだけだ”というマスコミに登場するコメンテーターの指摘は正しくない。相撲協会が作成し提出した寄付行為(第3条)を文科省が認可しているのであるから、国=文科省は、相撲協会寄付行為第3条が規定する相撲は「国技」であることを認めたと考えられ、となれば、文科省が「相撲道」を「国技」である旨のお墨付きを与えたと考えるのは自然である。換言すれば、相撲が国技である根拠とは、文科省が同協会を公益法人として認可したことと、同協会の寄付行為の規定を認可したこととがが、一体的であることに求められる。
であるから、国技に係る者が野球賭博を反社会的勢力の影響の下に行っていたという本件の責任は、ただただ、文科省にある。相撲協会が今後いかなる法人格を選択するのかは定かではないが、いまのところ、本件の文科省の監督責任は厳しく問われるべきなのだが、「相撲記者クラブ」が相撲協会のみならず文科省とも一体化しているから、これ以上の文科省批判は湧き上がるはずがない。
(4)マスコミが厳しい批判を行わないから、当局も動かない
当局はどうなのか。当局の捜査の加減は、マスコミの動性に左右されるから、「相撲記者クラブ」が相撲協会と一体化している以上、厳しい捜査は期待できない。ごく一部の力士、角界関係者等に捜査が及んで、何人かの者に逮捕状が出されて終わるのではないか。
(5)協会に自浄能力を期待するのは・・・
当事者である相撲協会が調査を行い、自浄能力を発揮することは、過去の同協会の「実績」からみて、あり得ないと考えるほうが自然だろう。当局、マスコミ(相撲記者クラブ)、監督官庁・・・が協会を守っている以上、協会に危機感は生まれまい。その結果、事件は風化し、角界内部の悪は温存される。そして・・・
2010年6月27日日曜日
2010年6月22日火曜日
社会の良識で相撲協会に制裁を―NHKは名古屋場所TV中継を中止せよ
「野球賭博」の当事者がTVに登場して“真実”をコメントし始めたことにより、相撲協会幹部の“作り話”が崩壊しつつある。当該コラムで前述したが、相撲協会幹部、親方、力士は平気で嘘をつくように筆者には思える。暴行事件のときも薬物疑惑のときもそうだった。“謝罪”もその場しのぎのものばかり、それが証拠に、疑惑が次から次へと湧き出してくる。
相撲協会は今回の事件をきっかけにして、反社会的勢力との結びつきを絶つことができるのか。それとも、曖昧な決着により、いままでどおり不適切な関係を続けるつもりなのか。
協会は、これまで、社会的批判を受け止めることがなかった。反省は見せ掛けで、その筋との不適切な関係を維持してきた。今回もそのつもりのようだ。協会の名古屋場所開催の意向が、そのことを物語っている。もちろん、当局・文科省・マスコミも協会を制裁することはないだろう。
だが、社会の良識が働けば、協会に法的制裁が及ばなくとも、協会を制裁することができる。その方法の第一は、生活者の制裁。人々がチケットを購入しないこと、第二は、企業の協力。企業が懸賞金を出さないこと、力士をCMに起用しないこと、第三が、メディアの協力。力士をメディアに登場させないこと、第四に、NHKの決断。公共放送がTV中継をしないこと――だ。いずれも協会の収入を断つことが目的であり、なかんずく、NHKが相撲中継を中止し、放映料を支払わないことが重要だ。NHKはこれまで、相撲協会が幾度となく不祥事を起こしながら、中継を取りやめなかった。
このたびの事件のカネの流れを大雑把に言えば、①庶民・企業等が相撲観戦のために支払ったチケット代、②企業が広告宣伝費として、力士・協会に支払った懸賞金等、③マスコミが力士・協会に支払った出演料(ギャラ)、④TV放映料・・・が協会の収入となり、その一部が親方・力士等の給料等として支払われ、受け取った力士等は給与の一部もしくは全部あるいはそれ以上の額を「野球賭博」に使い、賭け金の一部は胴元を通じて反社会的勢力の懐に入っている。つまり、相撲協会の①~④の収入は、野球賭博を通じて、反社会的勢力に流入している。
名古屋場所を開催しなければ、協会は経営的に打撃を受け、力士等に給与を払えなくなるという。当然である。一般企業が不祥事を起こせば、売上が減少し、経営は立ち行かなくなる。かりに、反社会的勢力と癒着していることが判明した企業が不買運動を起こされ、あるいは事業免許を取り上げられ、経営が危ぶまれたとしても、同情をしてくれる人はいない。当然の報いと理解される。相撲協会だけが例外とされる理由はない。
協会の収入は、賭博を通じて、反社会的勢力に流入している。協会の収入を断つことが、反社会的勢力の収入を断つことに通じる。NHKが生活者から徴収した視聴料は、TV放映料として相撲協会に入り、「野球賭博」を通じて、その筋の「収入」になっている。名古屋場所を協会が開催するのは勝手だが、NHKはTV中継を取りやめ、協会に放映料を支払うべきではない。同様に、企業等が提供する本場所中の懸賞金、優勝力士、三賞等の顕彰に係る報奨金、メディアが行う力士等のインタビュー等も同様に中止し、それに係るギャラの支払いを中止すべきだ。
社会が相撲協会に対して、その収入を絶つのは懲罰の意味もあるが、そればかりではない。賭博に関与した力士が名古屋場所を休場するのならば、日々の取組み自体が異常なものなのだから、そもそも、コンテンツとして崩壊している。協会は、名古屋場所で瑕疵のある興行を催し、それを正規の料金で見せるつもりなのだろうか。販売済みの前売り券については、もちろん、払い戻しを希望する者にはそうすべきだ。
多くの力士が疑惑により休場した結果、名古屋場所の取組みは不完全・不均衡なものとなり、通常の場所とはつりあわない相手との勝負が増えるだろう。そんな異常な本場所で「優勝」した力士に賜杯を渡し顕彰できるのか。異常な名古屋場所を見に行く人は、相撲偏愛者か、それとも・・・だと思うが。
相撲協会は今回の事件をきっかけにして、反社会的勢力との結びつきを絶つことができるのか。それとも、曖昧な決着により、いままでどおり不適切な関係を続けるつもりなのか。
協会は、これまで、社会的批判を受け止めることがなかった。反省は見せ掛けで、その筋との不適切な関係を維持してきた。今回もそのつもりのようだ。協会の名古屋場所開催の意向が、そのことを物語っている。もちろん、当局・文科省・マスコミも協会を制裁することはないだろう。
だが、社会の良識が働けば、協会に法的制裁が及ばなくとも、協会を制裁することができる。その方法の第一は、生活者の制裁。人々がチケットを購入しないこと、第二は、企業の協力。企業が懸賞金を出さないこと、力士をCMに起用しないこと、第三が、メディアの協力。力士をメディアに登場させないこと、第四に、NHKの決断。公共放送がTV中継をしないこと――だ。いずれも協会の収入を断つことが目的であり、なかんずく、NHKが相撲中継を中止し、放映料を支払わないことが重要だ。NHKはこれまで、相撲協会が幾度となく不祥事を起こしながら、中継を取りやめなかった。
このたびの事件のカネの流れを大雑把に言えば、①庶民・企業等が相撲観戦のために支払ったチケット代、②企業が広告宣伝費として、力士・協会に支払った懸賞金等、③マスコミが力士・協会に支払った出演料(ギャラ)、④TV放映料・・・が協会の収入となり、その一部が親方・力士等の給料等として支払われ、受け取った力士等は給与の一部もしくは全部あるいはそれ以上の額を「野球賭博」に使い、賭け金の一部は胴元を通じて反社会的勢力の懐に入っている。つまり、相撲協会の①~④の収入は、野球賭博を通じて、反社会的勢力に流入している。
名古屋場所を開催しなければ、協会は経営的に打撃を受け、力士等に給与を払えなくなるという。当然である。一般企業が不祥事を起こせば、売上が減少し、経営は立ち行かなくなる。かりに、反社会的勢力と癒着していることが判明した企業が不買運動を起こされ、あるいは事業免許を取り上げられ、経営が危ぶまれたとしても、同情をしてくれる人はいない。当然の報いと理解される。相撲協会だけが例外とされる理由はない。
協会の収入は、賭博を通じて、反社会的勢力に流入している。協会の収入を断つことが、反社会的勢力の収入を断つことに通じる。NHKが生活者から徴収した視聴料は、TV放映料として相撲協会に入り、「野球賭博」を通じて、その筋の「収入」になっている。名古屋場所を協会が開催するのは勝手だが、NHKはTV中継を取りやめ、協会に放映料を支払うべきではない。同様に、企業等が提供する本場所中の懸賞金、優勝力士、三賞等の顕彰に係る報奨金、メディアが行う力士等のインタビュー等も同様に中止し、それに係るギャラの支払いを中止すべきだ。
社会が相撲協会に対して、その収入を絶つのは懲罰の意味もあるが、そればかりではない。賭博に関与した力士が名古屋場所を休場するのならば、日々の取組み自体が異常なものなのだから、そもそも、コンテンツとして崩壊している。協会は、名古屋場所で瑕疵のある興行を催し、それを正規の料金で見せるつもりなのだろうか。販売済みの前売り券については、もちろん、払い戻しを希望する者にはそうすべきだ。
多くの力士が疑惑により休場した結果、名古屋場所の取組みは不完全・不均衡なものとなり、通常の場所とはつりあわない相手との勝負が増えるだろう。そんな異常な本場所で「優勝」した力士に賜杯を渡し顕彰できるのか。異常な名古屋場所を見に行く人は、相撲偏愛者か、それとも・・・だと思うが。
2010年6月21日月曜日
2010年6月20日日曜日
核心に迫れるか―相撲界野球賭博事件―
いまが正念場だ、角界の暗部を暴くことができるのかどうかの――
野球賭博事件問題の核心は、角界のだれとだれが野球賭博をやっているかではない。当該コラムで書いたように、今般、日本中の職場の多くにおいて、高校野球が賭博の対象になっていることは、珍しくない。そのことで、生活者が処罰されることはないし、問題となることはない。賭けマージャン、賭けゴルフ等々もしかりだ。
今回の角界の野球賭博事件で最も重要なことは、角界と反社会的勢力とのつながりの一点につきる。野球賭博に反社会的勢力がどのように関与しているのか、賭け金の流れ、賭けに負けた力士が、賭けの資金をどこに求めたか、また、胴元が反社会的勢力そのものなのか、角界関係者が胴元になっていたとしても、その背後に反社会的勢力の存在が認められるのかどうか――にある。
いまのところのマスコミ報道を見聞きする範囲では、その解明については不十分だ。現在の報道の状況としては、親方、力士、床山…のだれだれが野球賭博に関与していました、すいませんでした、で終わりそうな気配だ。角界の野球賭博事件は、それをやっていたことの罪を問うことで終わりそうな気配がする。
繰り返すが、事件発覚の状況は、朝青龍の暴行事件のときと似ている。朝青龍事件を報じたのは、新聞・TVといったマスコミではなく、某週刊誌だった。朝青龍暴行事件の現場は、六本木の某クラブで、その店は事件当時、麻薬取引関係者の出入りが頻繁にあったという噂が絶えなかった。事件当時といえば、芸能人の麻薬事件がしばしば報道されていたころだった。だからといって、朝青龍及び「被害者」が麻薬取引に関与していたというつもりはないが、本場所中のアスリート(=朝青龍)が顔を出すような場所でないことだけは確かではないか。
重要なのは、朝青龍事件も今回の野球賭博事件も、週刊誌が報じなければ、明るみに出なかった可能性が高いことだ。つまり、日本の(スポーツ)マスコミは、先の朝青龍暴行事件も、このたびの野球賭博の蔓延の事実も、知ってかしらずか、報じなかった。
筆者の推測では、相撲界と反社会的勢力は、巡業興行権を媒介として、戦後一貫してつながりがあった。また、その筋から角界関係者に対して、多額の交際費のような不適切なカネの流れがあった。力士・親方等は、その筋の関係者と親密な交際を行っていた。ところが、当局、(スポーツ)マスコミ並びに文科省(公益法人である相撲協会を所管する監督官庁)の3者は、そのことを見過ごしてきたばかりでなく、マスコミは相撲人気を煽り、当局・文科省は「国技」としてお墨付きを与えていた。その間、相撲界には「銃刀法違反」「八百長疑惑」「暴行事件」「麻薬事件」「朝青龍問題」などが起ったが、報道は一過性であり、文科省の指導も形式的であり、当局の捜査も生温かった。
「朝青龍事件」の場合、週刊誌報道がきっかけとなって、マスコミ報道が白熱する一方、朝青龍と「被害者」との間に示談が成立した。その結果、警察の捜査が朝青龍側に及ぶこともなく、朝青龍の突然の引退をもって、事件の真相はうやむやのまま、フェードアウトした。しかし、一部の専門メディアは、示談には反社会的勢力が関与したことを報じた。朝青龍事件の背後に反社会的勢力の存在がうかがえた。
今回も、同じ週刊誌の報道がきっかけとなって、賭博事件が明るみに出た。繰り返すが、大新聞は角界で野球賭博がほぼ恒常的に行われていたことを1行たりとも書いたことはないし、TVも1秒たりとも、流したことはない。(スポーツ)マスコミは相撲協会の広報宣伝の機能を果たし、公共放送は不祥事が多発する相撲のTV中継を休むことはなく続けていた。日本の公共放送は、視聴者から視聴料を取り続けながら、反社会的勢力と関係する団体が行う興行を中継し続けた。大企業は、その取組みに懸賞金を出し続けた。そればかりか、その「優勝者」を国をあげて顕彰した。
これまで角界で起きた事件に係る報道は、マスコミによって大量の「情報」が流れる一方、事件の真相・核心に迫るものはなく、むしろ、真相・核心を隠蔽する働きをしてきたように思える。麻薬事件の場合も、朝青龍暴行事件の場合も、背後に反社会的勢力の関与がうかがえたにも関わらず、報道がそこを突くことはなかった。今回の事件に先立って、「維持員席」のチケット販売をめぐって、相撲協会と反社会的勢力との深い結びつきが暗示されていたにもかかわらず、マスコミは角界の暗部を突くような報道をしなかった。逆に、(スポーツ)マスコミ、当局、文科省は、一貫して、相撲協会を守り続けてきた――なぜか
野球賭博事件問題の核心は、角界のだれとだれが野球賭博をやっているかではない。当該コラムで書いたように、今般、日本中の職場の多くにおいて、高校野球が賭博の対象になっていることは、珍しくない。そのことで、生活者が処罰されることはないし、問題となることはない。賭けマージャン、賭けゴルフ等々もしかりだ。
今回の角界の野球賭博事件で最も重要なことは、角界と反社会的勢力とのつながりの一点につきる。野球賭博に反社会的勢力がどのように関与しているのか、賭け金の流れ、賭けに負けた力士が、賭けの資金をどこに求めたか、また、胴元が反社会的勢力そのものなのか、角界関係者が胴元になっていたとしても、その背後に反社会的勢力の存在が認められるのかどうか――にある。
いまのところのマスコミ報道を見聞きする範囲では、その解明については不十分だ。現在の報道の状況としては、親方、力士、床山…のだれだれが野球賭博に関与していました、すいませんでした、で終わりそうな気配だ。角界の野球賭博事件は、それをやっていたことの罪を問うことで終わりそうな気配がする。
繰り返すが、事件発覚の状況は、朝青龍の暴行事件のときと似ている。朝青龍事件を報じたのは、新聞・TVといったマスコミではなく、某週刊誌だった。朝青龍暴行事件の現場は、六本木の某クラブで、その店は事件当時、麻薬取引関係者の出入りが頻繁にあったという噂が絶えなかった。事件当時といえば、芸能人の麻薬事件がしばしば報道されていたころだった。だからといって、朝青龍及び「被害者」が麻薬取引に関与していたというつもりはないが、本場所中のアスリート(=朝青龍)が顔を出すような場所でないことだけは確かではないか。
重要なのは、朝青龍事件も今回の野球賭博事件も、週刊誌が報じなければ、明るみに出なかった可能性が高いことだ。つまり、日本の(スポーツ)マスコミは、先の朝青龍暴行事件も、このたびの野球賭博の蔓延の事実も、知ってかしらずか、報じなかった。
筆者の推測では、相撲界と反社会的勢力は、巡業興行権を媒介として、戦後一貫してつながりがあった。また、その筋から角界関係者に対して、多額の交際費のような不適切なカネの流れがあった。力士・親方等は、その筋の関係者と親密な交際を行っていた。ところが、当局、(スポーツ)マスコミ並びに文科省(公益法人である相撲協会を所管する監督官庁)の3者は、そのことを見過ごしてきたばかりでなく、マスコミは相撲人気を煽り、当局・文科省は「国技」としてお墨付きを与えていた。その間、相撲界には「銃刀法違反」「八百長疑惑」「暴行事件」「麻薬事件」「朝青龍問題」などが起ったが、報道は一過性であり、文科省の指導も形式的であり、当局の捜査も生温かった。
「朝青龍事件」の場合、週刊誌報道がきっかけとなって、マスコミ報道が白熱する一方、朝青龍と「被害者」との間に示談が成立した。その結果、警察の捜査が朝青龍側に及ぶこともなく、朝青龍の突然の引退をもって、事件の真相はうやむやのまま、フェードアウトした。しかし、一部の専門メディアは、示談には反社会的勢力が関与したことを報じた。朝青龍事件の背後に反社会的勢力の存在がうかがえた。
今回も、同じ週刊誌の報道がきっかけとなって、賭博事件が明るみに出た。繰り返すが、大新聞は角界で野球賭博がほぼ恒常的に行われていたことを1行たりとも書いたことはないし、TVも1秒たりとも、流したことはない。(スポーツ)マスコミは相撲協会の広報宣伝の機能を果たし、公共放送は不祥事が多発する相撲のTV中継を休むことはなく続けていた。日本の公共放送は、視聴者から視聴料を取り続けながら、反社会的勢力と関係する団体が行う興行を中継し続けた。大企業は、その取組みに懸賞金を出し続けた。そればかりか、その「優勝者」を国をあげて顕彰した。
これまで角界で起きた事件に係る報道は、マスコミによって大量の「情報」が流れる一方、事件の真相・核心に迫るものはなく、むしろ、真相・核心を隠蔽する働きをしてきたように思える。麻薬事件の場合も、朝青龍暴行事件の場合も、背後に反社会的勢力の関与がうかがえたにも関わらず、報道がそこを突くことはなかった。今回の事件に先立って、「維持員席」のチケット販売をめぐって、相撲協会と反社会的勢力との深い結びつきが暗示されていたにもかかわらず、マスコミは角界の暗部を突くような報道をしなかった。逆に、(スポーツ)マスコミ、当局、文科省は、一貫して、相撲協会を守り続けてきた――なぜか
2010年6月18日金曜日
2010年6月17日木曜日
相撲協会は解散
相撲界で野球賭博が行われていることが問題になっている。文科省を始めとする関係者等が、ようやく、ことの深刻さを認識し始めたようだ。相撲界の不祥事及び事件が報道されるのは、もちろん、今回が初めてではない。問題発生のたびごとに、相撲協会内に「××調査委員会」や「○○機関」などが設置されるものの、真相は隠蔽されたままだ。
お気づきの方も多いと思うが、今回の野球賭博事件が明るみに出たのは、週刊誌報道からであって、(スポーツ)マスコミによるものではなかった。これは、朝青龍事件のときも同様だ。あのときにも、(スポーツ)マスコミは、朝青龍・相撲協会側に対して、説明責任を追及することはなかった。そればかりではない。相撲協会は財団法人(公益法人)であり、所管の文科省に監督責任がありながら、文科省も協会に対して、適正な指導を行わなかった。適正な指導と監督が継続されていれば、不祥事の再発は防げた。
筆者が腹立たしく思うのは、TVカメラの前に出てくる協会役員(親方=元力士)が、「やっていない」「そんなことは知らない」とまず否定し、事件報道の進捗とともに「反省している」「膿を出す」に変わり、やがて、「雲隠れ」することだ。彼らのコメントからは、時の経過とともに、「事件」「疑惑」がうやむやになることを見越しているようなのだ。つまり、責任をとること=角界からの追放、刑事罰等が降りかかることはないと、高を括っていることがその表情から明らかなのだ。
彼らが高を括っていられるのは、▽自分たちは、絶対にマスコミから厳しい追求を受けないこと、▽文科省の指導が形式的なこと(法人解散には至らないこと)、▽角界からの追放処分という厳罰は絶対に受けないこと――が了解されているからだろう。厳しい処分がくだらない背景には、相撲が「国技」と認識されているからだろう。本場所の優勝者の顕彰には、「総理大臣杯」が含まれている。文科省が手を出せない「タブーゾーン」なのだろうか。
週刊誌が火をつけ、マスコミが後追い報道し、文科省のそれなりの指導があり、処分がくだり、「表」の人事が一新され、本場所が始まれば「はい、それまで」。本場所は公共放送が中継をしてくれるし、チケットもそれなりに売れる。不祥事・事件が協会を経営的に圧迫することもない。だから、“のらりくらり”とした、なまぬるい「反省」と「処分」が繰り返されだけなのだ。
今回の野球賭博事件等は、反社会的勢力と角界が深く結びついていることを暗示している。この結びつきの延長線上あるものは、角界に対して恒常的に指摘されるところの「八百長」の存在だ。野球賭博の裏側には、「相撲賭博」があり、力士が野球賭博を行っている裏側には、力士の八百長相撲と相撲賭博が結びつき、反社会的勢力は、野球賭博と八百長=相撲賭博において、角界と結びついている。こう考えることが自然だ。
賭博にはいろいろある。職場で高校野球が賭博の対象になっていることは常識だが、そこでは、サラリーマン等がささいな金銭をかけているにすぎない。生活者が行う、賭けマージャン、賭けゴルフ、賭け花札・・・が問題視されることはない。組織的賭博に反社会的勢力が介在することにより、賭け金が大きくなり、不正な金銭の動きが恒常化し、その流れが反社会的勢力の資金源として「成長」していくことを防がなければならない。
角界の暗部の解明をどうするか。文科省が真相究明を放棄し、当局も捜査を控えれば、角界の不祥事は「許される」という「タブー」が社会に定着する。協会幹部は「表の責任」をとるだけ。そうなれば、一般常識をもった人ならば、角界は反社会的勢力とつながった団体だと認識する。そんなところに、自分の子供を預けようとは思うまい。相撲は「国技」と呼ばれながら、それを担う角界は特殊視され、反社会的勢力と結びついた怖い団体の1つとして、社会から疎外される。
それでいいのだろうか。協会、文科省、当局が本気で解明をする気があるのならば、次回に予定されている名古屋場所を中止し、角界全体が真相解明に尽力していることを表明すべきなのだ。
相撲が伝統芸能として貴重なことは言うまでもない。が、それを保存する方法はいくらでもある。いまのように、財団法人(公益法人)のまま、興行を続けるという「あり方」に限る必要はない。真相究明の方法として、協会解散という選択肢から考えるべきなのだ。
お気づきの方も多いと思うが、今回の野球賭博事件が明るみに出たのは、週刊誌報道からであって、(スポーツ)マスコミによるものではなかった。これは、朝青龍事件のときも同様だ。あのときにも、(スポーツ)マスコミは、朝青龍・相撲協会側に対して、説明責任を追及することはなかった。そればかりではない。相撲協会は財団法人(公益法人)であり、所管の文科省に監督責任がありながら、文科省も協会に対して、適正な指導を行わなかった。適正な指導と監督が継続されていれば、不祥事の再発は防げた。
筆者が腹立たしく思うのは、TVカメラの前に出てくる協会役員(親方=元力士)が、「やっていない」「そんなことは知らない」とまず否定し、事件報道の進捗とともに「反省している」「膿を出す」に変わり、やがて、「雲隠れ」することだ。彼らのコメントからは、時の経過とともに、「事件」「疑惑」がうやむやになることを見越しているようなのだ。つまり、責任をとること=角界からの追放、刑事罰等が降りかかることはないと、高を括っていることがその表情から明らかなのだ。
彼らが高を括っていられるのは、▽自分たちは、絶対にマスコミから厳しい追求を受けないこと、▽文科省の指導が形式的なこと(法人解散には至らないこと)、▽角界からの追放処分という厳罰は絶対に受けないこと――が了解されているからだろう。厳しい処分がくだらない背景には、相撲が「国技」と認識されているからだろう。本場所の優勝者の顕彰には、「総理大臣杯」が含まれている。文科省が手を出せない「タブーゾーン」なのだろうか。
週刊誌が火をつけ、マスコミが後追い報道し、文科省のそれなりの指導があり、処分がくだり、「表」の人事が一新され、本場所が始まれば「はい、それまで」。本場所は公共放送が中継をしてくれるし、チケットもそれなりに売れる。不祥事・事件が協会を経営的に圧迫することもない。だから、“のらりくらり”とした、なまぬるい「反省」と「処分」が繰り返されだけなのだ。
今回の野球賭博事件等は、反社会的勢力と角界が深く結びついていることを暗示している。この結びつきの延長線上あるものは、角界に対して恒常的に指摘されるところの「八百長」の存在だ。野球賭博の裏側には、「相撲賭博」があり、力士が野球賭博を行っている裏側には、力士の八百長相撲と相撲賭博が結びつき、反社会的勢力は、野球賭博と八百長=相撲賭博において、角界と結びついている。こう考えることが自然だ。
賭博にはいろいろある。職場で高校野球が賭博の対象になっていることは常識だが、そこでは、サラリーマン等がささいな金銭をかけているにすぎない。生活者が行う、賭けマージャン、賭けゴルフ、賭け花札・・・が問題視されることはない。組織的賭博に反社会的勢力が介在することにより、賭け金が大きくなり、不正な金銭の動きが恒常化し、その流れが反社会的勢力の資金源として「成長」していくことを防がなければならない。
角界の暗部の解明をどうするか。文科省が真相究明を放棄し、当局も捜査を控えれば、角界の不祥事は「許される」という「タブー」が社会に定着する。協会幹部は「表の責任」をとるだけ。そうなれば、一般常識をもった人ならば、角界は反社会的勢力とつながった団体だと認識する。そんなところに、自分の子供を預けようとは思うまい。相撲は「国技」と呼ばれながら、それを担う角界は特殊視され、反社会的勢力と結びついた怖い団体の1つとして、社会から疎外される。
それでいいのだろうか。協会、文科省、当局が本気で解明をする気があるのならば、次回に予定されている名古屋場所を中止し、角界全体が真相解明に尽力していることを表明すべきなのだ。
相撲が伝統芸能として貴重なことは言うまでもない。が、それを保存する方法はいくらでもある。いまのように、財団法人(公益法人)のまま、興行を続けるという「あり方」に限る必要はない。真相究明の方法として、協会解散という選択肢から考えるべきなのだ。
2010年6月11日金曜日
2010年6月9日水曜日
『東シナ海と西海文化(「海と列島文化」第4巻)』
●網野善彦ほか[著] ●小学館 ●6311円(税別)

本書がとりあげる地域は、九州西北部、佐賀、長崎、熊本の3県の海沿いである。この当たりの地図を眺めてみると、有明海、大村湾といった内海や、平戸島、五島列島、天草諸島といった島々、そして、西彼杵半島、島原半島、長崎半島などが入り組んだ、複雑な地形をなしていることに驚く。そこから西に東シナ海が広がり、直線で済州島を経て、中国の長江(揚子江)の下流域にぶつかる。以後、この地域を本書に従って、“西海地方”と呼ぶ。
こんにち、西海地方が日本の政治・経済の中心であるとは言い難い。が、本書にあるとおり、弥生時代から徳川時代末まで、世界と日本列島を結ぶ重要な役割を担ってきた。近代以前の西海地方は、日本列島の中にあって、世界に向かって開かれた唯一の窓であったと言って言い過ぎでない。
[1]弥生時代と西海地方
◎弥生文化は中国江南地方から伝えられたのか
西海地方が海外と接触を始めたのは、弥生時代(紀元前3世紀ごろから3世紀ごろまでの500~600年間)に遡る。弥生時代とは、日本列島が大陸文化の影響を受け、それまで築いてきた縄文時代の社会・文化が大きく変容を遂げた時代だと考えられる。
大陸文化は、日本列島に、稲作技術、金属使用等を伝えた一方、列島内の各所には、一定規模を有する権力機構(クニ)が整備され、有力な支配者が誕生した。その中の一つの「邪馬台国」と、その支配者(女王)・卑弥呼の名前が中国の文献に記されている。
大陸文化が日本に流入した有力な経路としては、朝鮮半島から対馬・壱岐を経由して、北九州に上陸したとされる「朝鮮半島ルート」が挙げられてきた。ところが、近年の弥生時代研究の進展により、中国江南地方から東シナ海を経て、西海地方に直接流入したとされる「江南ルート」が注目されるようになった。大陸文化の流入経路として「江南ルート」が「朝鮮半島ルート」より有力視されるようになった考古学上の契機の1つが、吉野ヶ里遺跡(佐賀県)の発見であった。同遺跡は現在の地図上では内陸に位置するが、当時、有明海は同遺跡の間近まで迫っていた。すなわち、同遺跡は海岸沿いに開けた“クニ”の址なのである。
◎倭人の姿は、江南地方の越人と同じ
そればかりではない。『魏志倭人伝』には、
■又一海を渡ること千余里、末盧國に至る。四千余戸有り。山海にそいて居る。草木茂盛して行くに前人を見ず。好んで魚ふくを捕うるに、水、深浅と無く、皆沈没して之を取る。 東南のかた陸行五百里にして、伊都國に至る。官を爾支と日い、副を泄謨觚・柄渠觚と日う。千余戸有り。世王有るも皆女王國に統属す。郡の使の往来して常に駐る所なり。
(略)
男子は大小と無く、皆黥面文身す。古よりこのかた、その使の中國に詣るや、皆自ら大夫と称す。夏后小康の子、会稽に封ぜらるるや、断髪文身して以て蛟龍の害を避く。 今、倭の水人、好んで沈没して、魚蛤を補う。文身は亦以て大魚・水禽を厭う。後やや以て飾りとなす。諸国の文身各々異なり、あるいは左にしあるいは右にし、あるいは大にあるいは小に、尊卑差あり。その道里を計るに、当に会稽の東治の東にあるべし。■
とあり、倭人が中国を訪れたとき、自らを夏(王朝)の末裔(太伯の後裔)であると称していることも江南地方との関係を推定させる根拠となっている。夏王朝とは、紀元前2070年頃~ 紀元前1600年頃にあったと伝承される中国最古の王朝で、夏后ともいう。近年、江南地方において考古学資料の発掘が相次ぎ、実在が見直されてきている。非漢民族系の水上民族だという説も有力である。
夏王朝の末裔を自称する民族は中国周辺にいくつかあり、その1つが、春秋時代の紀元前600年頃~紀元前334年、中国江南地方(浙江省)に建国された越である。越の首都は会稽(現在の浙江省紹興市)。もちろん、非漢民族系であると考えられている。また、時代は下って、紀元前220年~同80年の三国時代(魏・呉、蜀)には、江南地方には呉が建国されていて、呉も越人の国であった。
さらに、『魏志倭人伝』には、倭人が海中で鮫等の襲撃から身を守るため文身(刺青)をしていると記録されているが、江南地方の越の人々も鮫等の襲撃から身を守るため、倭人と同様、文身(刺青)をし、海中に潜って漁をしていたことが確認されている。なお、『魏志倭人伝』には、末盧國(現在の佐賀県松浦郡に推定)で、海に潜って漁をする人々の姿が記録されているが、西海地方にはいまなお、海人による潜水漁が伝えられている。
◎中国の東方憧憬信仰と日本の「徐福伝説」
徐福という方士(道士)が、中国を統一した秦(紀元前778年~紀元前206年)の始皇帝に対して、「東方の三神山に長生不老(不老不死)の霊薬がある」と具申し、始皇帝の命を受け、3,000人の童男童女(若い男女)と百工(多くの技術者)を従え、五穀の種を持って、東方に船出し、「平原広沢(広い平野と湿地)」を得て王となり戻らなかったとの記述が、司馬遷の『史記』の巻百十八『淮南衝山列伝』にある。日本側からみると、これがいわゆる「徐福伝説」で、有明海沿岸各地に徐福伝説が残されている。なお徐福の来訪地といわれるところは、日本の各所にある。
この伝説を素直に読めば、中国から東方に向けて、3000人が移住したわけで、東方とは日本列島であると推定される根拠がある。すなわち、中国側から「徐福伝説」を読み解くと、中国に古くから伝わる「東方憧憬信仰」の1つだ考えることが自然である。東方に方士を差し向けたことは、始皇帝が最初ではない。
古代中国では、東方に理想郷もしくは不老不死の国があるという東方憧憬信仰が、秦の建国以前から信じられていた。周代(紀元前1046年頃~紀元前771年)に、倭人と越人が交流し、倭人が暢を貢いだことが、後漢代の江南の学者王充の『論衡』にある。暢(草)とは神聖な祭事に欠かせない薬草もしくは神酒だといわれている。暢を東方の倭人が貢いだという情報が、東方憧憬信仰の形成要因の1つとなった可能性もあるし、併せて、江南地方と倭の交易ネットワークが、周の時代には整備されていたとも考えられる。
◎「家船」と「蛋民」
西海地方に近年まで残っていた家船(えぶね)といわれる水上生活者の存在を、中国南部の水上生活者(=「蛋民」)と比較する研究も進められている。蛋民研究も西海地方と江南地方を結びつける手掛かりの1つだと考えられている。
◎水稲栽培は中国江南地方からこの地にもたらされたのか?
いずれにしても、西海地方は、日本列島における弥生文化の最先端地域の1つだった。ならば、西海地方における稲作技術の受容については、どのような状況であったのだろうか。
稲作技術の流入経路としては、①華北説、②華中説、③華南説の3説がある。①は、大陸文化流入の「朝鮮半島ルート」に、②が「江南ルート」に、それぞれ対応する。③は柳田国男が唱えた「海上の道」説で、中国広東省から台湾~南西諸島(沖縄)を経て南九州に入ったとするルートであるが、今日の学会では支持者は少なく、稲作流入でも、②華中説=「江南ルート」が主流である。
日本最古の水田址遺跡は特定されていないが、弥生時代前期初頭の水田遺構は、福岡平野の板付遺跡や野多目遺跡、早良平野の橋本一丁田遺跡等で発見されている。また、縄文後期中葉に属する岡山県南溝手遺跡や同県津島岡大遺跡の土器胎土内からイネのプラント・オパールが発見されたことにより、紀元前約3500年前から陸稲(熱帯ジャポニカ)による稲作が行われていたとする学説が有力となっている。いずれにしても、稲作関連の遺構は、西海地方からの発見ではない。近年の研究では、水稲栽培で定義される弥生時代の始まりが、紀元前10世紀まで遡る可能性を指摘する。
[2]遣唐使と西海地方
時代はくだって、中国に強大な唐王朝(618年~907年)が成立。倭国はこの文化先進国から学問・政治制度、技術等を学ぶため、遣唐使を派遣した。彼らが唐に向かう遣唐使船は、西海地方の美美良久(みみらく)=福江島三井楽から出航した。西海地方は、奈良・平安時代における大陸・東シナ海世界の一環にあった。
[3]倭寇が跋扈する海域
中世になると、中国江南地方、朝鮮半島南部海岸地域、済州島、壱岐・対馬、西海地方を含めた海域は、倭寇が勢力を振るう圏域となった。倭寇とは同海域において、漁撈、交易、海賊行為を行った人々の総称と考えられ、必ずしも倭人とは限らない。倭寇は国家統治や国境を意識しない自由な民であり、まさにグローバルに経済活動を行った集団だった。
[4]近世、大航海時代と西海地方
中世末(1543年)、ポルトガル人が種子島に漂着して以降、日本は大航海時代の西欧世界と接触を開始した。1570年には長崎が開港し、1549年にはイエズス会のフランシスコ・ザビエルが日本にやってきた。16世紀なると、西海地方は、日本が産する銀を求めるスペイン、ポルトガルが行う世界貿易の一環に組み込まれ、世界貿易と同時にキリスト教(カトリック)が西海地方に伝えられた。キリスト教布教の本格化とともに、長崎、平戸、五島列島、天草地方等々に教会、聖堂が建設されたりしたが、秀吉によって「禁教令」が発せられ、キリスト教は弾圧対象となった。以降、長崎は江戸幕府の鎖国政策の中にあっても、朝鮮貿易、オランダ貿易の日本で唯一の窓口=世界貿易港であり続けた。
本書によって、西海地方は、古代から近世に至るまで、日本列島内において、最もドラスティックに海外と接触を続けた地域であったことを知る。

本書がとりあげる地域は、九州西北部、佐賀、長崎、熊本の3県の海沿いである。この当たりの地図を眺めてみると、有明海、大村湾といった内海や、平戸島、五島列島、天草諸島といった島々、そして、西彼杵半島、島原半島、長崎半島などが入り組んだ、複雑な地形をなしていることに驚く。そこから西に東シナ海が広がり、直線で済州島を経て、中国の長江(揚子江)の下流域にぶつかる。以後、この地域を本書に従って、“西海地方”と呼ぶ。
こんにち、西海地方が日本の政治・経済の中心であるとは言い難い。が、本書にあるとおり、弥生時代から徳川時代末まで、世界と日本列島を結ぶ重要な役割を担ってきた。近代以前の西海地方は、日本列島の中にあって、世界に向かって開かれた唯一の窓であったと言って言い過ぎでない。
[1]弥生時代と西海地方
◎弥生文化は中国江南地方から伝えられたのか
西海地方が海外と接触を始めたのは、弥生時代(紀元前3世紀ごろから3世紀ごろまでの500~600年間)に遡る。弥生時代とは、日本列島が大陸文化の影響を受け、それまで築いてきた縄文時代の社会・文化が大きく変容を遂げた時代だと考えられる。
大陸文化は、日本列島に、稲作技術、金属使用等を伝えた一方、列島内の各所には、一定規模を有する権力機構(クニ)が整備され、有力な支配者が誕生した。その中の一つの「邪馬台国」と、その支配者(女王)・卑弥呼の名前が中国の文献に記されている。
大陸文化が日本に流入した有力な経路としては、朝鮮半島から対馬・壱岐を経由して、北九州に上陸したとされる「朝鮮半島ルート」が挙げられてきた。ところが、近年の弥生時代研究の進展により、中国江南地方から東シナ海を経て、西海地方に直接流入したとされる「江南ルート」が注目されるようになった。大陸文化の流入経路として「江南ルート」が「朝鮮半島ルート」より有力視されるようになった考古学上の契機の1つが、吉野ヶ里遺跡(佐賀県)の発見であった。同遺跡は現在の地図上では内陸に位置するが、当時、有明海は同遺跡の間近まで迫っていた。すなわち、同遺跡は海岸沿いに開けた“クニ”の址なのである。
◎倭人の姿は、江南地方の越人と同じ
そればかりではない。『魏志倭人伝』には、
■又一海を渡ること千余里、末盧國に至る。四千余戸有り。山海にそいて居る。草木茂盛して行くに前人を見ず。好んで魚ふくを捕うるに、水、深浅と無く、皆沈没して之を取る。 東南のかた陸行五百里にして、伊都國に至る。官を爾支と日い、副を泄謨觚・柄渠觚と日う。千余戸有り。世王有るも皆女王國に統属す。郡の使の往来して常に駐る所なり。
(略)
男子は大小と無く、皆黥面文身す。古よりこのかた、その使の中國に詣るや、皆自ら大夫と称す。夏后小康の子、会稽に封ぜらるるや、断髪文身して以て蛟龍の害を避く。 今、倭の水人、好んで沈没して、魚蛤を補う。文身は亦以て大魚・水禽を厭う。後やや以て飾りとなす。諸国の文身各々異なり、あるいは左にしあるいは右にし、あるいは大にあるいは小に、尊卑差あり。その道里を計るに、当に会稽の東治の東にあるべし。■
とあり、倭人が中国を訪れたとき、自らを夏(王朝)の末裔(太伯の後裔)であると称していることも江南地方との関係を推定させる根拠となっている。夏王朝とは、紀元前2070年頃~ 紀元前1600年頃にあったと伝承される中国最古の王朝で、夏后ともいう。近年、江南地方において考古学資料の発掘が相次ぎ、実在が見直されてきている。非漢民族系の水上民族だという説も有力である。
夏王朝の末裔を自称する民族は中国周辺にいくつかあり、その1つが、春秋時代の紀元前600年頃~紀元前334年、中国江南地方(浙江省)に建国された越である。越の首都は会稽(現在の浙江省紹興市)。もちろん、非漢民族系であると考えられている。また、時代は下って、紀元前220年~同80年の三国時代(魏・呉、蜀)には、江南地方には呉が建国されていて、呉も越人の国であった。
さらに、『魏志倭人伝』には、倭人が海中で鮫等の襲撃から身を守るため文身(刺青)をしていると記録されているが、江南地方の越の人々も鮫等の襲撃から身を守るため、倭人と同様、文身(刺青)をし、海中に潜って漁をしていたことが確認されている。なお、『魏志倭人伝』には、末盧國(現在の佐賀県松浦郡に推定)で、海に潜って漁をする人々の姿が記録されているが、西海地方にはいまなお、海人による潜水漁が伝えられている。
◎中国の東方憧憬信仰と日本の「徐福伝説」
徐福という方士(道士)が、中国を統一した秦(紀元前778年~紀元前206年)の始皇帝に対して、「東方の三神山に長生不老(不老不死)の霊薬がある」と具申し、始皇帝の命を受け、3,000人の童男童女(若い男女)と百工(多くの技術者)を従え、五穀の種を持って、東方に船出し、「平原広沢(広い平野と湿地)」を得て王となり戻らなかったとの記述が、司馬遷の『史記』の巻百十八『淮南衝山列伝』にある。日本側からみると、これがいわゆる「徐福伝説」で、有明海沿岸各地に徐福伝説が残されている。なお徐福の来訪地といわれるところは、日本の各所にある。
この伝説を素直に読めば、中国から東方に向けて、3000人が移住したわけで、東方とは日本列島であると推定される根拠がある。すなわち、中国側から「徐福伝説」を読み解くと、中国に古くから伝わる「東方憧憬信仰」の1つだ考えることが自然である。東方に方士を差し向けたことは、始皇帝が最初ではない。
古代中国では、東方に理想郷もしくは不老不死の国があるという東方憧憬信仰が、秦の建国以前から信じられていた。周代(紀元前1046年頃~紀元前771年)に、倭人と越人が交流し、倭人が暢を貢いだことが、後漢代の江南の学者王充の『論衡』にある。暢(草)とは神聖な祭事に欠かせない薬草もしくは神酒だといわれている。暢を東方の倭人が貢いだという情報が、東方憧憬信仰の形成要因の1つとなった可能性もあるし、併せて、江南地方と倭の交易ネットワークが、周の時代には整備されていたとも考えられる。
◎「家船」と「蛋民」
西海地方に近年まで残っていた家船(えぶね)といわれる水上生活者の存在を、中国南部の水上生活者(=「蛋民」)と比較する研究も進められている。蛋民研究も西海地方と江南地方を結びつける手掛かりの1つだと考えられている。
◎水稲栽培は中国江南地方からこの地にもたらされたのか?
いずれにしても、西海地方は、日本列島における弥生文化の最先端地域の1つだった。ならば、西海地方における稲作技術の受容については、どのような状況であったのだろうか。
稲作技術の流入経路としては、①華北説、②華中説、③華南説の3説がある。①は、大陸文化流入の「朝鮮半島ルート」に、②が「江南ルート」に、それぞれ対応する。③は柳田国男が唱えた「海上の道」説で、中国広東省から台湾~南西諸島(沖縄)を経て南九州に入ったとするルートであるが、今日の学会では支持者は少なく、稲作流入でも、②華中説=「江南ルート」が主流である。
日本最古の水田址遺跡は特定されていないが、弥生時代前期初頭の水田遺構は、福岡平野の板付遺跡や野多目遺跡、早良平野の橋本一丁田遺跡等で発見されている。また、縄文後期中葉に属する岡山県南溝手遺跡や同県津島岡大遺跡の土器胎土内からイネのプラント・オパールが発見されたことにより、紀元前約3500年前から陸稲(熱帯ジャポニカ)による稲作が行われていたとする学説が有力となっている。いずれにしても、稲作関連の遺構は、西海地方からの発見ではない。近年の研究では、水稲栽培で定義される弥生時代の始まりが、紀元前10世紀まで遡る可能性を指摘する。
[2]遣唐使と西海地方
時代はくだって、中国に強大な唐王朝(618年~907年)が成立。倭国はこの文化先進国から学問・政治制度、技術等を学ぶため、遣唐使を派遣した。彼らが唐に向かう遣唐使船は、西海地方の美美良久(みみらく)=福江島三井楽から出航した。西海地方は、奈良・平安時代における大陸・東シナ海世界の一環にあった。
[3]倭寇が跋扈する海域
中世になると、中国江南地方、朝鮮半島南部海岸地域、済州島、壱岐・対馬、西海地方を含めた海域は、倭寇が勢力を振るう圏域となった。倭寇とは同海域において、漁撈、交易、海賊行為を行った人々の総称と考えられ、必ずしも倭人とは限らない。倭寇は国家統治や国境を意識しない自由な民であり、まさにグローバルに経済活動を行った集団だった。
[4]近世、大航海時代と西海地方
中世末(1543年)、ポルトガル人が種子島に漂着して以降、日本は大航海時代の西欧世界と接触を開始した。1570年には長崎が開港し、1549年にはイエズス会のフランシスコ・ザビエルが日本にやってきた。16世紀なると、西海地方は、日本が産する銀を求めるスペイン、ポルトガルが行う世界貿易の一環に組み込まれ、世界貿易と同時にキリスト教(カトリック)が西海地方に伝えられた。キリスト教布教の本格化とともに、長崎、平戸、五島列島、天草地方等々に教会、聖堂が建設されたりしたが、秀吉によって「禁教令」が発せられ、キリスト教は弾圧対象となった。以降、長崎は江戸幕府の鎖国政策の中にあっても、朝鮮貿易、オランダ貿易の日本で唯一の窓口=世界貿易港であり続けた。
本書によって、西海地方は、古代から近世に至るまで、日本列島内において、最もドラスティックに海外と接触を続けた地域であったことを知る。
2010年6月8日火曜日
2010年6月7日月曜日
『1Q84』
●村上春樹[著] ●新潮社 ●Book1~2 1800円 Book3 1900円(いずれも税別)



民主党のトップ二人が辞任した背景に何があるのか、実際のところはわからない。参院選に向けたイメージチェンジだというのが一般的見方だ。おそらく、その解釈で正しいのである。がしかし、どうにも不自然ではないか。
政権交代後の民主党を追い込んだのは、検察とマスコミが一体化した、鳩山と小沢に対する執拗な追及であり、追求の大義名分は“政治とカネ”だった。とりわけ、小沢一郎に対する検察とマスコミの追求は常軌を逸していた。小沢一郎という政治家は大衆に理解しにくいところがあるといわれるし、いかにも強面で、裏がありそうに見える。小沢一郎の顔が嫌だという人もいる。
危険なベストセラー『1Q84』
ところで、再び『1Q84』である。昨年、Book1~Book2が超ベストセラーとなり、今年の4月に続編のBook3が刊行された大作である。同書に関しては様々な解釈がなされているものの、天吾という青年と青豆という「殺し屋」の女性との純愛が大筋を構成するという見方に異論は生じないだろう。しかし、純愛というテーマでは割り切れない危険な要素が、この小説には散りばめられているように思う。フィクション、伝奇物語、現代の御伽噺・・・ではすまされない。とりわけ、BOOK3において、大きく扱われる牛河という私立探偵(調査員)に係る作者(村上春樹家)の人物像の付与については、看過できないものがある。
物語は、青豆がある謎の老婦人の依頼を受け、「さきがけ」という教団のリーダーを殺害(リーダーは自殺したとも解されるが)したところから大きく展開する。(「さきがけ」はオウム真理教を、そして、そのリーダーは麻原彰晃をイメージさせるが、そのことは物語の大筋に関与しない。)
教団のリーダーの抹殺を青豆に依頼した老婦人については、DV被害女性を救済するためには何でも実行する謎の大金持ちという設定である。この老婦人は、教団のリーダーが何人もの少女を淫行しているという疑いをもち、少女たちを守るため、青豆に殺害を依頼したことになっている。青豆はリーダーの殺害にいちおうは成功するが、その結果、教団から追われることになる。
牛河については、教団側が青豆の居場所を探すために雇った調査員という設定である。作者(村上春樹)が牛河に付与したキャラクターは、以下のとおり。
ここに挙げた牛河に関する描写は、同書中のごく一部にすぎない。このような描写がしばしば繰り返される。「彼を見た者のだれもが嫌悪を抱く」と、作者(村上春樹)はこの小説中、執拗に何度も何度も繰り返して、その醜さを強調する。なぜ、牛河の醜さがこうまで、強調されなければならないのか、最初のうちは理解しにくい。
牛河は、物語の終幕近く、彼が青豆の居場所を発見する寸前、青豆の雇い主である謎の老婦人が差し向けたタマルというボディーガードに殺されてしまう。醜悪な牛河の手によって、青豆が教団に差し出される寸前、牛河がタマルによって窒息死させられる場面には、多くの読者が拍手を送り、快感を覚えたに違いない。
ボディーガード・タマルのキャラクターは、完璧な仕事人で、青豆を助けるためにあらゆる援助を惜しまない者であり、肉体的にも精神的にも美しいゲイである。タマルは、拳銃、食料、衣服等々青豆が逃走するに必要な物品の調達から、隠れ家の手配、そして、ついには、青豆や老婦人を脅かす調査員(牛河)の抹殺まで、ありとあらゆる仕事を完璧にやってみせる。いわゆる、その道のプロ(殺し屋)だ。たとえば、イスラエルの特殊部隊(モサド)を髣髴させる。
『1Q84』の第一の特徴は、美と醜の二元論が貫徹している小説であることだ。「美」に属する者は、青豆、天吾、謎の老婦人、タマル、フカエリであり、「醜」は、牛河、天吾の父親(NHKの集金人)、青豆の母親(証人会という信仰宗教の信者)であり、天吾の下宿の住民であり、その他諸々の生活者たちだ。
第二の特徴は、「正」と「悪」が倒錯した世界であることだ。青豆がDV被害女性救済のため、謎の老婦人に雇われた殺し屋であることは既に書いた。それはそれで、マンガであるのだから、問題とするに及ばない。しかし、青豆が教団のリーダーを殺害(リーダーは自らが殺されることを容認していたとしても)したことは、錯誤による殺人であって、老婦人、青豆に義はない。さきがけ教団のリーダーは、淫行犯ではなかったのだから。
リーダーを殺された教団がその犯人=青豆を捕らえようとすることは当然の措置であり、義は教団の側にある。青豆は錯誤によって無益な(物語上は極めて重要だが)殺人を犯した者にすぎない。教団が警察を恃まずに内々で殺人犯をとらえるため、私立探偵(=牛河)を雇うことも当然(義)であり、牛河が青豆を追いかけることも当然(義)だ。
ところが、牛河は、その醜さゆえに、義をもたない側、錯誤に基づいて教団のリーダーを抹殺した側=老婦人(その代行者タマル)によって、逆に殺害されてしまう。青豆は牛河の殺害に直接関与していないとはいえ、青豆が天吾との純愛を追求するという利己的欲求のため、青豆を追いつめんとした牛河を死に至らしめたことは明白だ。牛河を殺したのは、謎の老婦人に司直の手が及ぶことを阻止しようとしたタマルによってであるが、牛河を死に至らしめた主因は、前出のとおり、青豆の身勝手さ(純愛の貫徹の欲望)からだ。
読者は、村上春樹が周到に準備した毒素によって、醜悪な牛河が抹殺される場面に快感を覚え拍手をし、安堵する。正義と邪悪とが倒錯した世界が村上と読者の間で共有され、醜悪な者に対するスティグマが一掃されることを喜びあう世界が完成する。
前出のとおり、タマルはモサドをイメージする。パレスチナのテロが失敗と多くの犠牲を伴う反面、イスラエルが公然と行うパレスチナ人民に対するテロは完璧であり、モサド側の犠牲を伴わずになしとげられる。イスラエル、西欧及び米国からみれば、アラブ・パレスチナは醜悪であり、スティグマの対象である(オリエンタリズム)。
『1Q84』にはいろいろな解釈が可能のようであり、それぞれの解釈が文芸評論家等々によって開陳されている。しかし、牛河がタマルに殺害される箇所は、「美」が「醜」に対して、無条件に優位にあるという村上春樹の前提によって描かれた世界だ。邪悪と正義の倒錯が完成され、「醜」の抹殺、つまり、スティグマの解消が快感を伴って許容される世界だ。この牛河抹殺の箇所こそが、「村上ワールド」の完成の場面なのだ。スティグマを一掃するためには、理由も理屈も要らない、美しいものが醜いものを排除することが快い――という世界観が達成された場面にほかならない。
小沢排除に通じる『1Q84』の人間観
人々は、生活、倫理、法といった、面倒くさいものを日々払いのけたいと願い、美が醜に勝るという価値観をもって、そのとおりに、すなわち「自由」に、行動することを望む。「醜」なる者が唱える理屈(理論、仕事、作品)はその存在に規定されて「醜」であるに違いないと盲信し、スティグマを一掃する扇動に身を委ねたがっている。
これまで、マスコミは、小沢一郎の政策や理念をたった一行も報道しない代わりに、繰り返し、彼のイメージ(醜)に従って、報道の基準とした。マスコミは、小沢一郎を論理的・政治的にではなく、美醜の基準で抹殺した。と同時に、人々は、小沢一郎をその外見等々によって嫌悪した。彼の辞任(排除)に安堵し、彼の政治的退場に喝采を送っている。このことは、日本の言論界が「村上ワールド」そのものになっていることを意味しないだろうか。『1Q84』は極めて危険なベストセラーなのである。



民主党のトップ二人が辞任した背景に何があるのか、実際のところはわからない。参院選に向けたイメージチェンジだというのが一般的見方だ。おそらく、その解釈で正しいのである。がしかし、どうにも不自然ではないか。
政権交代後の民主党を追い込んだのは、検察とマスコミが一体化した、鳩山と小沢に対する執拗な追及であり、追求の大義名分は“政治とカネ”だった。とりわけ、小沢一郎に対する検察とマスコミの追求は常軌を逸していた。小沢一郎という政治家は大衆に理解しにくいところがあるといわれるし、いかにも強面で、裏がありそうに見える。小沢一郎の顔が嫌だという人もいる。
危険なベストセラー『1Q84』
ところで、再び『1Q84』である。昨年、Book1~Book2が超ベストセラーとなり、今年の4月に続編のBook3が刊行された大作である。同書に関しては様々な解釈がなされているものの、天吾という青年と青豆という「殺し屋」の女性との純愛が大筋を構成するという見方に異論は生じないだろう。しかし、純愛というテーマでは割り切れない危険な要素が、この小説には散りばめられているように思う。フィクション、伝奇物語、現代の御伽噺・・・ではすまされない。とりわけ、BOOK3において、大きく扱われる牛河という私立探偵(調査員)に係る作者(村上春樹家)の人物像の付与については、看過できないものがある。
物語は、青豆がある謎の老婦人の依頼を受け、「さきがけ」という教団のリーダーを殺害(リーダーは自殺したとも解されるが)したところから大きく展開する。(「さきがけ」はオウム真理教を、そして、そのリーダーは麻原彰晃をイメージさせるが、そのことは物語の大筋に関与しない。)
教団のリーダーの抹殺を青豆に依頼した老婦人については、DV被害女性を救済するためには何でも実行する謎の大金持ちという設定である。この老婦人は、教団のリーダーが何人もの少女を淫行しているという疑いをもち、少女たちを守るため、青豆に殺害を依頼したことになっている。青豆はリーダーの殺害にいちおうは成功するが、その結果、教団から追われることになる。
牛河については、教団側が青豆の居場所を探すために雇った調査員という設定である。作者(村上春樹)が牛河に付与したキャラクターは、以下のとおり。
外見において、牛河は例外的な存在だった。背が低く、頭が大きくいびつで、髪がもしゃもしゃと縮れていた。脚は短く、キュウリのように曲がっていた。眼球が何かにびっくりしたみたいに外に飛び出し、首のまわりには異様にむっくりと肉がついていた。眉毛は濃くて大きく、もう少しでひとつにくっつきそうになっていた。それはお互いを求め合っている二匹の大きな毛虫のように見えた。学校の成績はおおむね優秀だったが、科目によってむらがあり、運動はとにかく苦手だった。(P250)
醜い少年は歳月の経過とともに成長して醜い青年となり、いつしか醜い中年男となった。人生のどの段階にあっても、道ですれ違う人々はよく振り返って彼を見た。子供たちは遠慮なくじろじろと正面から彼の顔を眺めた。醜い老人になってしまえばもうそれほど人目を惹くことはないのではないかと、牛河はときどき考える。老人というものはたいてい醜いものだから、・・・(P254)
ここに挙げた牛河に関する描写は、同書中のごく一部にすぎない。このような描写がしばしば繰り返される。「彼を見た者のだれもが嫌悪を抱く」と、作者(村上春樹)はこの小説中、執拗に何度も何度も繰り返して、その醜さを強調する。なぜ、牛河の醜さがこうまで、強調されなければならないのか、最初のうちは理解しにくい。
牛河は、物語の終幕近く、彼が青豆の居場所を発見する寸前、青豆の雇い主である謎の老婦人が差し向けたタマルというボディーガードに殺されてしまう。醜悪な牛河の手によって、青豆が教団に差し出される寸前、牛河がタマルによって窒息死させられる場面には、多くの読者が拍手を送り、快感を覚えたに違いない。
ボディーガード・タマルのキャラクターは、完璧な仕事人で、青豆を助けるためにあらゆる援助を惜しまない者であり、肉体的にも精神的にも美しいゲイである。タマルは、拳銃、食料、衣服等々青豆が逃走するに必要な物品の調達から、隠れ家の手配、そして、ついには、青豆や老婦人を脅かす調査員(牛河)の抹殺まで、ありとあらゆる仕事を完璧にやってみせる。いわゆる、その道のプロ(殺し屋)だ。たとえば、イスラエルの特殊部隊(モサド)を髣髴させる。
『1Q84』の第一の特徴は、美と醜の二元論が貫徹している小説であることだ。「美」に属する者は、青豆、天吾、謎の老婦人、タマル、フカエリであり、「醜」は、牛河、天吾の父親(NHKの集金人)、青豆の母親(証人会という信仰宗教の信者)であり、天吾の下宿の住民であり、その他諸々の生活者たちだ。
第二の特徴は、「正」と「悪」が倒錯した世界であることだ。青豆がDV被害女性救済のため、謎の老婦人に雇われた殺し屋であることは既に書いた。それはそれで、マンガであるのだから、問題とするに及ばない。しかし、青豆が教団のリーダーを殺害(リーダーは自らが殺されることを容認していたとしても)したことは、錯誤による殺人であって、老婦人、青豆に義はない。さきがけ教団のリーダーは、淫行犯ではなかったのだから。
リーダーを殺された教団がその犯人=青豆を捕らえようとすることは当然の措置であり、義は教団の側にある。青豆は錯誤によって無益な(物語上は極めて重要だが)殺人を犯した者にすぎない。教団が警察を恃まずに内々で殺人犯をとらえるため、私立探偵(=牛河)を雇うことも当然(義)であり、牛河が青豆を追いかけることも当然(義)だ。
ところが、牛河は、その醜さゆえに、義をもたない側、錯誤に基づいて教団のリーダーを抹殺した側=老婦人(その代行者タマル)によって、逆に殺害されてしまう。青豆は牛河の殺害に直接関与していないとはいえ、青豆が天吾との純愛を追求するという利己的欲求のため、青豆を追いつめんとした牛河を死に至らしめたことは明白だ。牛河を殺したのは、謎の老婦人に司直の手が及ぶことを阻止しようとしたタマルによってであるが、牛河を死に至らしめた主因は、前出のとおり、青豆の身勝手さ(純愛の貫徹の欲望)からだ。
読者は、村上春樹が周到に準備した毒素によって、醜悪な牛河が抹殺される場面に快感を覚え拍手をし、安堵する。正義と邪悪とが倒錯した世界が村上と読者の間で共有され、醜悪な者に対するスティグマが一掃されることを喜びあう世界が完成する。
前出のとおり、タマルはモサドをイメージする。パレスチナのテロが失敗と多くの犠牲を伴う反面、イスラエルが公然と行うパレスチナ人民に対するテロは完璧であり、モサド側の犠牲を伴わずになしとげられる。イスラエル、西欧及び米国からみれば、アラブ・パレスチナは醜悪であり、スティグマの対象である(オリエンタリズム)。
『1Q84』にはいろいろな解釈が可能のようであり、それぞれの解釈が文芸評論家等々によって開陳されている。しかし、牛河がタマルに殺害される箇所は、「美」が「醜」に対して、無条件に優位にあるという村上春樹の前提によって描かれた世界だ。邪悪と正義の倒錯が完成され、「醜」の抹殺、つまり、スティグマの解消が快感を伴って許容される世界だ。この牛河抹殺の箇所こそが、「村上ワールド」の完成の場面なのだ。スティグマを一掃するためには、理由も理屈も要らない、美しいものが醜いものを排除することが快い――という世界観が達成された場面にほかならない。
小沢排除に通じる『1Q84』の人間観
人々は、生活、倫理、法といった、面倒くさいものを日々払いのけたいと願い、美が醜に勝るという価値観をもって、そのとおりに、すなわち「自由」に、行動することを望む。「醜」なる者が唱える理屈(理論、仕事、作品)はその存在に規定されて「醜」であるに違いないと盲信し、スティグマを一掃する扇動に身を委ねたがっている。
これまで、マスコミは、小沢一郎の政策や理念をたった一行も報道しない代わりに、繰り返し、彼のイメージ(醜)に従って、報道の基準とした。マスコミは、小沢一郎を論理的・政治的にではなく、美醜の基準で抹殺した。と同時に、人々は、小沢一郎をその外見等々によって嫌悪した。彼の辞任(排除)に安堵し、彼の政治的退場に喝采を送っている。このことは、日本の言論界が「村上ワールド」そのものになっていることを意味しないだろうか。『1Q84』は極めて危険なベストセラーなのである。
2010年6月6日日曜日
W辞任
政権与党・民主党の代表(鳩山)と幹事長(小沢)の二人が同時に(W)辞任した。後任の代表は菅直人(現副総理)に決まった。国会での指名後、菅首相が誕生する。
辞任した鳩山首相の場合、普天間問題への取組み方及びその結論が不透明かつ不可解であった。取組み方、その結果導かれた結論は、国民の理解を得にくいものだった。しかし、普天間移転問題というのは、旧政権の場合、結論を十数年放置したままであったわけで、その間、那覇の中心街に米軍が駐留し基地を使用し続けていたわけであるから、自民党に批判する資格はないし、鳩山が移転を急いだことは間違っていない。
「移転」に反対する人はいない。沖縄に行ったことのある人ならば、普天間基地の危険性は自明のことである。移転先として、鳩山が「沖縄県外」と主張したことも間違っていない。沖縄にこれ以上基地負担を押し付け続けることは、公平性に欠ける。鳩山がその解決のために真正面から取り組もうとした姿勢に間違いはない。
しかし、結論を5月末に設定したこと、そして、代替地案の模索・公表の過程については、迷走以外のなにものでもなかった。さらに驚くべき事実として、日本中が、普天間の移転先であることを公然と拒否したことを挙げなければならない。沖縄の人々の基地負担を考慮するならば、公然と反対を唱えることを憚るのが一般的感受性だと思う。沖縄ならいいが、自分たちのところは困る、という主張は、公然たる沖縄差別にほかならない。そうした地域のエゴイズムについて、少なくとも、日本のマスメディア及び野党自民党は同調した。というよりも、受入れ拒否を公然と支持した。マスメディアと自民党は、「沖縄差別」を扇動した。そのことの深刻さを、国民の誰一人が感じていないことが情けない。
ご存知のとおり、辞任直前、鳩山は普天間基地の移転先を同じ沖縄県の辺野古と定め、米国と同意した。「最低でも県外」という鳩山の思惑は実現せず、自民党政権時代の「辺野古」に逆戻りした。このことが「辞任」の主因の1つだといっていいだろう。
不可解なのは、「辺野古」に逆戻りした言い訳である。鳩山の表現は、筆者にはよく理解できない内容だった。普天間に駐屯している海兵隊の一部はグアムに移動することが決まっている。残留が決まったわずかばかりの米海兵隊について、鳩山はなんと「抑止力」だと改めて“再定義”をしたのだ。それだけではない。鳩山は、「(そのことを)勉強しなおした結果、抑止力であることが改めて認識できた」と弁明した。この言葉は、鳩山の移転の意図を潰した“大きな力”の存在をうかがわせる。鳩山は挫折を余儀なくされた。
普天間基地移転問題は、本質の議論がないまま政局として大きく報道され、鳩山の“辞任”をもって終焉した。しかし、この一連の騒動を自然だと感じる人はそう多くはないと思う。普通の感性の人ならば、なんとも不可解・不自然な流れだと思うはずだ。その不可解さは、おそらくは、日米の力関係の帰結だと想像する以外に解釈のしようがない。
この問題に関する日本のマスコミ報道を振り返ると、米軍駐留の本質に係る議論は一切なかったといっていいすぎでない。日米同盟のあり方、米軍の駐留の是非、日本の防衛のあり方・・・基地問題=沖縄問題の解決とは、日米関係そのものを問うところから始めなければならなかったはずなのだが。
一方、鳩山が意図したであろう(と想像する)普天間移転問題の解決プログラムは、国民の総意として、米軍の駐留を拒絶する情況をつくりだすことではなかったか。鳩山は米軍の駐留を拒絶すること=米軍基地なき日本国の実現に向け、その第一弾として、普天間問題に着手しようとしたのではないか。普天間問題とは、「駐留なき同盟」を実現する第一歩なのだと。鳩山が「抑止力について勉強する前」、すなわち、昨年の総選挙までは、「(普天間問題は)少なくとも(沖縄)県外」だと公言していたことから、そのことは十分想像がつく。
前出のとおり、鳩山の最終目標は、「(米軍の)駐留なき(日米)同盟の(実現)」だったように思う。彼は手始めに沖縄の普天間基地を県外に移転させ、そのことによる、国民的支持――対等な日米関係を待望するナショナリズムの台頭――をもって、駐留なき同盟の実現のための足元を固めたかったに違いない。鳩山は、そういう意味で、ナショナリストなのである。ところが、鳩山(政権)は、かつて鳩山同様に対等な日米関係の実現に向けて暴走し崩壊した、細川政権と同じ道を歩んだ。細川(当時首相)の後ろにいたのが、鳩山とともに民主党幹事長職を辞した、“小沢一郎”その人であることは偶然ではない。
民主党政権誕生後から今日まで、鳩山と小沢の二人に対しては、検察とマスコミによる、執拗なまでのネガティブキャンペーンが続いた。細川の場合も、政治とカネのスキャンダルが騒がれたし、それと同様の手法として、田中角栄の失脚(ロッキード事件)も思い出される。田中角栄が首相のとき、彼は米国と厳しく対立した。そのことは、このコラムで何度も書いたので繰り返さない。
田中、細川、そして鳩山・小沢が政権の座を追われた構図は、それぞれの政治信条やイデオロギー、対立する団体等々の動きとは関係していない。民主党政権の誕生によって、たとえば、国民生活が著しく不安定化したとか、増税があったとか、景気が後退したという現象は生じていない。鳩山と小沢の退陣は、「政治とカネ」という国民の間に生じたスティグマ(嫌悪感)による。しかも、その嫌悪感は、マスコミによって誘導された「民意」によっている。小沢に対する嫌悪感とは、検察とマスコミから一方的に流される「報道」によって醸成されたものであって、国民(生活)の危機(感)からではない。
マスコミの攻撃を受けた3人の首相(及び小沢)に共通点があるとしたら、ただ一点、彼らがともに“米国離れ”を志向した政治家であった、ということだけだ。
辞任した鳩山首相の場合、普天間問題への取組み方及びその結論が不透明かつ不可解であった。取組み方、その結果導かれた結論は、国民の理解を得にくいものだった。しかし、普天間移転問題というのは、旧政権の場合、結論を十数年放置したままであったわけで、その間、那覇の中心街に米軍が駐留し基地を使用し続けていたわけであるから、自民党に批判する資格はないし、鳩山が移転を急いだことは間違っていない。
「移転」に反対する人はいない。沖縄に行ったことのある人ならば、普天間基地の危険性は自明のことである。移転先として、鳩山が「沖縄県外」と主張したことも間違っていない。沖縄にこれ以上基地負担を押し付け続けることは、公平性に欠ける。鳩山がその解決のために真正面から取り組もうとした姿勢に間違いはない。
しかし、結論を5月末に設定したこと、そして、代替地案の模索・公表の過程については、迷走以外のなにものでもなかった。さらに驚くべき事実として、日本中が、普天間の移転先であることを公然と拒否したことを挙げなければならない。沖縄の人々の基地負担を考慮するならば、公然と反対を唱えることを憚るのが一般的感受性だと思う。沖縄ならいいが、自分たちのところは困る、という主張は、公然たる沖縄差別にほかならない。そうした地域のエゴイズムについて、少なくとも、日本のマスメディア及び野党自民党は同調した。というよりも、受入れ拒否を公然と支持した。マスメディアと自民党は、「沖縄差別」を扇動した。そのことの深刻さを、国民の誰一人が感じていないことが情けない。
ご存知のとおり、辞任直前、鳩山は普天間基地の移転先を同じ沖縄県の辺野古と定め、米国と同意した。「最低でも県外」という鳩山の思惑は実現せず、自民党政権時代の「辺野古」に逆戻りした。このことが「辞任」の主因の1つだといっていいだろう。
不可解なのは、「辺野古」に逆戻りした言い訳である。鳩山の表現は、筆者にはよく理解できない内容だった。普天間に駐屯している海兵隊の一部はグアムに移動することが決まっている。残留が決まったわずかばかりの米海兵隊について、鳩山はなんと「抑止力」だと改めて“再定義”をしたのだ。それだけではない。鳩山は、「(そのことを)勉強しなおした結果、抑止力であることが改めて認識できた」と弁明した。この言葉は、鳩山の移転の意図を潰した“大きな力”の存在をうかがわせる。鳩山は挫折を余儀なくされた。
普天間基地移転問題は、本質の議論がないまま政局として大きく報道され、鳩山の“辞任”をもって終焉した。しかし、この一連の騒動を自然だと感じる人はそう多くはないと思う。普通の感性の人ならば、なんとも不可解・不自然な流れだと思うはずだ。その不可解さは、おそらくは、日米の力関係の帰結だと想像する以外に解釈のしようがない。
この問題に関する日本のマスコミ報道を振り返ると、米軍駐留の本質に係る議論は一切なかったといっていいすぎでない。日米同盟のあり方、米軍の駐留の是非、日本の防衛のあり方・・・基地問題=沖縄問題の解決とは、日米関係そのものを問うところから始めなければならなかったはずなのだが。
一方、鳩山が意図したであろう(と想像する)普天間移転問題の解決プログラムは、国民の総意として、米軍の駐留を拒絶する情況をつくりだすことではなかったか。鳩山は米軍の駐留を拒絶すること=米軍基地なき日本国の実現に向け、その第一弾として、普天間問題に着手しようとしたのではないか。普天間問題とは、「駐留なき同盟」を実現する第一歩なのだと。鳩山が「抑止力について勉強する前」、すなわち、昨年の総選挙までは、「(普天間問題は)少なくとも(沖縄)県外」だと公言していたことから、そのことは十分想像がつく。
前出のとおり、鳩山の最終目標は、「(米軍の)駐留なき(日米)同盟の(実現)」だったように思う。彼は手始めに沖縄の普天間基地を県外に移転させ、そのことによる、国民的支持――対等な日米関係を待望するナショナリズムの台頭――をもって、駐留なき同盟の実現のための足元を固めたかったに違いない。鳩山は、そういう意味で、ナショナリストなのである。ところが、鳩山(政権)は、かつて鳩山同様に対等な日米関係の実現に向けて暴走し崩壊した、細川政権と同じ道を歩んだ。細川(当時首相)の後ろにいたのが、鳩山とともに民主党幹事長職を辞した、“小沢一郎”その人であることは偶然ではない。
民主党政権誕生後から今日まで、鳩山と小沢の二人に対しては、検察とマスコミによる、執拗なまでのネガティブキャンペーンが続いた。細川の場合も、政治とカネのスキャンダルが騒がれたし、それと同様の手法として、田中角栄の失脚(ロッキード事件)も思い出される。田中角栄が首相のとき、彼は米国と厳しく対立した。そのことは、このコラムで何度も書いたので繰り返さない。
田中、細川、そして鳩山・小沢が政権の座を追われた構図は、それぞれの政治信条やイデオロギー、対立する団体等々の動きとは関係していない。民主党政権の誕生によって、たとえば、国民生活が著しく不安定化したとか、増税があったとか、景気が後退したという現象は生じていない。鳩山と小沢の退陣は、「政治とカネ」という国民の間に生じたスティグマ(嫌悪感)による。しかも、その嫌悪感は、マスコミによって誘導された「民意」によっている。小沢に対する嫌悪感とは、検察とマスコミから一方的に流される「報道」によって醸成されたものであって、国民(生活)の危機(感)からではない。
マスコミの攻撃を受けた3人の首相(及び小沢)に共通点があるとしたら、ただ一点、彼らがともに“米国離れ”を志向した政治家であった、ということだけだ。
2010年6月4日金曜日
登録:
コメント (Atom)