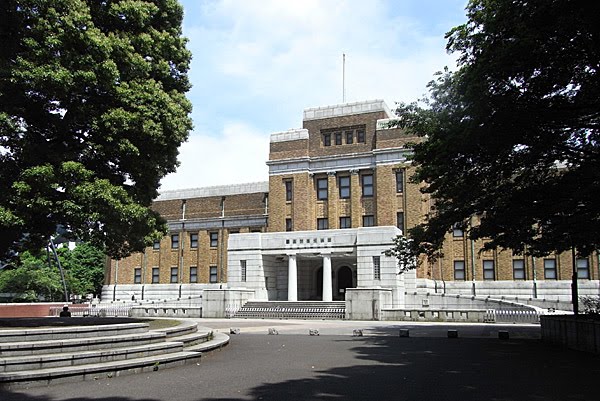沖縄については、ヤマト人の立場から、柳田国男、折口信夫、岡本太郎、谷川健一、吉本隆明らの知の巨人たちが、自らの思想の拠点の確認対象の1つとして、積極的に言及してきた。
1960年代くらいまでの沖縄には、日本の基層を感じさせる生活風土が現存していたような気がする。1920年代、柳田民俗学において創出された「沖縄学」は、柳田が沖縄本島から先島を訪問したときの直感がそのスタートになったものと推測する。そのときの沖縄には、本土では消失してしまった「原日本」がアクチュアルにとどまっていたのではないか。
柳田・折口の「沖縄学」の確立が意味するものは何か――という反省的論及が今日まで、いくつかなされてきた。その中には、柳田は、沖縄を無条件に「日本」に取り込む思想的土台を築いた――日本を「南方」へと拡大するための植民地経営の学だったという指摘もある。柳田・折口の「沖縄学」にロマン主義的傾向を認めないわけではないが、二人が沖縄に言及しなかったならば、日本の民俗学、歴史学、文学は、いまよりかなり貧しいものとなったはずだ。
時代はくだって、米軍占領下の沖縄が日本に返還されようとした1970年代初頭、そのとき、沖縄とは何か、戦後日本とは何かが厳しく問われた時代だった。
日本の明治以降の近代化は、古代的天皇制を混合した、独自の統治のあり方を世界史上にとどめている。簡単に言えば、日本は、あの悲惨な“ヒロシマ”を経験してもなお今日まで、共和制国家を志向することがない。
1960~1970年にかけて、日本の左翼が「革命」を夢想する一方、共同体=国家論が複眼的視座で問われた。そして、そのとき、レーニンの『国家と革命』に代表される機能的国家論の相対化の思想的拠点として、沖縄が再びクローズアップされた。日本の基層をとどめる沖縄を「再発見」することをもって、日本(共同体)の国家と権力の源泉を問わんとした。そればかりではない。マルクス・レーニン主義に疲れた転向左翼の一部は民俗学に傾倒し、とりわけ、沖縄から、日本国及び天皇制を問わんとした。古琉球の原始共同体を、「(天皇制)日本」を無化する実体だと看做そうとした。このことについては、後述するが、琉球王府樹立後、その権力構造は、世俗的王権(兄)と聞得大君(妹)の司祭権とが並立する形式として完成した。エケリ(兄=男神)とオナリ(妹=女神)である。この構造は、古琉球における原始的共同体=シマの権力構造が洗練化され、王府に反映し制度化されたものだ。基層をとどめる制度は琉球王府にあり、ヤマトの天皇制にはない、ヤマトの王権(天皇制度)は、基層において、いまのあり方とは異なっていた--という確信が、その正統性を疑う根拠とされ、琉球王府のほうに正統性を感じたのである。
さて、古代倭国の王国の1つである邪馬台国について、『魏志倭人伝』は、以下のとおり記している。
■その國、本また男子を以て王となし、住まること七、八十年。倭國乱れ、相攻伐すること歴年、乃ち共に一女子を立てて王となす。名付けて卑弥呼という。鬼道に事え、能く衆を惑わす。年已に長大なるも、夫婿なく、男弟あり、佐けて國を治む。王となりしより以来、見るある者少なく、婢千人を以て自ら侍せしむ。ただ男子一人あり、飲食を給し、辞を伝え居処に出入す。宮室・楼観・城柵、厳かに設け、常に人あり、兵を持して守衛す。■
卑弥呼が統治したとされる邪馬台国の王権の構造もまた、女帝(姉)=卑弥呼と、それをたすけて統治に関与する男帝(弟)の並立にあった。卑弥呼は「鬼道につかえ」というから、宗教的な儀式や卜を旨としたに違いない。日本列島の某所にあったとされる古代王国・邪馬台国の権力構造は、後年樹立された沖縄王府のそれと同一であった。女帝・男帝の並立は、前出のとおり、古琉球のシマの統治形式を始原としたものが、琉球王府に制度化された統治構造である。
(1)沖縄とはなにか
沖縄の神話、民話、伝承によれば、シマ(始原の共同体)を起こした人間は一対の男女であり、その関係は兄妹だとされる。「おなり(姉妹の神)」「えけり(兄弟の神)」である。「おなり」は守護する者であり、「えけり」は守護される者である。「おなり」は「にーがん(根神)」となって次世代に継承され、これまた次世代へと継承されたシマの行政的首長(男性)=「にーつちゅ(根人)」を守り、この一対の男女によってシマは統治される。祖先崇拝が、沖縄の信仰の根幹をなす。
「おなり」はシマにおいて「祝女(ノロ)」として、神の言葉を伝え(神の代行者となり)、ムラの神事をとりしきり、かつ、共同体の成員の諸々の相談にのったり、厄除けをしたりして、ムラの安寧を維持する。沖縄では、女性は「おなり神」として、神の代行者であるばかりでなく、神そのものなのである。
シマには、神を祀る聖地があり、それは「御嶽(うたき)」と呼ばれる。「御嶽」はシマの根神が祀られることはもちろんだが、外来の神がオボツ山、カグラ山から降誕する聖なる空間である。外来の神は、海の彼方(=二ライ、カナイ)から、直接御嶽にやってくることもあるし、立神、岬を経て、山上であるオボツ、カグラに逗留し、シマの共同体の御嶽に祖霊神とともにやってくる。
前出の「おなり」たちは、現世において、外来の神を迎え、もてなす役割を負っている。「おなり」は外来の神と同衾することもある。また、始原の人間は、海の底もしくは海の彼方(二ライ、カナイ)からシマにやってきたのだから、死後は二ライ、カナイに戻るものと理解されている。シマの神観念は祖先崇拝と並んで、外来の神を迎えるかたちもとる。
祖霊神、外来神は人々に何をもたらすのかといえば、もちろん、富や健康をもたらすのであるが、西欧のサンタクロースのように、品物をもってやってくるわけではもちろんない。だが、農耕に重要な作物の種子や農耕具は、外来の神がもたらしたものだと伝承されている。
しかし、実際は、外来神がもってくるのは物質ではなく、「セジ」と呼ばれる霊力を人々に授ける。セジはヤマトでは「タマ」であり、タマは魂もしくは霊の字があてられる。ヤマトでは、霊力を授かる儀式をタマフリといい、怨霊を抱いた死者のタマが人々に悪事を働くことを恐れ、鎮魂に励むことをタマシズメという。
沖縄、ヤマトを問わず、人力の及ばない超越的パワーを人々は常々畏怖し、尊び、また、それを定期的に迎え入れ、歓待することによって、豊作、豊漁、安寧、子孫繁栄がもたらされると信じた。このような信仰の構造は、沖縄とヤマトの基層において異なるところがない。にもかかわらず、ヤマトで発展した神道は、女神の役割を遠ざけ、神職は男性に占有されるようになってしまった。また、明治維新以降の国家神道--その頂点とされる近代天皇制度においては、天皇は男性に限定されるようになった。しかし、日本の神話時代、古代を含めて、女神、女帝はいくらでもいたし、女帝ではないが、新羅征伐に霊威を発揮したことが伝承される、神功皇后を神女の代表的存在の一人として挙げることができる。もちろん、前出の卑弥呼が、「オナリ神」でなくてなんであろうか。
また、国文学者で沖縄学の研究者である折口信夫は『大嘗祭の本義』において、真床襲衾について考察を加えている。折口の説では、真床襲衾とは、大嘗祭の秘儀中の秘儀であり、その由来は古事記天孫降臨のニニギノミコトが赤子のまま降臨するさいに包まれていた布団のことだと説明している。さらに折口は、その布団が意味するものは、天皇が降臨する稲の霊と同衾することだ、と断じたのである。折口説の正誤を判断する力量はもちろん、もちあわせないものの、沖縄において、オナリを代行する祝女(のろ)がセジ(=たとえば稲の霊)を迎え入れ、それと同衾することは自然のことである。沖縄のノロ(祝神)の役割をヤマトの基層の信仰とみなすならば、折口の真床襲衾の解釈が根拠のないものだともいえない。
しかし、いずれにしても、ヤマトと沖縄は、基層において同根の信仰を形成しながら、時の経過とともに、袂を別ったのである。
(2)沖縄神事を代表する「イザイホー」
久高島において12年に一度の午年に行われる「イザイホー」は、沖縄の神事を最も代表するものの1つだと思われる。
久高島の集落はアガリ(東)の外間とイリー(西)の久高に分かれている。久高島は、沖縄島東南部に位置するため、古くから国人の畏怖と憧憬の対象である海上他界(二ライカナイ)に最も近い地点にあるとされ、対岸にある斎場御嶽(せいふぁうたき)と並んで、王権祭祀の二大祭場とされてきた。
イザイホーについて、本書「久高島と神事」湧上元雄[著]を参照しつつ、紹介をしておこう。
イザイホーとは、端的にいえば、島の女性祭祀集団の加入者儀礼であり、ナンチューホー(成巫儀礼)とも呼ばれる。「ホー」は呪法、儀法のホー、「イザイ」は、いざる、あさる、探る、の意で、神女の適格を判定する神判の意といわれるが、また一方、審判の意をもつとされる神事「七つ梯渡り(ななつばしわたり)」の神遊び始めた乙兼(うとうがた)の童名イザヤーによる、との2説ある。
イザイホーの概要と目的を整理しておこう(神事の詳細は、本書参照のこと)。
■久高島外間村には、始祖百名白樽(ひゃくなしらたる)と母加那志(ふぁーがなしー)夫婦の伝承があり、…(略)…「兄妹始祖型洪水神話」の類型に属している。天降り(あもり)、地中出現、津波からの生き残りを問わず、人の世の原夫婦は、原母(げんぼ)より生じた兄妹でなければならないという島建神(しまだてがみ)の伝承は、沖縄の「おなり(姉妹)神」信仰の基調をなすものであったといえよう。
それは、王権祭祀における国王と、そのおなり神の聞得大君、村落祭祀の根人と根神、家の祭りのえけり(兄弟)とおなり(姉妹)との関係においても、この原理は貫かれている。現行の門中(むんちゅう)祭祀でも、ウミナイウクディ(おみおなりおこで)とウミキーウクディ(おみえけりおこで)という一対の女神役を立てて、門中の祖霊を祀っている。
久高島のイザイホー祭りにおいても、加入儀礼を終えたナンチュ(初めて神女となった人)が、そのインキャー(いせえけりの転訛。勝れた兄弟の意)と対面するアサンマーイの儀式に、
タマガエーヌ ウプティシジ ウリティ イモーネ インキャートゥ ユティキャーシ(ナンチュに憑依した始祖霊が天降って、ナンチュの男兄弟と魂合いなされた)
というウムイ(神歌)が歌われる。
「タマガエー」とは、魂が上がった者、すなわち精霊(しょうりょう)の発動したナンチュのことで、「ウプティシジ」(おぼつせじ)は天津霊威(あまつせじ)、「ユティキャーン」は、行き逢って、の意である。ナンチュは亡祖母のシジ(セジ。霊威)を継承した者の意であるから、この儀礼は、兄妹始祖の原初の時代に立ち返って、おなりとえけりが魂合いをした、ということになろう。(P365~366)■
■イザイホーは、…(略)…冬至の太陽の死と再生という危機を呪術的に克服し、新たに祖霊のウプティシジを豊かに受け、生命力満ちあふれたナンチュが参加する神遊びによって、島の共同体や、わが子わが夫の平安・延命・繁栄の願望を現実化しようとした古代祭祀だったと思われる。(P386)■
聖地・久高島において、午年の11月15日から4日間に及ぶイザイホーは、そのスケールにおいて、また神事の演出の力において、出色のものである。また、4日間に盛り込まれたそれぞれの神事が意味するところは、沖縄・ヤマトの基層の信仰のあり方を示すものともいえる。しかしながら、島の過疎化が進み、1990年、 2002年のイザイホーは中止となっていて、1978年を最後に現在に至るまで行われていない。こんどの午年は2014年であるが、そのときイザイホーが行われるのかどうか心配である。
(3)海上の道
沖縄の稲作について触れておこう。前出の柳田国男は『海上の道』において、日本の稲作は南方から、琉球弧を、海路を使って渡ってきた集団により伝えられたものだと説いた。その後、最古の稲作遺構が北九州で発見されたこともあり、「南方説」は退けられ、朝鮮ルート、華南ルートが有力視されてきた。しかしながら、稲に関する科学的検査方法の進歩にともない、学会においても、南方説が復活する兆しをみせている。
本書の「西表島の稲作と畑作」(安渓遊地[著])では、先島で古くから栽培されている稲の種類が、ジャポニカ、インディカにも属さないブル種(ジャバニカ)に属することが推定されている。また、西表島で行われてきた牛を使った踏耕(ウシクミ)という農耕手法は、東南アジア~八重山~沖縄~ヤマト(種子島、南九州)を結びつける証拠の1つとなっている。