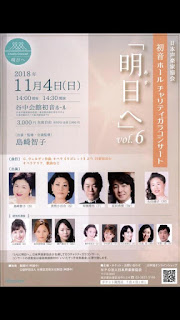アジア杯2019、筆者が優勝と予想していた韓国がカタールに負け、前回優勝国のオーストラリアが開催国UAEに負け、優勝候補の一角と目された2チームが中東勢によりベスト4進出を拒まれた。
韓国の戦力はアジアナンバーワンだと思われたが・・・
大会前、筆者は韓国の戦力はアジアで群を抜いていると思っていた。ベテランのキ・ソンヨン(ニューカッスル)、脂がのり切っているソン・フンミン(トッテナム)と、イングランド・プレミアリーグでレギュラーをはる2選手に加え、ファン・ヒチャン( ブンデスリーガ・ハンブルガーSV)ほか、欧州でプレーする選手を複数擁する韓国代表は現時点でアジア最強だと思っていた。
予選リーグではチームとしてのまとまりが見られず、攻撃のかたちが見いだせない試合が続いたが、グループCを3連勝で首位通過、貫録を見せた。危険信号が灯ったのがラウンド16のバーレーン戦。延長までもつれこんでの辛勝だった。やっぱりうまくいっていないのか、と思いつつも、だんだんと調子を上げてくるだろうと考えていた矢先の敗退だった。ベスト8をかけたカタールとの試合では、スピードある攻撃が見られず、相手の堅い守備に決定機は少なく、カタールの一発に泣いた。
ポゼッション重視のベント監督は時代遅れ
韓国の敗因としては、キ・ソンヨンの負傷離脱、3試合目から合流したソン・フンミンの過労による調整不足などが挙げられているが、代表監督のベント(ポルトガル)の指導、采配の責任を追及する声が韓国国内で強まっているようだ。
ベントの目指すサッカーはポゼッション重視。そのため、韓国の伝統的強みとされる速さ、力強さが消えてしまった。チーム全体に停滞感がひろがり、韓国の特徴である闘志あふれるプレー、たとえば球際の強さ、深いタックル、速いサイド攻撃、ペナルティーエリア内での反応の速さ…が影をひそめてしまった。
ベントが代表監督に就任して以来、韓国は負けなしだったらしいが、日本代表と同様、親善試合の結果はあてにならない。親善試合では相手の状態を考慮し、勝敗ではなくサッカーの質をしっかり見極めないと、公式戦で取り返しのつかない結果に終わる。代表監督の評価については、韓国代表で起きたことを日本も他山の石とすべきだ。韓国はベントを躊躇なく解任できるから、2022に向けてはよかったかもしれない。
ポゼッションサッカーは堅守に対応できない
今日の世界のサッカー界におけるトレンドは、W杯ロシア大会が示した堅守速攻、フィジカル重視で変わっていない。本大会における中東勢を中心とした各国の台頭は、堅守速攻、とりわけ規律の高い守備、相手が守備体形をつくる前にゴール前に攻め込む速攻を武器とするチームが増えたことによる。
堅守速攻の土台となるのは強いフィジカル。韓国のエース、ソン・フンミンが精彩を欠いたのは、年始のイングランド、プレミアリーグの過密日程による疲労からだと思われる。しかし、代表戦ではそのことは理由にならない。エースがコンディション不良ならば、代替選手がその穴を埋めなければならないし、代表監督は調整期間を設けるような選手起用を心掛けなければいけない。
韓国代表が持ち前の強いフィジカルを生かしたサッカーを捨ててしまえば、相手は脅威を感じない。韓国は原点に帰るべきだった。さて、日本はどうなるのだろうか。
2019年1月27日日曜日
2019年1月25日金曜日
森保ジャパンに未来なし――ベトナム戦は悲惨な勝利
ベスト4を賭けた日本―ベトナムは日本が1-0で辛勝した。同組のイランが中国に勝ったので、日本はイランと準決勝で相まみれる。
まだツキがある日本代表
日本に惜敗したベトナムは東南アジア王者。成長著しく、予選リーグ3位ながらノックアウトステージ(NOS)に勝ち上がり、ヨルダンをPK戦で破った。当然、勢いに乗っている。この試合、日本にとって予断は許されないと言われていたものの、ここまで日本が苦しむとは思っていなかった。
日本の決勝点はVAR(ビデオアシスタントレフリー)によるPK獲得によるもの。このPK判定について、各国で議論があったという。VARからの確認要請を受けて主審がビデオを見たとしても、堂安の転倒をファウルとみなしてPKをとる主審とそうでない主審がいたにちがいない。日本はまたまた幸運に恵まれた。既報のとおり、日本は吉田の先制得点がVARで取消しになっていたから、なんともすっきりしない勝ちだった。
この日の日本代表は試合には勝ったものの、内容は相変わらず悪い。NOSの日本の対戦相手、サウジアラビア、ベトナムにしてみれば、「相撲に勝って、勝負に負けた」と言いたくなるに違いない。
ベトナムの戦術に簡単にはまった森保ジャパン
日本がこの試合苦戦した要因の第一は、日本がベトナムの術中にはまっていた点。ベトナムは日本のパスコースを読みきっていて、ことごとく遮断した。たいへんな運動量だった。森保ジャパンはベトナムの作戦に対処できなかったが、ベトナムが納得できないVARで失点した後、彼らの足が止まってから、やっと、パスがとおりだし、前線も機能し出した。それでも、幸運なPKによる1点にとどまった。つまり、90分間を通して、日本がベトナムを完全に崩し、クリーンシュートを放ったシーンは一度もなかった。堂安の強引さが功を奏したまで。いってみれば個人プレーの結果にすぎない。フィジカルの強い対戦相手ではまずもって通用しない。
残念だが北川は代表レベルに達していない
相手がパスに対して労を惜しまず遮断してくるのなら、ワントップに当てる作戦もあった。ところが日本のワントップ(CF)として先発した北川が起点として機能しない。筆者は北川が代表に選ばれ、大迫の控えで試合に出る理由がわからない。北川の技術、闘争心はまだまだ低レベル。もっと練習してほしい。
CFの大迫に次ぐ二番手は武藤だが、彼の欠陥については前回の拙Blogで詳論したので繰り返さない。森保ジャパンのワントップは人材難だ。
森保ジャパンの最弱点はGK
森保ジャパンにおいて、結果に現れないが最も心配なウイークポイントはGK。正GKは権田らしいが、とにかく判断力が悪い。フィジカル、キャッチング、高さ、反応のレベルはJリーグの並みクラス。対戦相手ベトナムのGK、ダン・バン・ラムに比べて権田の技術、フィジカルが数段落ちることはだれの目から見ても明らかだった。日本代表のGKこそ筆者が最も心配しているポジションだ。
森保ジャパンの弱点整理
ここまでの5試合で露呈した森保ジャパンの弱点は以下のとおり。親善試合ではわからなかったが、公式戦だとはっきりする。
このアジェンダは不毛。アジアのサッカーはいま、急速に発展しつつある。視点を広げてアジアのサッカーを地域別にみると以下のとおりとなろう。
そのなかにあって、イラン、日本、韓国、オーストラリア、サウジアラビアが強豪国だった。ところが、本大会においては唯一、イランだけが抜群の強さをみせているものの、日本、韓国、オーストラリアが停滞している。日本に惜敗したサウジアラビアは、あまり変化がない。
一方、前出の全地域が急速に力をつけてきたから、強豪国といわれた5カ国との差が一気に縮まった。一般論として、世界のスポーツのレベルは年々上がっている。上位が停滞すれば、下位にひっくり返される。2019アジア杯はそのような現実を目の当たりにした感がある。
冒頭のアジェンダに対しては、日本はこれからもアジアで絶対的な強さを誇らなければだめ、という解答しかない。内容的にも結果的にも、他国を圧倒しなければ、世界に追いつけない。日本が停滞すれば、アジアから見くだされ、世界で通用しない代表チームになってしまう。後退はもちろん、停滞すら許されない。日本が森保監督のままガラパゴス化し、停滞すれば、全アジア地域との差が縮まるどころか、逆転されるのは時間の問題となる。
森保が代表監督として的確でない理由
森保が代表監督としてなぜ、適正を欠くのかといえば、彼がJリーグというローカルなクラブチームの監督の経験しかないから。森保が少なくとも他国のナショナルチームを指揮した経験があっての日本代表監督就任ならば、適職の可能性はあった。それすらないのだから、悪いのは森保ではなく、任命者ということになる。
レベルの低い国の代表チームが外国人監督を招聘する理由は、代表監督を専門職とする者がもつ視野の広さ、引き出しの多さを買ってのこと。彼らは世界中を渡り歩き、異なる言語、文化、習慣、宗教等を乗り越えながら、受託した代表チームを指導する経験をもっている。世界のサッカートレンドに敏感な彼らは、契約先固有の国民性・フィジカル・世界観と、世界のサッカートレンドを融合し、代表チームを強化するスキルを持っている。
直近の事例でいえば、世界の有能な代表監督たちは、2018W杯ロシア大会当時の世界のトレンドが堅守速攻であることを認識し、それまでのポゼッションサッカーに見切りをつけていた。日本サッカー界に向けて、2018ロシア大会開催よりもずっと前から「フィジカル重視」の発言を行っていたのは、管見の限りだが、元日本代表監督のオシムだったと記憶する。そしてロシア大会は、オシムの言葉どおりのサッカーが展開された。ことほどさように、サッカー後進国にとって、代表監督を専門職とする者の存在は、世界のサッカー潮流を知るための潜望鏡のようなものなのだ。
準決勝、森保が目指すサッカーを明確に示してほしい
森保日本代表監督が目指し、また、理想とするサッカーはどのようなものなのか。世界と合い渉れると(思い描く)日本代表のサッカースタイルはどのようなものなのか。彼は代表監督として、代表ファンにどのような言葉でそれを発信し、日本代表チームに意識づけし、代表選手のプレーに浸透させているのか。このことを次戦イランとの試合で、明確に示してほしい。それが示せなければ、森保ジャパンに未来なし――と断言できる。
まだツキがある日本代表
 |
| ベトナムの大応援団 |
日本の決勝点はVAR(ビデオアシスタントレフリー)によるPK獲得によるもの。このPK判定について、各国で議論があったという。VARからの確認要請を受けて主審がビデオを見たとしても、堂安の転倒をファウルとみなしてPKをとる主審とそうでない主審がいたにちがいない。日本はまたまた幸運に恵まれた。既報のとおり、日本は吉田の先制得点がVARで取消しになっていたから、なんともすっきりしない勝ちだった。
この日の日本代表は試合には勝ったものの、内容は相変わらず悪い。NOSの日本の対戦相手、サウジアラビア、ベトナムにしてみれば、「相撲に勝って、勝負に負けた」と言いたくなるに違いない。
ベトナムの戦術に簡単にはまった森保ジャパン
日本がこの試合苦戦した要因の第一は、日本がベトナムの術中にはまっていた点。ベトナムは日本のパスコースを読みきっていて、ことごとく遮断した。たいへんな運動量だった。森保ジャパンはベトナムの作戦に対処できなかったが、ベトナムが納得できないVARで失点した後、彼らの足が止まってから、やっと、パスがとおりだし、前線も機能し出した。それでも、幸運なPKによる1点にとどまった。つまり、90分間を通して、日本がベトナムを完全に崩し、クリーンシュートを放ったシーンは一度もなかった。堂安の強引さが功を奏したまで。いってみれば個人プレーの結果にすぎない。フィジカルの強い対戦相手ではまずもって通用しない。
残念だが北川は代表レベルに達していない
相手がパスに対して労を惜しまず遮断してくるのなら、ワントップに当てる作戦もあった。ところが日本のワントップ(CF)として先発した北川が起点として機能しない。筆者は北川が代表に選ばれ、大迫の控えで試合に出る理由がわからない。北川の技術、闘争心はまだまだ低レベル。もっと練習してほしい。
CFの大迫に次ぐ二番手は武藤だが、彼の欠陥については前回の拙Blogで詳論したので繰り返さない。森保ジャパンのワントップは人材難だ。
森保ジャパンの最弱点はGK
森保ジャパンにおいて、結果に現れないが最も心配なウイークポイントはGK。正GKは権田らしいが、とにかく判断力が悪い。フィジカル、キャッチング、高さ、反応のレベルはJリーグの並みクラス。対戦相手ベトナムのGK、ダン・バン・ラムに比べて権田の技術、フィジカルが数段落ちることはだれの目から見ても明らかだった。日本代表のGKこそ筆者が最も心配しているポジションだ。
森保ジャパンの弱点整理
ここまでの5試合で露呈した森保ジャパンの弱点は以下のとおり。親善試合ではわからなかったが、公式戦だとはっきりする。
- ワントップ=人材難
- 二列目=攻撃の創造性の欠如、連携、有機性、構築力がなく個人プレーばかり
- GK=フィジカル、判断力が低い。人材難で、もっとも心配なポジション
- 代表監督=力量不足(情報力、指導力、サッカー観、采配の未熟さ、戦術の柔軟性の欠如…)
このアジェンダは不毛。アジアのサッカーはいま、急速に発展しつつある。視点を広げてアジアのサッカーを地域別にみると以下のとおりとなろう。
- 急速に台頭する東南アジア、
- 資金力豊富な中国、
- 独特の「サッカー王国」を築く湾岸、中東諸国、
- フィジカル面で欧州に引けを劣らないイラン及びオーストラリア、
- 潜在能力の高い中央アジア、
- 飛躍が期待される西アジア(インド、パキスタン、ネパール、ブータン…)
- そして②の中国を含めた、日本、韓国、北朝鮮、台湾で構成される東アジア
そのなかにあって、イラン、日本、韓国、オーストラリア、サウジアラビアが強豪国だった。ところが、本大会においては唯一、イランだけが抜群の強さをみせているものの、日本、韓国、オーストラリアが停滞している。日本に惜敗したサウジアラビアは、あまり変化がない。
一方、前出の全地域が急速に力をつけてきたから、強豪国といわれた5カ国との差が一気に縮まった。一般論として、世界のスポーツのレベルは年々上がっている。上位が停滞すれば、下位にひっくり返される。2019アジア杯はそのような現実を目の当たりにした感がある。
冒頭のアジェンダに対しては、日本はこれからもアジアで絶対的な強さを誇らなければだめ、という解答しかない。内容的にも結果的にも、他国を圧倒しなければ、世界に追いつけない。日本が停滞すれば、アジアから見くだされ、世界で通用しない代表チームになってしまう。後退はもちろん、停滞すら許されない。日本が森保監督のままガラパゴス化し、停滞すれば、全アジア地域との差が縮まるどころか、逆転されるのは時間の問題となる。
森保が代表監督として的確でない理由
森保が代表監督としてなぜ、適正を欠くのかといえば、彼がJリーグというローカルなクラブチームの監督の経験しかないから。森保が少なくとも他国のナショナルチームを指揮した経験があっての日本代表監督就任ならば、適職の可能性はあった。それすらないのだから、悪いのは森保ではなく、任命者ということになる。
レベルの低い国の代表チームが外国人監督を招聘する理由は、代表監督を専門職とする者がもつ視野の広さ、引き出しの多さを買ってのこと。彼らは世界中を渡り歩き、異なる言語、文化、習慣、宗教等を乗り越えながら、受託した代表チームを指導する経験をもっている。世界のサッカートレンドに敏感な彼らは、契約先固有の国民性・フィジカル・世界観と、世界のサッカートレンドを融合し、代表チームを強化するスキルを持っている。
直近の事例でいえば、世界の有能な代表監督たちは、2018W杯ロシア大会当時の世界のトレンドが堅守速攻であることを認識し、それまでのポゼッションサッカーに見切りをつけていた。日本サッカー界に向けて、2018ロシア大会開催よりもずっと前から「フィジカル重視」の発言を行っていたのは、管見の限りだが、元日本代表監督のオシムだったと記憶する。そしてロシア大会は、オシムの言葉どおりのサッカーが展開された。ことほどさように、サッカー後進国にとって、代表監督を専門職とする者の存在は、世界のサッカー潮流を知るための潜望鏡のようなものなのだ。
準決勝、森保が目指すサッカーを明確に示してほしい
森保日本代表監督が目指し、また、理想とするサッカーはどのようなものなのか。世界と合い渉れると(思い描く)日本代表のサッカースタイルはどのようなものなのか。彼は代表監督として、代表ファンにどのような言葉でそれを発信し、日本代表チームに意識づけし、代表選手のプレーに浸透させているのか。このことを次戦イランとの試合で、明確に示してほしい。それが示せなければ、森保ジャパンに未来なし――と断言できる。
2019年1月23日水曜日
代表史上、最も醜悪な勝利――アジア杯KOステージ、日本、サウジに辛勝
サッカーアジア杯UAE大会、日本―サウジアラビアは日本が1-0で勝利し、ベスト8入りを果たした。ベスト8は日本を含めたアジアの4強(イラン、オーストラリア、韓国)、そして、ベトナム(次戦日本)、開催国UAE、カタール、中国に決まった。
いまの日本代表は弱い
さて、サウジ戦、日本の勝利に喜んでいる人は少ないだろう。むしろ、日本の弱さをはっきりと認識したと思う。日本は予選リーグ3連勝で1位通過、そしてノックアウトステージの初戦、ベスト8を賭けた難敵サウジアラビア戦に勝ったのだから、記録の上では順調なようにみえる。
ほんとうだろうか。筆者は拙Blogにおいて、本大会における日本代表のサッカーに警鐘を鳴らしてきた。ここまでの日本代表のサッカーは危機的状況にあると。そのことをサウジ戦で確信できた。
サウジ戦のスタッツをみれば一目瞭然、ほぼサウジにボールを支配され、日本は攻撃のかたちを一度たりともつくれなかった。日本は自陣のハーフコートに押し込まれ、まるで守備の練習を見ているようだった。
日本が上げた決勝点は、前半20分、コーナーキックから日本のCBのヘッディングによるもの。それ以外、日本はほぼ試合時間のすべてを自陣に立て籠もり、守備に終始した。もちろん、サッカーにおいて、このような試合が発生することは承知している。日本より実力がはるかに上回るブラジル、フランスといった強豪国に対して、弱小国である日本が取らざるを得ない選択として。
日本の相手は難敵とはいえ、FIFAランキングで日本を下回るサウジアラビアである。そればかりではない。筆者が残念に思うのは、日本が虎の子の1点を戦術的に守り切ろうとしたとは思えないことである。日本が先取点を上げなくとも、日本はサウジに終始攻撃されていたであろうことは明白なのである。つまり、日本は成り行きとして押し込まれ、守備しかできなかった。だから、この試合は、日本代表史上、もっとも醜悪な勝利だと筆者は考える。
いまだ調子があがらない攻撃陣
すでに以前の拙Blogに記したとおり、本大会における日本代表の調子は悪い。とりわけ攻撃陣4選手は最悪である。サウジ戦のワントップ武藤は、相手DFとの接触プレーでことごとく手を使ってファウルをとられ、攻撃の芽を摘んでいた。主審イルマトフは手を使った接触プレーのすべてを公平にファウルにとった。だから、日本代表が狙われたわけではない。
2列目の堂安、南野、原口にいたっては、自らがフィニッシュを狙う動きばかりで、彼らが連動して攻撃を仕掛けるようなアクションがみられない。それ以外は守備要員といったありさま。後方及びサイドから、攻撃に転じられるような有効なパス等が彼らに供給されない。攻撃の基点が皆無であり、攻撃を構築するイマジネーションがない。W杯ロシア大会で見せた香川、乾、長友でみせたような創造性がない。
堅守はそれで結構なことだが、堅守から速攻がないから、相手にキープを許してしまう。相手のサウジに決定力がなかったから完封できたものの、このような試合が続くようであれば、チームの成長はない。
「自分たちのサッカーをやるだけ」はどこへいったのか
アジア杯を通じて日本代表はなにを獲得したかったのか。言うまでもなくそれは優勝である。優勝するためには「勝利」が最優先だという理屈は明白である。このような大会では、勝利し続けなければ、若い選手に経験を積ませることもできないし、チームの戦術の幅を広げることもできない。だから勝つための手段を選ぶ。ところが、である、これまで日本代表はなんと言ってきたのか。日本代表選手の主力たちは、W杯を前にして、ことごとく「自分たちのサッカーをする」と言ってきたのではなかったのか。そうすれば勝てるとも…
森保ジャパンは「自分たちのサッカー」のあるべき姿をもっていない。試合の成り行きで選手がやみくもに動きまわり、ここまでのところ、各個のバラバラなアクションの積み上げが結果として成功してきたにすぎない。それが、予選リーグ3連勝、ノックアウトステージ1勝をあげたにすぎない。しかもそれらの勝利は、どれも「幸運」なものばかりである。ツキも実力のうちとは言われるけれど、森保が監督として、日本代表の理想とするサッカーを見せるべく選手を動かさなければ、また、選手が必死で戦い抜かなければ、勝利の女神は日本チームから去ってゆく。
いまの日本代表の実力はアジアで6番手
本大会のここまでの試合を見た筆者の印象からすると、現時点の日本代表の力は、韓国→イラン→オーストラリア→サウジアラビア→UAE→ウズベキスタン、に次ぐ程度だと思われる。もしかすると、中国より弱いかもしれない。日本はサウジアラビア、ウズベキスタンに勝ったけれど、内容では劣っている。
森保ジャパンがこの先、ホームの親善試合で勝ち続けたとしても、W杯2020カタール大会予選では苦戦するし、アジア予選が突破できたとしても、カタールW杯でベスト16入りするのは難しかろう。結論は今回も同じ、狭隘なナショナリズムに拘って日本人(森保)監督に固執することはまちがっている。
いまの日本代表は弱い
さて、サウジ戦、日本の勝利に喜んでいる人は少ないだろう。むしろ、日本の弱さをはっきりと認識したと思う。日本は予選リーグ3連勝で1位通過、そしてノックアウトステージの初戦、ベスト8を賭けた難敵サウジアラビア戦に勝ったのだから、記録の上では順調なようにみえる。
ほんとうだろうか。筆者は拙Blogにおいて、本大会における日本代表のサッカーに警鐘を鳴らしてきた。ここまでの日本代表のサッカーは危機的状況にあると。そのことをサウジ戦で確信できた。
サウジ戦のスタッツをみれば一目瞭然、ほぼサウジにボールを支配され、日本は攻撃のかたちを一度たりともつくれなかった。日本は自陣のハーフコートに押し込まれ、まるで守備の練習を見ているようだった。
日本が上げた決勝点は、前半20分、コーナーキックから日本のCBのヘッディングによるもの。それ以外、日本はほぼ試合時間のすべてを自陣に立て籠もり、守備に終始した。もちろん、サッカーにおいて、このような試合が発生することは承知している。日本より実力がはるかに上回るブラジル、フランスといった強豪国に対して、弱小国である日本が取らざるを得ない選択として。
日本の相手は難敵とはいえ、FIFAランキングで日本を下回るサウジアラビアである。そればかりではない。筆者が残念に思うのは、日本が虎の子の1点を戦術的に守り切ろうとしたとは思えないことである。日本が先取点を上げなくとも、日本はサウジに終始攻撃されていたであろうことは明白なのである。つまり、日本は成り行きとして押し込まれ、守備しかできなかった。だから、この試合は、日本代表史上、もっとも醜悪な勝利だと筆者は考える。
いまだ調子があがらない攻撃陣
すでに以前の拙Blogに記したとおり、本大会における日本代表の調子は悪い。とりわけ攻撃陣4選手は最悪である。サウジ戦のワントップ武藤は、相手DFとの接触プレーでことごとく手を使ってファウルをとられ、攻撃の芽を摘んでいた。主審イルマトフは手を使った接触プレーのすべてを公平にファウルにとった。だから、日本代表が狙われたわけではない。
2列目の堂安、南野、原口にいたっては、自らがフィニッシュを狙う動きばかりで、彼らが連動して攻撃を仕掛けるようなアクションがみられない。それ以外は守備要員といったありさま。後方及びサイドから、攻撃に転じられるような有効なパス等が彼らに供給されない。攻撃の基点が皆無であり、攻撃を構築するイマジネーションがない。W杯ロシア大会で見せた香川、乾、長友でみせたような創造性がない。
堅守はそれで結構なことだが、堅守から速攻がないから、相手にキープを許してしまう。相手のサウジに決定力がなかったから完封できたものの、このような試合が続くようであれば、チームの成長はない。
「自分たちのサッカーをやるだけ」はどこへいったのか
アジア杯を通じて日本代表はなにを獲得したかったのか。言うまでもなくそれは優勝である。優勝するためには「勝利」が最優先だという理屈は明白である。このような大会では、勝利し続けなければ、若い選手に経験を積ませることもできないし、チームの戦術の幅を広げることもできない。だから勝つための手段を選ぶ。ところが、である、これまで日本代表はなんと言ってきたのか。日本代表選手の主力たちは、W杯を前にして、ことごとく「自分たちのサッカーをする」と言ってきたのではなかったのか。そうすれば勝てるとも…
森保ジャパンは「自分たちのサッカー」のあるべき姿をもっていない。試合の成り行きで選手がやみくもに動きまわり、ここまでのところ、各個のバラバラなアクションの積み上げが結果として成功してきたにすぎない。それが、予選リーグ3連勝、ノックアウトステージ1勝をあげたにすぎない。しかもそれらの勝利は、どれも「幸運」なものばかりである。ツキも実力のうちとは言われるけれど、森保が監督として、日本代表の理想とするサッカーを見せるべく選手を動かさなければ、また、選手が必死で戦い抜かなければ、勝利の女神は日本チームから去ってゆく。
いまの日本代表の実力はアジアで6番手
本大会のここまでの試合を見た筆者の印象からすると、現時点の日本代表の力は、韓国→イラン→オーストラリア→サウジアラビア→UAE→ウズベキスタン、に次ぐ程度だと思われる。もしかすると、中国より弱いかもしれない。日本はサウジアラビア、ウズベキスタンに勝ったけれど、内容では劣っている。
森保ジャパンがこの先、ホームの親善試合で勝ち続けたとしても、W杯2020カタール大会予選では苦戦するし、アジア予選が突破できたとしても、カタールW杯でベスト16入りするのは難しかろう。結論は今回も同じ、狭隘なナショナリズムに拘って日本人(森保)監督に固執することはまちがっている。
2019年1月19日土曜日
George生誕祭
根津のBar Hidamariのオーナー、Georgeさんの生誕祭とやらでお店を訪れたものの超満席で入れず。
サービス精神旺盛なGeorgeさん、わざわざお店の外にでてきて、お姿を見せてくれました。ゴージャス!
サービス精神旺盛なGeorgeさん、わざわざお店の外にでてきて、お姿を見せてくれました。ゴージャス!
2019年1月18日金曜日
つくられた横綱(稀勢の里)の悲劇
大相撲の横綱、稀勢の里が引退した。テレビを筆頭としたメディアは、このニュースをトップで伝えた。ニュース番組、情報番組、ワイドショー等ではかなりの時間を「稀勢の里引退」に割いた。筆者は大相撲をスポーツだと思っていないので、メディアの格別の反応に驚いた。それほどのことなのだろうか。厚労省の統計不正、JOC竹田会長の贈賄疑惑、辺野古をめぐる県民投票・・・政権にとって“不都合な真実”の目くらましかと。
大相撲は伝統芸能、スポーツではない
大相撲がスポーツでないことについては拙Blogで何度も書いた。繰り返せば、大相撲とは、伝統芸能の興行なのだ。だからといって、力士が弱いわけではない。プロレスラーが常人に比して著しく強いのと同様、力士も強い。彼らは稽古に励み、肉体を極限まで強化する。
その実力は稽古場で計られ、各力士のおおよそのレベルが非公式に査定される。角界と呼ばれる大相撲業界の内側で各力士の実力のほどが認識される。本場所、真剣勝負で戦った結果が公式記録だ。白星、黒星。その結果、トップに上り詰めた者が横綱の地位を得る。
この過程はスポーツだが、本場所の公式記録が必ずしも真剣勝負の結果を反映していない、というのが筆者の推測だ。人気が出そうな力士を番付上位にあげる力学が働いているのではないかと。
スター性のある力士が幕内にいなければ、興行としてマイナスだ。近年、ハワイ、モンゴル出身の力士が横綱の地位を占めた結果、興行に悪い影響が出た。そこで、日本人横綱を、と稀勢の里は横綱になった。角界幹部及び全力士が、“稀勢の里は横綱”で合意した。
「奇跡の逆転優勝」を信じるか信じないか
稀勢の里のピークは、横綱としての初の場所となった2017年3月(春)場所。そのときの状況を、Wikipediaで参照してみる。
(横綱・稀勢の里は)初日から12連勝と好調であったが、13日目に日馬富士に寄り倒された際に左肩を負傷。14日目の鶴竜戦は一方的に寄り切られ、この時点1敗で並んでいた照ノ富士に逆転優勝を許してしまう可能性が高まった。照ノ富士との勝負はいまでも語り草になっていて、奇跡の逆転優勝として相撲ファンの記憶に残っている。稀勢の里の代名詞でもある。
千秋楽、稀勢の里は、その左の二の腕が内出血で大きく黒ずむほどけがが悪化している中で、優勝争い単独トップの照ノ富士との直接対決を迎える。優勝決定戦と合わせて2連勝することが必要な稀勢の里の優勝はほぼ無いと思われたが、本割で左への変化から最後は突き落としで勝利、引き続いての優勝決定戦では、もろ差しを許して土俵際まで押されたが、体を入れ替えての一発逆転の小手投げが決まって勝利し、奇跡的な逆転優勝を決めた。
しかし、筆者は“奇跡の逆転優勝”に疑念を抱いている。稀勢の里のケガは尋常ではなかった。大胸筋の筋断裂という、大ケガだった。大胸筋を痛めれば、まず、腕が上がらなくなる。痛みをこらえて無理にあげたとしても、力が出ない。筋断裂ならば余計だ。それでも稀勢の里は勝った。
この取組は八百長として仕組まれたものではない。おそらく、対戦相手が忖度したのだと思う。相撲界繁栄のため、「優勝」を稀勢の里に譲った、と筆者は考えている。
「奇跡」後に厳しい現実がやってくる
奇跡は、稀勢の里に2度は訪れなかった。周囲の忖度もここまでだった。彼は後遺症に悩まされ、以降、休場が続いた。横綱昇進後の稀勢の里の成績は36勝36敗97休、2017年5月の夏場所から8場所連続で休場。年6場所制となった1983年以降のワースト記録。さらに昨年11月の九州場所で初日から4連敗、今年の初場所で初日から3連敗を喫して、昨年9月の秋場所千秋楽からは8連敗となった。1場所15日制が定着した1949年夏場所以降のワースト記録を更新した。
それでも、2018年秋場所は、10勝5敗で15日間務めあげた場所もあった。だが、筆者はこの場所の成績が怪しいと思っている。このことは後述する。
稀勢の里は「史上最弱」横綱
公式記録が物語るように、稀勢の里は、「史上最弱横綱」と呼ばれて不思議ではない。以下、稀勢の里の横綱昇進後の場所ごとの成績をみておこう。
・2017
春場所=13勝2敗(優勝)、夏場所=6勝5敗4休、名古屋場所=2勝4敗9休、秋場所=全休、九州場所=4勝6敗5休
・2018
初場所=1勝5敗9休、春場所=全休、夏場所=全休、名古屋場所=全休、秋場所=10勝5敗、九州場所0勝5敗10休
・2019
初場所=0勝4敗-引退
なんとも無残な成績だ。ところで、不自然なのが2018年秋場所の10勝5敗ではなかろうか。推測だが、周囲の引退勧告を鎮めるため、角界が時間稼ぎをしたのではないか。勝敗は他の力士の忖度の結果だろう。稀勢の里の復調を待ったのではないか。
「奇跡」は2001年にも起こっている(貴乃花の逆転優勝)
本割で負傷して、決定戦で逆転優勝するという「奇跡の優勝」のパターンは、稀勢の里の場合だけではない。なんと、あの貴乃花も同じような「奇跡の優勝」をはたしていた。そして、その後、低迷して引退するという稀勢の里と似たような進路を辿った。そのときの貴乃花の状況をWikipediaで再現してみよう。
(横綱・貴乃花は2001年)、5月(夏)場所初日から13連勝して完全無敵の強さだった。しかし14日目の武双山戦で土俵際での巻き落としを喰らって、右膝半月板を損傷する大けがを負った。もはや立つことも困難なほどの重傷であり、本来休場するべきところであった。二子山親方ら関係者も休場するよう貴乃花に勧めたが、幕内優勝が掛かっていたため、周囲の休場勧告を振り切り、翌日の千秋楽は無理矢理強行出場した。千秋楽はテーピングをせずに、横綱土俵入りを披露した。しかし本割りの仕切り最中にすら右膝を引き摺るような仕草があり、勝負にならないことは明らかであった。その悲惨な状況に審判部として土俵下に座る九重は仕切りの最中にも「貴乃花、痛かったらやめろ!」と忠告したほどである。予想通り千秋楽結びの一番の武蔵丸戦では、武蔵丸の立合いの変化に全くついて行けず一瞬で勝負がつく様な敗退で武蔵丸と相星となった。この「奇跡の逆転優勝」を境に貴乃花はケガや体調不良に悩まされるようになる。そして、2001年7月(名古屋)場所から2002年7月(名古屋)場所まで休場。次の9月(秋)場所に12勝3敗の成績を残すも、2002年11月(九州)場所を休場、そして2003年の1月(初)場所、4勝3敗1休の成績をもって引退している。
続く優勝決定戦は誰もが武蔵丸の勝利を確信せざるを得なかったが、大方の予想を覆し、武蔵丸を豪快な上手投げで破った。勝利を決めた直後の鬼の形相と奇跡的な優勝に小泉純一郎は表彰式で「痛みに耐えてよく頑張った!感動した!!おめでとう!!!」と貴乃花を賞賛した。後世相撲史に語り継がれる大一番となった。貴乃花が怪我を押して出場した背景には「休場すれば本割、優勝決定戦と不戦勝で武蔵丸が優勝をさらう史上初の事態になった」という状況があり、この優勝の際のスポーツ新聞の記事で貴乃花は「横綱としてというより、1人の力士としてやろうと思った。ひざがダメになったらという不安?そうなったらそうなったときですから」と言っていた。
貴乃花と稀勢の里の引退パターンはウリフタツ
貴乃花、稀勢の里、両者の共通点は、①場所中大ケガを追いながら、優勝争いをしていた力士に「奇跡的に勝利」し優勝する、②奇跡の優勝後、休場を続ける、③休場明けの場所でそれなりの成績を残す、④それなりの成績を残したその次の場所から再び休場を繰り返す、⑤休場明けに再度登場した場所で負け続け、引退に至る――という、①~⑤のプロセスが寸分たがわず同一だということだ。場所中のケガ→強行出場→相手の忖度→奇跡の優勝→故障休場→復活→故障休場→再々登場→大負け・引退というパターンだ。
大相撲は興行である
冒頭に筆者の大相撲に係る見解を開陳したとおり、「奇跡の逆転優勝」も角界の管理者、演技者が共同で仕込んだ物語にすぎない。対戦相手同士が阿吽の呼吸で感じ合い、勝負を演じた結果だろう。だからこれを八百長とは呼ばない。
それを「名勝負」として受け止めるナイーブ(うぶ)なファンや愛好家がいる限り、大相撲の「名場面」がこの先、再現され続けられるだろう。そのことは悪いことではない。江戸時代に確立された歌舞伎が今日まで愛され続けられているように、大相撲もこの先、いつまでも愛され続けられることだろう。
2019年1月16日水曜日
森保ジャパンは危険水域に
サッカーW杯ロシア大会(2018)終了後に発足した日本代表(森保ジャパン)が、アジア杯(UAE大会)で苦戦している。予選2試合で勝点6をあげ、早々と決勝トーナメント進出を決めたが、内容が悪すぎる。格下相手の予選リーグ、初戦のトルクメニスタン戦3-2、第2試合オマーン戦1-0と、いずれも辛勝。
とりわけオマーン戦では、主審の誤審でPKを得た1得点のみ。そのうえ、ペナルティーエリア内の長友のハンドをこれまた主審が見逃すという2度の幸運に恵まれ、なんとか勝ちを拾った。ビデオ判定があったら、日本が0-1で負けていた可能性も高かった。
選手は調整不足、監督は力不足、闘争心はゼロ
主審の判定に泣かされることもあるし、その反対もあるから、オマーン戦の結果はいい。それよりもなによりも、アジア杯における日本代表チームの状態が悪すぎる。第一に選手のコンディションの悪さ、第二に闘争心が感じられないこと、第三が指揮官の資質、能力不足の露呈――と、内容は極めて深刻。森保には選手を統率する力がない。モチベーターの役割すら果たしていないようにみえる。試合中の指示が不明確なのがうかがえるし、試合前の戦術の徹底がなされておらず、相手に自軍がなにを武器に、いかに戦うか――が理解されていないまま、選手が試合に入っている感が否めない。
日本国内における親善試合でいい結果を出したものだから、日本のメディアが絶賛した森保ジャパンだが、公式戦では相手が思うようにやらせてくれない。その分、内容の乏しい試合を続けている。具体的には、攻撃面では、選手が個人プレーに走りすぎ、コンビネーションが絶無。2列目の堂安、南野、原口が「個」について誤解している感があり、仲間と確実に得点につながるような有機的アクションの構築が目指されていない。
ロシア大会代表を凌ぐ人材ゼロ
それだけではない。中島が欠場した今大会、魅力的なニュースターも現れていない。まず2018年ロシア大会で活躍した大迫を押しのけるようなCFが出ていない。大迫が欠場したオマーン戦でそのことが証明された。
サイドバック(SB)も低調。右SBの酒井もキレがなく、右サイドからの攻撃の形ができていない。酒井に代わる人材もいない。左SBのベテラン長友が相変わらず豊富な運動量を見せつけているが、彼を追い越す人材が不在なことの逆証明。森保ジャパンにおいて、両SBの人材不足は明らか。SBに関しては、お先真っ暗闇である。中盤の柴崎もプレーメークができていない。スペインリーグで試合には出ていないのだから、彼のポジションを奪う人材が出てこなければいけない。
守備陣では、吉田とコンビを組むCBの人材が発掘できていないまま、大会に来てしまった感がある。さらに深刻なのがGK。権田が連続出場したが、高さ、判断力、キャッチがおぼつかない。トルクメニスタン戦で相手の先制ゴールとなったミドルシュートにほぼ無反応というのはさびしい限り。
このままなら、日本代表のガラパゴス化が進むばかり
森保が決勝トーナメントでこのチーム状態を建て直せなければ、協会は監督更迭のプログラムに着手しなければなるまい。代表監督とは、協会が「育てる」ような職務ではない。日本人だから日本代表監督という論法の誤りは、引退した日本人横綱・稀勢の里の事例が示すとおり。このままなら、日本代表のガラパゴス化がますます進行する。
とりわけオマーン戦では、主審の誤審でPKを得た1得点のみ。そのうえ、ペナルティーエリア内の長友のハンドをこれまた主審が見逃すという2度の幸運に恵まれ、なんとか勝ちを拾った。ビデオ判定があったら、日本が0-1で負けていた可能性も高かった。
選手は調整不足、監督は力不足、闘争心はゼロ
主審の判定に泣かされることもあるし、その反対もあるから、オマーン戦の結果はいい。それよりもなによりも、アジア杯における日本代表チームの状態が悪すぎる。第一に選手のコンディションの悪さ、第二に闘争心が感じられないこと、第三が指揮官の資質、能力不足の露呈――と、内容は極めて深刻。森保には選手を統率する力がない。モチベーターの役割すら果たしていないようにみえる。試合中の指示が不明確なのがうかがえるし、試合前の戦術の徹底がなされておらず、相手に自軍がなにを武器に、いかに戦うか――が理解されていないまま、選手が試合に入っている感が否めない。
日本国内における親善試合でいい結果を出したものだから、日本のメディアが絶賛した森保ジャパンだが、公式戦では相手が思うようにやらせてくれない。その分、内容の乏しい試合を続けている。具体的には、攻撃面では、選手が個人プレーに走りすぎ、コンビネーションが絶無。2列目の堂安、南野、原口が「個」について誤解している感があり、仲間と確実に得点につながるような有機的アクションの構築が目指されていない。
ロシア大会代表を凌ぐ人材ゼロ
それだけではない。中島が欠場した今大会、魅力的なニュースターも現れていない。まず2018年ロシア大会で活躍した大迫を押しのけるようなCFが出ていない。大迫が欠場したオマーン戦でそのことが証明された。
サイドバック(SB)も低調。右SBの酒井もキレがなく、右サイドからの攻撃の形ができていない。酒井に代わる人材もいない。左SBのベテラン長友が相変わらず豊富な運動量を見せつけているが、彼を追い越す人材が不在なことの逆証明。森保ジャパンにおいて、両SBの人材不足は明らか。SBに関しては、お先真っ暗闇である。中盤の柴崎もプレーメークができていない。スペインリーグで試合には出ていないのだから、彼のポジションを奪う人材が出てこなければいけない。
守備陣では、吉田とコンビを組むCBの人材が発掘できていないまま、大会に来てしまった感がある。さらに深刻なのがGK。権田が連続出場したが、高さ、判断力、キャッチがおぼつかない。トルクメニスタン戦で相手の先制ゴールとなったミドルシュートにほぼ無反応というのはさびしい限り。
このままなら、日本代表のガラパゴス化が進むばかり
森保が決勝トーナメントでこのチーム状態を建て直せなければ、協会は監督更迭のプログラムに着手しなければなるまい。代表監督とは、協会が「育てる」ような職務ではない。日本人だから日本代表監督という論法の誤りは、引退した日本人横綱・稀勢の里の事例が示すとおり。このままなら、日本代表のガラパゴス化がますます進行する。
2019年1月9日水曜日
お次は長野か!読売の不可解プロテクト外し
FAで広島から読売に移籍した丸佳浩外野手の人的補償が長野久義外野手(34)と決まった。先の内海哲也投手(36)に次ぐ連続の驚きだ。まさかまさかである。筆者の予想は左のワンポイント戸根千明投手(26)だったから、これまた大外れ。
相次いだ「ドラフト破り」選手のプロテクト外し
このたびの内海、長野の人的補償による放出には共通点がある。内海は2002年ドラフトでオリックスの指名を受けたが拒否、東京ガスに入社して一浪の末、翌年の自由枠にて読売に入団した。長野は2006年ドラフト(日本ハムからの指名)、2007年ドラフト(千葉ロッテからの指名)を拒否して二浪、2008年ドラフトで読売(の単独指名により)に入団した。つまり、内海、長野の共通点は、2人とも「ドラフト破り」の過去を持っているということだ。このことは、「巨人入り」を熱望して浪人までした選手をあっさりと、プロテクトから外したことを意味する。
読売の「ドラフト破り」は江川卓を初代にして、球界に黒歴史を刻んできた。その江川にはコーチ・監督の声がかからず、内海、長野がFAの人的補償で放出されたとなれば、読売が「ドラフト破り」の黒歴史の清算を図っているとも考えられる。大新聞社を親会社とするプロ野球球団がルール破りの歴史をもつということは、よろしくない。もし読売が過去の清算に乗り出したとするならば、「ドラフト破り」で読売に入団した現「エース」、菅野智之投手もいずれは放出されることになるのだろうか――
もちろん、筆者のこの「推論」は皮肉でありジョーク。読売グループに良心はない。「読売巨人軍」は、常勝軍団、球界の盟主、紳士たれ・・・らしいが、読売新聞の拡販を使命とした、時代遅れのスポーツ媒体にすぎない。
原辰徳(出戻り)監督の決定事項
内海、長野のプロテクト外しの意図はなにか――複数のスポーツコメンテーターがこのテーマに取組んでいて、色々な見解を発表しているが、管見の限り、しっくりしない。いうまでもなく、当事者である読売球団がプロテクトを外した選手名を公表するわけがない。だから真相はわからない。
ただいえるのは、監督に復帰した原辰徳の決定によるということだけだ。原が監督に復帰したと同時に、球団GMを兼ねることが報道されており、そのとおり、前GMの鹿取義隆が読売を去っている。つまり、内海、長野のプロテクト外しを決めたのは原辰徳だということ。
若手投手放出は読売のトラウマ、
読売は近年、FAによる人的補償のみならず、トレード等による若手投手放出でミスを重ねている。その代表例が一岡竜司投手(2013年)のプロテクト外しだ。この件は先の拙blogでも書いたし、多くの報道があるので繰り返さない。
一岡に次いでFAの人的補償で他球団に移籍した結果活躍したのが、2017年、山口俊投手(31)の人的補償でDeNAに移籍した平良拳太郎投手(23)だ。平良は読売に在籍した2014~2016年、一軍登板1試合で1敗の成績だったが、DeNA移籍2年目、先発13試合で5勝3敗の実績を残し、2018年にはローテーション入りが確実視されている。
そればかりではない。2016年にトレードで日本ハムに移籍した公文克彦投手(26)も移籍先で活躍している。公文の読売在籍中(2013~2016)の一軍成績は14年に3試合登板、3イニング、16年に12試合登板で、3年間通算、勝利、ホールド等0だったのだが、日本ハムに移籍した途端、2017年には41試合登板、3ホールド、18年には57試合登板、11ホールドの実績を残している。
読売は同球団で実績の上がらなかった若手3投手(一岡、平良、公文)を放出したが、3投手とも移籍先で頭角を現したという次第。これら3事例から、読売には、若手投手の素質を見抜く力がなく、育成もできなかったことがわかる。読売の指導者(とりわけ投手コーチ)の無能ぶりを如実に示している。
原辰徳の編成能力に疑問
読売が内海、長野のベテランをプロテクトから外した一方で、中島宏之野手(36)及び岩隈久志投手(37)を獲得したことが話題になっている。中島は米国球団経験者だが、MLBに昇格していない。岩隈はMLBで実績を残したが、故障でほぼ2シーズン登板していない。つまり、内海、長野の放出が即ち若返りには通じていない。さらに不可解なのが、中井大介内野手(29)、廖任磊投手(25)を自由契約に、橋本到外野手(28)を金銭で楽天にトレードしたこと。中井はDeNA、廖は西武が獲得した。
(※なお、辻東倫内野手(24)が引退しているが、その理由は不明。致命的な故障があったのかもしれないので例外とする。)
2019シーズン、中井、廖、橋本が活躍し、中島、岩隈がダメだったら、原辰徳の編成能力が疑われて当然だろう。
優勝すれば、すべて忘れ去られる
丸、炭谷、中島、岩隈が仮に2019シーズン、鳴かず飛ばずであったとしても、他の選手の活躍で読売が優勝すれば、“原辰徳の編成能力がどうの、育成方法がどうの・・・”という批判は忘れ去られる。他球団に移籍した内海、長野、中井、廖がそれなりに活躍しようが、大した話題にはなるまい。それが「巨人」中心でまわり続ける、日本のプロ野球界の実態であり、スポーツメディアのスタンスなのだ。
相次いだ「ドラフト破り」選手のプロテクト外し
このたびの内海、長野の人的補償による放出には共通点がある。内海は2002年ドラフトでオリックスの指名を受けたが拒否、東京ガスに入社して一浪の末、翌年の自由枠にて読売に入団した。長野は2006年ドラフト(日本ハムからの指名)、2007年ドラフト(千葉ロッテからの指名)を拒否して二浪、2008年ドラフトで読売(の単独指名により)に入団した。つまり、内海、長野の共通点は、2人とも「ドラフト破り」の過去を持っているということだ。このことは、「巨人入り」を熱望して浪人までした選手をあっさりと、プロテクトから外したことを意味する。
読売の「ドラフト破り」は江川卓を初代にして、球界に黒歴史を刻んできた。その江川にはコーチ・監督の声がかからず、内海、長野がFAの人的補償で放出されたとなれば、読売が「ドラフト破り」の黒歴史の清算を図っているとも考えられる。大新聞社を親会社とするプロ野球球団がルール破りの歴史をもつということは、よろしくない。もし読売が過去の清算に乗り出したとするならば、「ドラフト破り」で読売に入団した現「エース」、菅野智之投手もいずれは放出されることになるのだろうか――
もちろん、筆者のこの「推論」は皮肉でありジョーク。読売グループに良心はない。「読売巨人軍」は、常勝軍団、球界の盟主、紳士たれ・・・らしいが、読売新聞の拡販を使命とした、時代遅れのスポーツ媒体にすぎない。
原辰徳(出戻り)監督の決定事項
内海、長野のプロテクト外しの意図はなにか――複数のスポーツコメンテーターがこのテーマに取組んでいて、色々な見解を発表しているが、管見の限り、しっくりしない。いうまでもなく、当事者である読売球団がプロテクトを外した選手名を公表するわけがない。だから真相はわからない。
ただいえるのは、監督に復帰した原辰徳の決定によるということだけだ。原が監督に復帰したと同時に、球団GMを兼ねることが報道されており、そのとおり、前GMの鹿取義隆が読売を去っている。つまり、内海、長野のプロテクト外しを決めたのは原辰徳だということ。
若手投手放出は読売のトラウマ、
読売は近年、FAによる人的補償のみならず、トレード等による若手投手放出でミスを重ねている。その代表例が一岡竜司投手(2013年)のプロテクト外しだ。この件は先の拙blogでも書いたし、多くの報道があるので繰り返さない。
一岡に次いでFAの人的補償で他球団に移籍した結果活躍したのが、2017年、山口俊投手(31)の人的補償でDeNAに移籍した平良拳太郎投手(23)だ。平良は読売に在籍した2014~2016年、一軍登板1試合で1敗の成績だったが、DeNA移籍2年目、先発13試合で5勝3敗の実績を残し、2018年にはローテーション入りが確実視されている。
そればかりではない。2016年にトレードで日本ハムに移籍した公文克彦投手(26)も移籍先で活躍している。公文の読売在籍中(2013~2016)の一軍成績は14年に3試合登板、3イニング、16年に12試合登板で、3年間通算、勝利、ホールド等0だったのだが、日本ハムに移籍した途端、2017年には41試合登板、3ホールド、18年には57試合登板、11ホールドの実績を残している。
読売は同球団で実績の上がらなかった若手3投手(一岡、平良、公文)を放出したが、3投手とも移籍先で頭角を現したという次第。これら3事例から、読売には、若手投手の素質を見抜く力がなく、育成もできなかったことがわかる。読売の指導者(とりわけ投手コーチ)の無能ぶりを如実に示している。
原辰徳の編成能力に疑問
読売が内海、長野のベテランをプロテクトから外した一方で、中島宏之野手(36)及び岩隈久志投手(37)を獲得したことが話題になっている。中島は米国球団経験者だが、MLBに昇格していない。岩隈はMLBで実績を残したが、故障でほぼ2シーズン登板していない。つまり、内海、長野の放出が即ち若返りには通じていない。さらに不可解なのが、中井大介内野手(29)、廖任磊投手(25)を自由契約に、橋本到外野手(28)を金銭で楽天にトレードしたこと。中井はDeNA、廖は西武が獲得した。
(※なお、辻東倫内野手(24)が引退しているが、その理由は不明。致命的な故障があったのかもしれないので例外とする。)
2019シーズン、中井、廖、橋本が活躍し、中島、岩隈がダメだったら、原辰徳の編成能力が疑われて当然だろう。
優勝すれば、すべて忘れ去られる
丸、炭谷、中島、岩隈が仮に2019シーズン、鳴かず飛ばずであったとしても、他の選手の活躍で読売が優勝すれば、“原辰徳の編成能力がどうの、育成方法がどうの・・・”という批判は忘れ去られる。他球団に移籍した内海、長野、中井、廖がそれなりに活躍しようが、大した話題にはなるまい。それが「巨人」中心でまわり続ける、日本のプロ野球界の実態であり、スポーツメディアのスタンスなのだ。
2019年1月3日木曜日
2019年1月1日火曜日
Happy New Year 2019
あけましておめでとうございます。
元号の平成が終わる年。
次の年号はわからないが、筆者は昭和、平成、そして✖✖と、天皇三代の時代を生きる気配が濃厚だ。
今年の見通しは暗いものばかり。その元凶は現政権にある。
打倒「安倍内閣」が実現してほしい。
元号の平成が終わる年。
次の年号はわからないが、筆者は昭和、平成、そして✖✖と、天皇三代の時代を生きる気配が濃厚だ。
今年の見通しは暗いものばかり。その元凶は現政権にある。
打倒「安倍内閣」が実現してほしい。
2018年12月31日月曜日
2018年12月30日日曜日
2018年12月26日水曜日
『国体論―菊と星条旗』
●白井聡〔著〕 ●集英社新書 ●940円+税
本書は、国体という概念を媒介に日本の近現代史を読み直しつつ、現在の安倍政権を痛烈に批判するという建付けである。著者の白井聡は戦後日本の諸状況について、「永続敗戦」という著者自身になる造語概念を使って規定する政治学者。本書はその論の発展的展開として位置づけられる。それゆえ、まずもって「永続敗戦」の原理をおさえておく。
(一)北一輝の『国体論及び純正社会主義』
日本の近現代史において、筆者の記憶に残る国体に係る事案は3つある。最初のそれは1906年(明治39年)、北一輝の処女作『国体論及び純正社会主義』の発刊である。北一輝は後の2.26事件(1935/昭和10年2月26日)を起こした青年将校に強い影響を及ぼした思想家。北一輝の思想は本書で詳細に取り上げらえているので説明を省くが、大雑把にその肝を示せば、天皇は国民のためにあるという、「天皇機関説」の範疇にある。北一輝が2.26事件の思想的指導者として死刑に処せられた理由は、北の天皇論に影響された青年将校により国家転覆未遂事件が起きたからにほかならない。
(二)「国体明徴の声明」
第二番目は、2.26事件の直後、同年8月に、ときの政府が発表した「国体明徴の声明」である。この声明は、軍部及び右翼が天皇を統治権行使の機関とみる学説を攻撃し、その主張者美濃部達吉を「学匪」ときめつけたので、天皇機関説事件ともよばれる。「国体明徴の声明」はときの権力者が北の思想と2.26事件を経験し、いま国体は危機にある、という認識から発せられたともいえる。貴族院・衆議院とも国体明徴を決議し、美濃部は貴族議員を辞め、その著書『憲法概要』『憲法精義』は発禁となった。これをもって政府は軍部の要求に負けて天皇機関説を排撃し、議会主義を否定し、学問言論思想の自由に強く干渉するようになる。
ときの岡田啓介内閣が発した「国体明徴の声明」は、その後の軍部独裁、アジア・太平洋戦争突入という、日本現代史の転換点を象徴する重大な事件だった。
国体明徴事件が示すとおり、戦前の軍部、右翼によって持ち出された国体とは、著者(白井聡)の表現を借りれば、“万世一系の天皇を頂点に戴いた「君臣相睦み合う家族国家」を理念として全国民に強制する体制(P3)”と定義される。天皇を絶対不可侵・超越的存在の神として崇め、日本国民は臣民として天皇(の命令)に絶対服従しなければならないとする国家原理とも別言できる。なお「明徴」とは、「明らかにする」と同義である。
(三)敗戦直前、戦争終結条件としての国体護持
国体が次に顕在化するのは、日本のアジア・太平洋戦争末期、日本の敗戦が決定的となり、連合軍からポツダム宣言(無条件降伏)の受諾を強いられたときであった。ときの日本帝国の為政者は、戦争終結の条件として国体護持に執着したため、無条件降伏を受け入れなかった。そのため連合軍の本土無差別爆撃(1944/6~1945/8)、沖縄地上戦(1945/3)、広島・長崎原爆投下(1945/8)という、連合軍による、日本の民間人大量殺戮を招き寄せた。
それでも無条件降伏を頑なに拒んだ日本帝国の為政者が、一転してアメリカ軍に降伏したのは、1945年8月9日のソ連軍の日本帝国領内侵攻作戦の開始であった。昭和天皇及びその側近はソ連軍の対日参戦に恐怖し、降伏を決意した。
その政府が起こした戦争の末期、敗戦という国家滅亡の危機にあっては、敵であったアメリカの支配を積極的に受け入れ、天皇(家)を抹殺しかねないソ連軍=「共産主義」から国体を護持することに成功する。戦争当事者である日本帝国の為政者は、ソ連軍=共産主義から国体を守るため、アメリカにひれ伏すという選択を行い、結果、国体は守られた。それが、戦後の象徴天皇制である。
戦後の国体とはなにか
本書における明治維新からアジア太平洋戦争敗戦までの国体論は、橋川文三の未完の著『昭和維新試論』等を下敷きにして、簡潔かつ明確に整理されている。ところが、戦後の国体論は難解である。著者(白井聡)の戦後の国体論は、戦前の国体を体現した天皇の代わりに、アメリカをそっくり代入するという図式に単純化される。その点において筋が悪い。
著者(白井聡)の戦後の国体論の中核にあるのは、アメリカである。本書は、戦後日本の対米従属を国体だと規定するわけだが、その論証は矢部浩二や孫崎亨の戦後日米関係論に依拠していて、それを超えるような情報や見識が見当たらない。強いて新鮮だと思わせる部分を挙げれば、「天皇制民主主義」という言葉の提起だろうか。
アメリカの日本占領政策は古代からのセオリーに倣ったもの
天皇が日本帝国の戦争に関与していることは明らかだった。戦勝国側は、天皇の戦争責任を強く追及するかと思われたが、アメリカは天皇の戦争責任を免責し、新憲法の中で天皇を日本国民の象徴と新たに規定した。
著者(白井聡)は、アメリカの天皇免責について、アメリカの日本研究の結果だと大げさに指摘しているがそうでもない。たとえば、新約聖書の舞台となった現在のイスラエル・パレスチナの地は、いまから2000年余り前、ローマ帝国の属州だった。この地の支配者は、ローマ帝国第5代ユダヤ属州総督ポンテオ・ピラトだった。ピラトはイエスを磔刑に処した人物として新約に記されている。
そのピラトだが、彼はイエスを処刑することに最後まで消極的だった。というのも、ローマが属州を支配する構図は、総督自らが強権を振るうことではなく、ユダヤ教の神官に属州の統治を委任するものだったからである。武力を背景にして占領者が前面に出る直接的支配は、被占領地の人民の抵抗を受けやすい。ローマ兵に犠牲者が出る確率が高い。侵略者、占領者が当該地を安定的に統治する方法は、土着の支配者を配下にして間接的に支配するのがセオリーである。
2000年前に遡らなくとも、日本帝国が中国東北部に侵略して「建国」した満州国においても、日本帝国はローマ帝国と同様の統治方法を採用した。1931(昭和6)年9月、柳条湖事件に端を発して満州事変が勃発、関東軍により満州全土が占領され、関東軍主導の下に同地域は中華民国からの独立を宣言し、1932年(昭和7年)3月、満州国が「建国」された。元首(満州国執政、後に満州国皇帝)には清朝最後の皇帝・愛新覚羅溥儀が就いた。中華民国によって滅亡した清朝は満州人が漢族を破って建国した王朝だったから、日本帝国が「建国」した満州国に清王朝の末裔を元首に置いたのは、戦勝国アメリカが日本を占領したとき、その国(日本)の天皇を元首(象徴)として残した事例と似通っている。
アメリカの日本占領政策の第一は、日本帝国の武装解除及び占領軍人の安全確保だった。アメリカが警戒したのは、戦争終結後にあっても旧日本軍の残党が日本各所でゲリラ戦を展開することだった。それを防ぐ切札的存在が天皇だった。日本の敗戦直後(1945年)の動きを追ってみよう。
戦後の国体の形成というよりも維持は、戦争末期、日本帝国の為政者がソ連=共産主義の日本侵略を阻止するためにアメリカと手を組み、アメリカ主導の占領政策を受け入れたことから始まったのである。戦勝国(アメリカ)にとっても占領政策の柱に天皇を据えることに異議はなかった。
その後、日本は民主国家として再生し、かつての国体とは絶縁したと思われている。明治欽定憲法は撤廃され、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、象徴天皇制などを規定した日本国憲法が施行された。そこで国体は死語と化し、あえて戦後の国体とはなにかと問われれば、日本国憲法こそが戦後のそれというのが、一般的認識として定着した。そればかりか、今日、わが国の状況において、国体をテーマとした議論、論考、研究等としては、鈴木邦男著の『天皇陛下の味方です: 国体としての天皇リベラリズム』くらいしか、見当たらない。
アメリカへの隷属が新たな国体か
敗戦後から今日までの日本の歩みは、著者(白井聡)が指摘するとおり、アメリカに隷属している。とりわけ、現在の安倍首相は、アメリカのトランプ大統領の忠臣といったありさまで、アメリカ・メディアからも嘲笑を受けるありさまである。日本政府は、日米同盟は不変、普遍と認識している、と事ある後に国民に説明する。その結果、日米地位協定が代表するとおり、日本はアメリカの属国以下である。著者(白井聡)は、戦後の日本の為政者が頑ななアメリカ信仰を保持・盲従する心的構造を、アメリカをご本尊とする戦後国体思想だと結論づける。さて、そこが本書を支持するか否かの境目だろう。筆者は著者(白井聡)の論に納得していない。
天皇制の危機的局面に現れる国体擁護の動き
国体がわが国の現代史に現れた局面は、前出のとおり、天皇制が危機的状況に陥った時である。そしてもちろん、国体の護持を国民に呼びかけるのは、革新の側ではなく、絶対的、超越的存在としての天皇を擁護したい勢力からであった。戦前の場合は、議会制民主主義や社会主義の台頭を恐れた軍部及び右翼であり、アジア・太平洋戦争末期の場合は、ソ連(共産主義)の侵攻により、日本の天皇(家)がロシア皇帝(一族)のごとく処刑されることを恐れた日本の為政者からであった。
戦後の反米運動
戦後の日米関係に対する異議申し立ては、本書にあるように、60年安保闘争、68年前後の新左翼・全共闘運動、三島由紀夫の自害、反日爆弾闘争といった、戦後民主主義を相対化する思想に基づく政治運動によった。しかし連合赤軍事件、内ゲバ事件等に代表されるそれら運動組織の自滅行動を契機として、体制側の弾圧及びマスメディアによるネガティブキャンペーンが功を奏し、それら運動組織は「過激派」という蔑称で市民権を失ってしまった。このときに現れた革命運動は左翼にとっては共産主義革命(世界革命)を目指すものであり、唯一、三島由紀夫のそれだけが、アメリカに隷属する天皇、ときの政権及び自衛隊を批判するものであった。戦後体制の暴力的打倒を目指しながら、左派と三島は同床異夢の関係にあった。
日本はアングロサクソンとうまくやれば・・・
日本国民のなかに著者(白井聡)がいう戦後の国体(アメリカ信仰)がどれほど浸透しているのか。浸透というよりも、無意識化されているのか。筆者の直観では、アメリカは日本(人)にとってもっとも親和的な外国であるが、無謬的存在にまでは至っていないと思う。ただ気になるのは、「日本はアングロサクソンとうまくやれば、うまくいく」という俗論である。この言説を耳にしたのは、TVの討論番組において保守系国会議員が賜ったのか、あるいは保守系言論人の発言だったか覚えていないが、筆者のまわりの俗物保守派のあいだではしばしば使用される。
日本の近現代史において、日英同盟(Anglo-Japanese Alliance)が締結されていた期間(1902~1923)、日本帝国は順風満帆だった。日露戦争勝利(1904)、不平等条約解消=関税自主権獲得(1911)、第一次世界大戦参戦及び勝利(1914-1918)といった具合である。ところが、同盟廃棄後、満州事変(1930)を契機として、日本帝国は侵略戦争の道を突き進み、1945年の大破局を迎えたことはいうまでもない。
敗戦後の日本はアメリカの占領下におかれ、GHQの指令により国を運営してきたが、1952年、日米同盟(Japan-US Alliance)の締結(註)後、日英同盟締結後と同様に、日本は国際舞台において成功の道を歩んできている。そのとき講和条約が発効し、以降、日本は日米同盟に包摂されるかのように復興、繁栄を続け、GDP世界3位、G7(7大先進国)の一つという「大国」に成長している。
前出の「アングロサクソンに~」という言説は、(わが国は)大英帝国(戦前)、アメリカ合衆国(戦後)という超大国に追随していればいい、という没主体性を別言しただけの俗論である。だがいみじくも、その没主体性が日本を繁栄に導いたことも事実なのである。だが、それを国体とするのはなじまない。
著者(白井聡)が「永久敗戦レジューム」と定義した日本の戦後体制は、いい得て妙であるが、戦後の国体の中心にアメリカを据えるのは無理がある。日本の国体は明治維新に確立した天皇制国家であり、それは戦前・戦中・戦後も一貫している。著者(白井聡)は、国体の中心が戦後、天皇からアメリカに移ったというが、その戦後体制は国体の変化というよりも、明治以来の超大国依存、没主体的国家・国民性と規定すれば済む。日本の国体の真の変換は、天皇制か共和制かの二者択一以外にない。
著者(白井聡)の論の基調に流れる危険性
著者(白井聡)は、本書冒頭に今生天皇の退位の「お言葉」を掲げ、文末もそれで終わっている。著者(白井聡)は天皇と安倍政権を対立的関係に並べ、天皇の側に、民主主義の可能性を見出している。著者(白井聡)の認識は、かつて2.26事件で決起した青年将校が抱いた「恋闕の情」及び政治家・官僚に対する「君側の奸」という反感、すなわち、あくまでも純粋である「国民の天皇」を希求する情念に通じている。
著者(白井聡)の「お言葉」の受止めの延長線上には、安倍首相を筆頭とした政(政治家)、官(官僚)、学(学者)産(実業家)、そしてメディアが「君側の奸」であり、彼らはアメリカ依存だからダメだが、天皇だけは清いという結論を暗示している本書末に、著者(白井聡)は次のように書いている。
註:Japan-US Allianceとは、以下の2つの条約の総称である。
本書は、国体という概念を媒介に日本の近現代史を読み直しつつ、現在の安倍政権を痛烈に批判するという建付けである。著者の白井聡は戦後日本の諸状況について、「永続敗戦」という著者自身になる造語概念を使って規定する政治学者。本書はその論の発展的展開として位置づけられる。それゆえ、まずもって「永続敗戦」の原理をおさえておく。
「永続敗戦」とは(略)、日本の戦後レジュームの核心を指示し、その特殊な対米従属の在り方を解明するための概念である。その原理は、アメリカのアジアでの最重要の同盟者となることによって、第二次世界大戦における敗北が持つ意味を曖昧化すること、すなわち、「敗戦の否認」である。敗戦の否認を続けるためには際限なくアメリカに従属せねばならず、際限のない対米従属を続ける限り敗戦を否認し続けることができる。かくして、負けを正面から認めたくないがために、永遠と負け続ける。この原理を主柱として、親米保守派がその支配に鎮座し続ける体制が「永続敗戦レジューム」である。(本書註:P342)(※『永続敗戦論―戦後日本の核心』講談社+α文庫、2016年、61~77頁参照)日本の現代史における国体
(一)北一輝の『国体論及び純正社会主義』
日本の近現代史において、筆者の記憶に残る国体に係る事案は3つある。最初のそれは1906年(明治39年)、北一輝の処女作『国体論及び純正社会主義』の発刊である。北一輝は後の2.26事件(1935/昭和10年2月26日)を起こした青年将校に強い影響を及ぼした思想家。北一輝の思想は本書で詳細に取り上げらえているので説明を省くが、大雑把にその肝を示せば、天皇は国民のためにあるという、「天皇機関説」の範疇にある。北一輝が2.26事件の思想的指導者として死刑に処せられた理由は、北の天皇論に影響された青年将校により国家転覆未遂事件が起きたからにほかならない。
(二)「国体明徴の声明」
第二番目は、2.26事件の直後、同年8月に、ときの政府が発表した「国体明徴の声明」である。この声明は、軍部及び右翼が天皇を統治権行使の機関とみる学説を攻撃し、その主張者美濃部達吉を「学匪」ときめつけたので、天皇機関説事件ともよばれる。「国体明徴の声明」はときの権力者が北の思想と2.26事件を経験し、いま国体は危機にある、という認識から発せられたともいえる。貴族院・衆議院とも国体明徴を決議し、美濃部は貴族議員を辞め、その著書『憲法概要』『憲法精義』は発禁となった。これをもって政府は軍部の要求に負けて天皇機関説を排撃し、議会主義を否定し、学問言論思想の自由に強く干渉するようになる。
ときの岡田啓介内閣が発した「国体明徴の声明」は、その後の軍部独裁、アジア・太平洋戦争突入という、日本現代史の転換点を象徴する重大な事件だった。
国体明徴事件が示すとおり、戦前の軍部、右翼によって持ち出された国体とは、著者(白井聡)の表現を借りれば、“万世一系の天皇を頂点に戴いた「君臣相睦み合う家族国家」を理念として全国民に強制する体制(P3)”と定義される。天皇を絶対不可侵・超越的存在の神として崇め、日本国民は臣民として天皇(の命令)に絶対服従しなければならないとする国家原理とも別言できる。なお「明徴」とは、「明らかにする」と同義である。
(三)敗戦直前、戦争終結条件としての国体護持
国体が次に顕在化するのは、日本のアジア・太平洋戦争末期、日本の敗戦が決定的となり、連合軍からポツダム宣言(無条件降伏)の受諾を強いられたときであった。ときの日本帝国の為政者は、戦争終結の条件として国体護持に執着したため、無条件降伏を受け入れなかった。そのため連合軍の本土無差別爆撃(1944/6~1945/8)、沖縄地上戦(1945/3)、広島・長崎原爆投下(1945/8)という、連合軍による、日本の民間人大量殺戮を招き寄せた。
それでも無条件降伏を頑なに拒んだ日本帝国の為政者が、一転してアメリカ軍に降伏したのは、1945年8月9日のソ連軍の日本帝国領内侵攻作戦の開始であった。昭和天皇及びその側近はソ連軍の対日参戦に恐怖し、降伏を決意した。
昭和天皇が積極的にアメリカを「迎え入れた」最大の動機は、共産主義への恐怖と嫌悪であった・・・皇帝一家の殺害にまで至ったロシア革命の帰結と敗戦直後の社会混乱に鑑みれば、「共産主義革命=国体の破壊」という観念自体は全くの絵空事ではなかった。したがって、アメリカの軍事的プレゼンスを積極的に受け入れることは、まさに「国体護持」の手段たり得たのである。(P56~57)日本の近現代史において国体が顕在化するのは、天皇制度が危機に瀕している状況下である。天皇を国民の側に引き寄せる北一輝の思想がときの支配層を震撼させ、しかも、政府転覆未遂事件まで起きた。ときの政府はその思想的指導者及び青年将校のリーダーを処刑し、より強権的支配を確立する。加えて、民主的勢力を一掃し、独裁体制を固める。
その政府が起こした戦争の末期、敗戦という国家滅亡の危機にあっては、敵であったアメリカの支配を積極的に受け入れ、天皇(家)を抹殺しかねないソ連軍=「共産主義」から国体を護持することに成功する。戦争当事者である日本帝国の為政者は、ソ連軍=共産主義から国体を守るため、アメリカにひれ伏すという選択を行い、結果、国体は守られた。それが、戦後の象徴天皇制である。
戦後の国体とはなにか
本書における明治維新からアジア太平洋戦争敗戦までの国体論は、橋川文三の未完の著『昭和維新試論』等を下敷きにして、簡潔かつ明確に整理されている。ところが、戦後の国体論は難解である。著者(白井聡)の戦後の国体論は、戦前の国体を体現した天皇の代わりに、アメリカをそっくり代入するという図式に単純化される。その点において筋が悪い。
著者(白井聡)の戦後の国体論の中核にあるのは、アメリカである。本書は、戦後日本の対米従属を国体だと規定するわけだが、その論証は矢部浩二や孫崎亨の戦後日米関係論に依拠していて、それを超えるような情報や見識が見当たらない。強いて新鮮だと思わせる部分を挙げれば、「天皇制民主主義」という言葉の提起だろうか。
アメリカの日本占領政策は古代からのセオリーに倣ったもの
天皇が日本帝国の戦争に関与していることは明らかだった。戦勝国側は、天皇の戦争責任を強く追及するかと思われたが、アメリカは天皇の戦争責任を免責し、新憲法の中で天皇を日本国民の象徴と新たに規定した。
著者(白井聡)は、アメリカの天皇免責について、アメリカの日本研究の結果だと大げさに指摘しているがそうでもない。たとえば、新約聖書の舞台となった現在のイスラエル・パレスチナの地は、いまから2000年余り前、ローマ帝国の属州だった。この地の支配者は、ローマ帝国第5代ユダヤ属州総督ポンテオ・ピラトだった。ピラトはイエスを磔刑に処した人物として新約に記されている。
そのピラトだが、彼はイエスを処刑することに最後まで消極的だった。というのも、ローマが属州を支配する構図は、総督自らが強権を振るうことではなく、ユダヤ教の神官に属州の統治を委任するものだったからである。武力を背景にして占領者が前面に出る直接的支配は、被占領地の人民の抵抗を受けやすい。ローマ兵に犠牲者が出る確率が高い。侵略者、占領者が当該地を安定的に統治する方法は、土着の支配者を配下にして間接的に支配するのがセオリーである。
2000年前に遡らなくとも、日本帝国が中国東北部に侵略して「建国」した満州国においても、日本帝国はローマ帝国と同様の統治方法を採用した。1931(昭和6)年9月、柳条湖事件に端を発して満州事変が勃発、関東軍により満州全土が占領され、関東軍主導の下に同地域は中華民国からの独立を宣言し、1932年(昭和7年)3月、満州国が「建国」された。元首(満州国執政、後に満州国皇帝)には清朝最後の皇帝・愛新覚羅溥儀が就いた。中華民国によって滅亡した清朝は満州人が漢族を破って建国した王朝だったから、日本帝国が「建国」した満州国に清王朝の末裔を元首に置いたのは、戦勝国アメリカが日本を占領したとき、その国(日本)の天皇を元首(象徴)として残した事例と似通っている。
アメリカの日本占領政策の第一は、日本帝国の武装解除及び占領軍人の安全確保だった。アメリカが警戒したのは、戦争終結後にあっても旧日本軍の残党が日本各所でゲリラ戦を展開することだった。それを防ぐ切札的存在が天皇だった。日本の敗戦直後(1945年)の動きを追ってみよう。
- 8月15日=天皇の戦争終結宣言(玉音放送)
- 8月30日=占領軍総司令官マッカーサー、厚木に到着
- 9月2日=無条件降伏文書調印
- 9月27日=マッカーサーが天皇と会見
戦後の国体の形成というよりも維持は、戦争末期、日本帝国の為政者がソ連=共産主義の日本侵略を阻止するためにアメリカと手を組み、アメリカ主導の占領政策を受け入れたことから始まったのである。戦勝国(アメリカ)にとっても占領政策の柱に天皇を据えることに異議はなかった。
その後、日本は民主国家として再生し、かつての国体とは絶縁したと思われている。明治欽定憲法は撤廃され、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、象徴天皇制などを規定した日本国憲法が施行された。そこで国体は死語と化し、あえて戦後の国体とはなにかと問われれば、日本国憲法こそが戦後のそれというのが、一般的認識として定着した。そればかりか、今日、わが国の状況において、国体をテーマとした議論、論考、研究等としては、鈴木邦男著の『天皇陛下の味方です: 国体としての天皇リベラリズム』くらいしか、見当たらない。
アメリカへの隷属が新たな国体か
敗戦後から今日までの日本の歩みは、著者(白井聡)が指摘するとおり、アメリカに隷属している。とりわけ、現在の安倍首相は、アメリカのトランプ大統領の忠臣といったありさまで、アメリカ・メディアからも嘲笑を受けるありさまである。日本政府は、日米同盟は不変、普遍と認識している、と事ある後に国民に説明する。その結果、日米地位協定が代表するとおり、日本はアメリカの属国以下である。著者(白井聡)は、戦後の日本の為政者が頑ななアメリカ信仰を保持・盲従する心的構造を、アメリカをご本尊とする戦後国体思想だと結論づける。さて、そこが本書を支持するか否かの境目だろう。筆者は著者(白井聡)の論に納得していない。
天皇制の危機的局面に現れる国体擁護の動き
国体がわが国の現代史に現れた局面は、前出のとおり、天皇制が危機的状況に陥った時である。そしてもちろん、国体の護持を国民に呼びかけるのは、革新の側ではなく、絶対的、超越的存在としての天皇を擁護したい勢力からであった。戦前の場合は、議会制民主主義や社会主義の台頭を恐れた軍部及び右翼であり、アジア・太平洋戦争末期の場合は、ソ連(共産主義)の侵攻により、日本の天皇(家)がロシア皇帝(一族)のごとく処刑されることを恐れた日本の為政者からであった。
戦後の反米運動
戦後の日米関係に対する異議申し立ては、本書にあるように、60年安保闘争、68年前後の新左翼・全共闘運動、三島由紀夫の自害、反日爆弾闘争といった、戦後民主主義を相対化する思想に基づく政治運動によった。しかし連合赤軍事件、内ゲバ事件等に代表されるそれら運動組織の自滅行動を契機として、体制側の弾圧及びマスメディアによるネガティブキャンペーンが功を奏し、それら運動組織は「過激派」という蔑称で市民権を失ってしまった。このときに現れた革命運動は左翼にとっては共産主義革命(世界革命)を目指すものであり、唯一、三島由紀夫のそれだけが、アメリカに隷属する天皇、ときの政権及び自衛隊を批判するものであった。戦後体制の暴力的打倒を目指しながら、左派と三島は同床異夢の関係にあった。
日本はアングロサクソンとうまくやれば・・・
日本国民のなかに著者(白井聡)がいう戦後の国体(アメリカ信仰)がどれほど浸透しているのか。浸透というよりも、無意識化されているのか。筆者の直観では、アメリカは日本(人)にとってもっとも親和的な外国であるが、無謬的存在にまでは至っていないと思う。ただ気になるのは、「日本はアングロサクソンとうまくやれば、うまくいく」という俗論である。この言説を耳にしたのは、TVの討論番組において保守系国会議員が賜ったのか、あるいは保守系言論人の発言だったか覚えていないが、筆者のまわりの俗物保守派のあいだではしばしば使用される。
日本の近現代史において、日英同盟(Anglo-Japanese Alliance)が締結されていた期間(1902~1923)、日本帝国は順風満帆だった。日露戦争勝利(1904)、不平等条約解消=関税自主権獲得(1911)、第一次世界大戦参戦及び勝利(1914-1918)といった具合である。ところが、同盟廃棄後、満州事変(1930)を契機として、日本帝国は侵略戦争の道を突き進み、1945年の大破局を迎えたことはいうまでもない。
敗戦後の日本はアメリカの占領下におかれ、GHQの指令により国を運営してきたが、1952年、日米同盟(Japan-US Alliance)の締結(註)後、日英同盟締結後と同様に、日本は国際舞台において成功の道を歩んできている。そのとき講和条約が発効し、以降、日本は日米同盟に包摂されるかのように復興、繁栄を続け、GDP世界3位、G7(7大先進国)の一つという「大国」に成長している。
前出の「アングロサクソンに~」という言説は、(わが国は)大英帝国(戦前)、アメリカ合衆国(戦後)という超大国に追随していればいい、という没主体性を別言しただけの俗論である。だがいみじくも、その没主体性が日本を繁栄に導いたことも事実なのである。だが、それを国体とするのはなじまない。
著者(白井聡)が「永久敗戦レジューム」と定義した日本の戦後体制は、いい得て妙であるが、戦後の国体の中心にアメリカを据えるのは無理がある。日本の国体は明治維新に確立した天皇制国家であり、それは戦前・戦中・戦後も一貫している。著者(白井聡)は、国体の中心が戦後、天皇からアメリカに移ったというが、その戦後体制は国体の変化というよりも、明治以来の超大国依存、没主体的国家・国民性と規定すれば済む。日本の国体の真の変換は、天皇制か共和制かの二者択一以外にない。
著者(白井聡)の論の基調に流れる危険性
著者(白井聡)は、本書冒頭に今生天皇の退位の「お言葉」を掲げ、文末もそれで終わっている。著者(白井聡)は天皇と安倍政権を対立的関係に並べ、天皇の側に、民主主義の可能性を見出している。著者(白井聡)の認識は、かつて2.26事件で決起した青年将校が抱いた「恋闕の情」及び政治家・官僚に対する「君側の奸」という反感、すなわち、あくまでも純粋である「国民の天皇」を希求する情念に通じている。
著者(白井聡)の「お言葉」の受止めの延長線上には、安倍首相を筆頭とした政(政治家)、官(官僚)、学(学者)産(実業家)、そしてメディアが「君側の奸」であり、彼らはアメリカ依存だからダメだが、天皇だけは清いという結論を暗示している本書末に、著者(白井聡)は次のように書いている。
(天皇が)「お言葉」を読み上げたあの常のごとく穏やかな姿には、同時に烈しさが滲み出ていた・・・著者(白井聡)が国体の概念を用いて本書を著そうとした下地に天皇の「お言葉」があったことは明白である。そのことは日本の国体が戦前、戦後を通じて不変であり普遍的であることの逆証明にもなる。著者(白井聡)もその国体に絡めとられ、天皇制か共和制かと問う思考を脱落させてしまったのである。
それは闘う人間の烈しさだ。「この人は何かと闘っており、その闘いには義がある」――そう確信した時、不条理と闘うすべての人に対して筆者が懐く敬意から、黙って通り過ぎることはできないと感じた。ならば、筆者がそこに立ち止まってできることは、その「何か」を能う限り明確に提示することであった。(P340)
註:Japan-US Allianceとは、以下の2つの条約の総称である。
- 1952~1960:「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(Security Treaty Between the United States and Japan)
- 1960~:「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan)
2018年12月22日土曜日
筋トレ仲間忘年会を根津にて開催
2018年12月21日金曜日
内海の人的補償は一岡のトラウマ
FAを使って西武から読売に移籍した炭谷捕手の人的補償が内海投手と決まった。驚きである。まさかである。前の拙Blogにて書いた通り、筆者は宇佐見捕手と予想したのだから大外れに終わった。
内海を獲得した西武は大儲け
西武は炭谷を放出して、内海と2,280万円(炭谷の年俸・5,700万円×40%*ランクB=2,280万円+人的補償としての内海)を獲得したことになる。炭谷と内海の1対1のトレードなら2,280万円は入らなかったわけだから、西武はお得な商売をしたことになる。内海と炭谷の1対1のトレードは、西武はもちろんOKだろうが、読売には話にならない商談だったに違いない。
一方の読売の判断はどうなのだろうか。内海ほどの功労者をプロテクトしなかったのは非情という意見もある。来年、内海が再度、FA宣言して読売に戻るという推測もあるが、西武が人的補償を求めれば、また新たな違う選手を西武にとられることになるので、西武と読売のFA⇔人的補償の循環が永年続くまで。
原辰徳の内海外しは一岡のトラウマから
内海をプロテクトしなかったのは、GMを兼ねた原辰徳(読売の新=出戻り監督)の判断だと思う。FA・人的補償となると、メディアが常に話題にするのが読売の失敗事例、一岡投手の放出である。
一岡投手(当時読売)は大竹投手(当時広島)のFA宣言による読売入団の人的補償で2013年に広島に入団し、以降、2014シーズンから今日まで、広島の貴重な中継ぎ投手として活躍を続けている。その一方、読売に移籍した大竹投手は一年目こそ活躍したものの、以降の成績は下降続き。その結果として、読売のFAの人的補償の失敗事例として、語り継がれている。
一岡投手をプロテクトしなかったそのときの読売の監督が原辰徳だった。おそらくこの失敗は、原辰徳及び読売球団のトラウマとなり、今年のFAでは多くの若手選手をプロテクトしたのではないか。若い才能が他球団で花開いたとしたら、読売は若手を育成できない、読売が若手選手の才能を見通せない――という評価が定着する。そうなれば、球団のイメージはより悪化する。ドラフトで読売に入団したとしても、時間をおかずに海外移籍を希望する若手選手が続出するだろう。
さて、次は広島が読売に対してだれを人的補償として要求するのか。筆者の予想は左のワンポイント・戸根投手だったが、どうやら当たらなそうな予想が濃厚だ。
内海を獲得した西武は大儲け
西武は炭谷を放出して、内海と2,280万円(炭谷の年俸・5,700万円×40%*ランクB=2,280万円+人的補償としての内海)を獲得したことになる。炭谷と内海の1対1のトレードなら2,280万円は入らなかったわけだから、西武はお得な商売をしたことになる。内海と炭谷の1対1のトレードは、西武はもちろんOKだろうが、読売には話にならない商談だったに違いない。
一方の読売の判断はどうなのだろうか。内海ほどの功労者をプロテクトしなかったのは非情という意見もある。来年、内海が再度、FA宣言して読売に戻るという推測もあるが、西武が人的補償を求めれば、また新たな違う選手を西武にとられることになるので、西武と読売のFA⇔人的補償の循環が永年続くまで。
原辰徳の内海外しは一岡のトラウマから
内海をプロテクトしなかったのは、GMを兼ねた原辰徳(読売の新=出戻り監督)の判断だと思う。FA・人的補償となると、メディアが常に話題にするのが読売の失敗事例、一岡投手の放出である。
一岡投手(当時読売)は大竹投手(当時広島)のFA宣言による読売入団の人的補償で2013年に広島に入団し、以降、2014シーズンから今日まで、広島の貴重な中継ぎ投手として活躍を続けている。その一方、読売に移籍した大竹投手は一年目こそ活躍したものの、以降の成績は下降続き。その結果として、読売のFAの人的補償の失敗事例として、語り継がれている。
一岡投手をプロテクトしなかったそのときの読売の監督が原辰徳だった。おそらくこの失敗は、原辰徳及び読売球団のトラウマとなり、今年のFAでは多くの若手選手をプロテクトしたのではないか。若い才能が他球団で花開いたとしたら、読売は若手を育成できない、読売が若手選手の才能を見通せない――という評価が定着する。そうなれば、球団のイメージはより悪化する。ドラフトで読売に入団したとしても、時間をおかずに海外移籍を希望する若手選手が続出するだろう。
さて、次は広島が読売に対してだれを人的補償として要求するのか。筆者の予想は左のワンポイント・戸根投手だったが、どうやら当たらなそうな予想が濃厚だ。
2018年12月19日水曜日
2018年12月8日土曜日
2018年12月5日水曜日
高輪ゲートウェイは歴史・文化の破壊である
民俗学者で日本地名研究所長であった谷川 健一(1921-2013)は、“地名は大地に刻まれた刺青である”という意味のことを言った。戦後の住居表示法施行に伴う地名変更が行政により進められ、多くの貴重な町名等が失われた状況を憂いた発言だった。それでも、学校名、駅名、バスの停留所等に地名を残す努力が続けられてきた。
さて、「高輪ゲートウェイ」である。恥ずかしい。江戸東京の歴史、文化に対する冒涜である。かつて国鉄は、山手線の新駅に「御徒町」という由緒ある駅名を冠した。この地域は、江戸期、御徒と呼ばれた下級武士(騎乗を許されない歩兵)が居住した地域であったのだが、前出の町名変更により、台東という表示に変更されてしまった結果、町名としての御徒町は消滅した。国鉄はそれを新駅名として後世に残したのである。その国鉄は解体され、東京を走る旧国鉄の鉄道は、JR東日本という民営企業が引き継いだ。
このたびの山手線新駅の駅名については、一般公募したにもかかわらず、公募数下位の「高輪ゲートウェイ」に決まったという。公募は形式であって、JR東日本が「高輪ゲートウェイ」という駅名をあらかじめ決定していたと思われる。つまり、社長決済による決定であろう。命名者はJR東日本の現社長である。
新駅名を得意げに発表するJR 東日本の某社長の風貌からは、失礼ながら歴史、文化、民俗学に思いをはせるリベラルアーツが感じられない。この駅名はほぼ永遠に近い時間、東京に残されることになろう。某社長の名前は、この愚かな駅名の命名者として、無教養の経営者として、歴史・文化の破壊者として、刺青のごとく消え去ることがない。愚かというよりも、哀れである。

さて、「高輪ゲートウェイ」である。恥ずかしい。江戸東京の歴史、文化に対する冒涜である。かつて国鉄は、山手線の新駅に「御徒町」という由緒ある駅名を冠した。この地域は、江戸期、御徒と呼ばれた下級武士(騎乗を許されない歩兵)が居住した地域であったのだが、前出の町名変更により、台東という表示に変更されてしまった結果、町名としての御徒町は消滅した。国鉄はそれを新駅名として後世に残したのである。その国鉄は解体され、東京を走る旧国鉄の鉄道は、JR東日本という民営企業が引き継いだ。
このたびの山手線新駅の駅名については、一般公募したにもかかわらず、公募数下位の「高輪ゲートウェイ」に決まったという。公募は形式であって、JR東日本が「高輪ゲートウェイ」という駅名をあらかじめ決定していたと思われる。つまり、社長決済による決定であろう。命名者はJR東日本の現社長である。
新駅名を得意げに発表するJR 東日本の某社長の風貌からは、失礼ながら歴史、文化、民俗学に思いをはせるリベラルアーツが感じられない。この駅名はほぼ永遠に近い時間、東京に残されることになろう。某社長の名前は、この愚かな駅名の命名者として、無教養の経営者として、歴史・文化の破壊者として、刺青のごとく消え去ることがない。愚かというよりも、哀れである。

2018年12月2日日曜日
NPB、今年最後のお楽しみ(読売の人的補償選手は?)
炭谷(西武)、丸(広島)のFAによる読売への移籍が決まった。そのことによって人的補償で読売から出ていく選手がだれになるのか、2018-シーズンオフ、最後のお楽しみといったところ。NPBファンは、読売のプロテクトから外れる選手の予想に興味津々である。人的補償選手を予想るす前に、FA制度により発生する補償の概要を確認しておく。
(一)FA宣言した選手のランク付け
FA宣言した選手が他球団に移籍した場合、移籍された球団はその見返り(補償)を移籍先に求めることができる。補償は、移籍した選手の元球団の年俸による〈格付け〉に基づく。〈格付け〉は、日本人選手の旧年俸順に上位3位までを〈ランクA〉、4位から10位までを〈ランクB〉、11位以下を〈ランクC〉とする。〈ランクA〉と〈ランクB〉がFA移籍した場合に限り補償が発生する。
炭谷(西武)は〈ランクB〉、丸(広島)は〈ランクA〉であるから、西武、広島とも読売に対し補償を求めることができる。補償は、〔金銭補償〕+〔人的補償〕である。
(二)補償の内容
〔金銭補償〕
移籍先球団は〈ランクA〉の選手獲得の場合は旧年俸の50%(2度目以降のFAでは25%)を、ランクBの選手獲得の場合は旧年俸の40%(2度目以降のFAでは20%)を前球団へ支払わなければならない。
〔人的補償〕
移籍先球団は前球団が指名した上記の獲得制限外の選手1名を与えなければならない。ただし前球団が求めない場合は、〈ランクA〉の選手獲得の場合は旧年俸の30%(2度目以降のFAでは15%)、〈ランクB〉の選手獲得の場合は上記の獲得制限外の選手1名または旧年俸の20%(2度目以降のFAでは10%)を前球団へ支払わなければならない。
人的補償を求めない場合(金銭補償に加えて、〈ランクA〉の選手獲得の場合は旧年俸の30%(2度目以降のFAでは15%)、ランクBの選手獲得の場合は旧年俸の20%(2度目以降のFAでは10%)を得ることができる。
(三)丸(広島)の場合の実際の補償内容
丸(推定年俸2.1億円)のFA移籍により、広島は読売から金銭補償として、2.1×0.5=1.05億円が入る。人的補償をしない場合、1.05+2.1×0.3(=0.63)=1.68億円が入る。広島は6300万円か人的補償を選択することになるわけだが、人的補償のほうが魅力的であるから、前出の金銭補償に加えて人的補償を求める。
(四)人的補償と獲得制限選手(プロテクト)
獲得制限選手名簿(28名)がいわゆるプロテクトであり、プロテクトから外れた選手が人的補償対象選手である。前球団はその中からチーム強化に必要とする選手を移籍先球団に申し出ることとなる。また、前球団が人的補償できないのは、プロテクトした28名の選手のほか、FA権取得により外国人枠の適用外になった選手を含む外国人選手、直近のドラフトで獲得した新人選手である。
(五)西武と広島の人的補償の優先順位
複数名のFA宣言選手と契約した場合には、それぞれの球団に異なる獲得可能選手リストを提示できる。万一、人的補償選手が複数の球団で重複した場合には、移籍先球団と同一連盟内の球団が優先される。同一連盟内であれば同年度の勝率が低い球団が優先される。読売は炭谷(西武)と丸(西武)の2選手をFAで獲得したから、西武と広島がともに人的補償を要求した場合、双方に向けて2種類のプロテクト名簿を提出する。西武と広島が同一選手の獲得を申し出た場合は、広島に優先権がある。
(六)補償に係る日程
補償に関する日程は、まずFA選手と移籍先球団との選手契約締結がコミッショナーより公示された日が起点となり、2週間以内にまず移籍先球団が上記の獲得制限選手を除いた選手名簿を提示する。この後起点より40日以内に全ての補償を完了しなければならないが、金銭補償に限り前球団の同意があれば40日を延長することができる。人的補償として選ばれた選手が移籍を拒否した場合、その選手は資格停止選手となり処分が解除されるまで試合をすることができなくなる。補償は金銭補償のみだった場合と同じになる。
(七)プロテクトから外れる読売の選手は?
読売がプロテクトする28選手及び外れる選手を予想すると――
プロテクトか人的補償対象かのボーダーラインにいる選手は、先発投手陣では昨シーズン1勝の大竹及び桜井。リリーフでは谷岡、池田、利根。大竹が人的補償として広島が指名すると、古巣復帰となる。捕手は阿部が捕手復帰を希望しているというから、宇佐美あたりか。野手では、ユーティリティープレイヤーの中島の入団で、同タイプの吉川大ではないか。
(八)西武、広島が人的補償で獲得する選手
西武、広島は野手が豊富。補償の優先順位は投手→捕手→野手 の順になろう。プロテクトから外した読売の選手のうち、広島、西武が欲しい選手はいるか。筆者の見立てでは、広島が投手で、西武が捕手。ずばり、広島が左のワンポイントの利根、西武が炭谷の代替として宇佐美を人的補償として要求すると思う。
(一)FA宣言した選手のランク付け
FA宣言した選手が他球団に移籍した場合、移籍された球団はその見返り(補償)を移籍先に求めることができる。補償は、移籍した選手の元球団の年俸による〈格付け〉に基づく。〈格付け〉は、日本人選手の旧年俸順に上位3位までを〈ランクA〉、4位から10位までを〈ランクB〉、11位以下を〈ランクC〉とする。〈ランクA〉と〈ランクB〉がFA移籍した場合に限り補償が発生する。
炭谷(西武)は〈ランクB〉、丸(広島)は〈ランクA〉であるから、西武、広島とも読売に対し補償を求めることができる。補償は、〔金銭補償〕+〔人的補償〕である。
(二)補償の内容
〔金銭補償〕
移籍先球団は〈ランクA〉の選手獲得の場合は旧年俸の50%(2度目以降のFAでは25%)を、ランクBの選手獲得の場合は旧年俸の40%(2度目以降のFAでは20%)を前球団へ支払わなければならない。
〔人的補償〕
移籍先球団は前球団が指名した上記の獲得制限外の選手1名を与えなければならない。ただし前球団が求めない場合は、〈ランクA〉の選手獲得の場合は旧年俸の30%(2度目以降のFAでは15%)、〈ランクB〉の選手獲得の場合は上記の獲得制限外の選手1名または旧年俸の20%(2度目以降のFAでは10%)を前球団へ支払わなければならない。
人的補償を求めない場合(金銭補償に加えて、〈ランクA〉の選手獲得の場合は旧年俸の30%(2度目以降のFAでは15%)、ランクBの選手獲得の場合は旧年俸の20%(2度目以降のFAでは10%)を得ることができる。
(三)丸(広島)の場合の実際の補償内容
丸(推定年俸2.1億円)のFA移籍により、広島は読売から金銭補償として、2.1×0.5=1.05億円が入る。人的補償をしない場合、1.05+2.1×0.3(=0.63)=1.68億円が入る。広島は6300万円か人的補償を選択することになるわけだが、人的補償のほうが魅力的であるから、前出の金銭補償に加えて人的補償を求める。
(四)人的補償と獲得制限選手(プロテクト)
獲得制限選手名簿(28名)がいわゆるプロテクトであり、プロテクトから外れた選手が人的補償対象選手である。前球団はその中からチーム強化に必要とする選手を移籍先球団に申し出ることとなる。また、前球団が人的補償できないのは、プロテクトした28名の選手のほか、FA権取得により外国人枠の適用外になった選手を含む外国人選手、直近のドラフトで獲得した新人選手である。
(五)西武と広島の人的補償の優先順位
複数名のFA宣言選手と契約した場合には、それぞれの球団に異なる獲得可能選手リストを提示できる。万一、人的補償選手が複数の球団で重複した場合には、移籍先球団と同一連盟内の球団が優先される。同一連盟内であれば同年度の勝率が低い球団が優先される。読売は炭谷(西武)と丸(西武)の2選手をFAで獲得したから、西武と広島がともに人的補償を要求した場合、双方に向けて2種類のプロテクト名簿を提出する。西武と広島が同一選手の獲得を申し出た場合は、広島に優先権がある。
(六)補償に係る日程
補償に関する日程は、まずFA選手と移籍先球団との選手契約締結がコミッショナーより公示された日が起点となり、2週間以内にまず移籍先球団が上記の獲得制限選手を除いた選手名簿を提示する。この後起点より40日以内に全ての補償を完了しなければならないが、金銭補償に限り前球団の同意があれば40日を延長することができる。人的補償として選ばれた選手が移籍を拒否した場合、その選手は資格停止選手となり処分が解除されるまで試合をすることができなくなる。補償は金銭補償のみだった場合と同じになる。
(七)プロテクトから外れる読売の選手は?
読売がプロテクトする28選手及び外れる選手を予想すると――
- 投手(13)=澤村、菅野、畠、山口俊、今村、田口、鍬原、宮國、内海、野上、吉川光、高田、中川(森福、大竹、桜井、谷岡、池田、戸根、高木京、大江)
- 捕手(2)=小林、大城(宇佐美、岸田、田中貴)
- 内野(6)=吉川尚、坂本・阿部・岡本・山本、田中俊(北村、若林、湯浅、増田、吉川大)
- 外野(7)=陽、長野、亀井、重信、石川、松原、和田恋(立岡、村上)
- 28選手がプロテクト選手。赤太字がプロテクト外=人的補償対象選手
プロテクトか人的補償対象かのボーダーラインにいる選手は、先発投手陣では昨シーズン1勝の大竹及び桜井。リリーフでは谷岡、池田、利根。大竹が人的補償として広島が指名すると、古巣復帰となる。捕手は阿部が捕手復帰を希望しているというから、宇佐美あたりか。野手では、ユーティリティープレイヤーの中島の入団で、同タイプの吉川大ではないか。
(八)西武、広島が人的補償で獲得する選手
西武、広島は野手が豊富。補償の優先順位は投手→捕手→野手 の順になろう。プロテクトから外した読売の選手のうち、広島、西武が欲しい選手はいるか。筆者の見立てでは、広島が投手で、西武が捕手。ずばり、広島が左のワンポイントの利根、西武が炭谷の代替として宇佐美を人的補償として要求すると思う。
2018年12月1日土曜日
2018年11月30日金曜日
徒然なるままにNPB‐2018シーズンをふり返る
NPB‐2018シーズンは、広島の丸のFAによる読売入団をもって幕を閉じた。そこで、徒然なるままに今年のNPBをふり返ってみよう。
セは1強(広島)、5弱が継続
セリーグが広島、パリーグは西武が優勝した。CSはセが広島、パはソフトバンクが制し、日本シリーズはソフトバンクが優勝した。
筆者のリーグ戦セリーグ順位予想は3月14日付の拙Blogにて示したとおり、1.広島、2.阪神、3.読売、4.DeNA、5.中日、6.ヤクルト の順であった。
結果は、1.広島、2.ヤクルト、3.読売、4.DeNA、5.中日、6.阪神となり、ヤクルトと阪神の順位がそっくり入れ替わっていた。ほかの4球団の順位は予想どおりで、なんとも奇妙な順位となった。筆者の予想が当たったわけではないが、それなりの結果だったと思う。要するに2018シーズンのセリーグは昨年と同様、1強(広島)5弱(ほか5球団)の構図に変化がなかった。
金本(阪神前監督)に采配のキレなし
5弱の分析をしても意味はないと思うが、2位と予想した阪神が最下位にまで沈んだのは意外だった。その第一の要因は金本采配。筆者及びメディアが阪神の戦力を過大評価したこともあるが、それ以上に金本采配に疑問が多かった。
加えて2018年は夏季に猛暑が続き、野球界全体に打高投低傾向が著しかった。阪神打線は糸井、福留のベテラン頼り。とうとう彼らにも衰えが顕著になった。しかるに、若手が伸び悩んだ。要するに、ベテラン頼みで若手育成に失敗したまま、シーズンを迎えてしまったわけだ。金本采配も疑問だらけ・・・最下位は必然だった。
分厚い選手層で、読売3位を死守
ペナントレースで3位となった読売。分厚い選手層でどうにかAクラスに踏みとどまった。この球団も故障者に泣かされた。投手陣ではマシソン、カミネロ(退団)、ヤングマン、桜井、畠、西村(引退)、杉内(引退)が戦力にならなかった。打線も坂本、吉川尚、陽、長野、ゲレーロ(体調不良?)、石川らが長期間、戦列を離れた。これだけの選手が戦列を離れながら3位をキープできたのは繰り返すが、ぶ厚い選手層ゆえだ。2球団分の選手を抱えている。
岡本(読売)の成長は筆者には大サプライズ
読売の、というよりもNPB最大のサプライズは岡本の大活躍。入団一年目(2015年)はともかくとして、彼の2年目(2016年)の成績は、打率.100(3試合、10打数、1安打、0本塁打、打点0、三振2)。続く2017年は、打率.194(15試合、31打数、6安打、0本塁打、打点0、三振10)にとどまった。
ところが今シーズンにはなんと、打率.309(143試合、540打数、167安打、33本塁打、100打点、120三振)の強打者に大変身した。3年間の平均打率が1割台の選手が4年目にして、これだけ打撃成績が向上した事例については覚えがない。大変身、大サプライズ、大驚愕という表現でも足りない。アスリートとはこんなものか。
爆買い再開した読売
岡本の活躍に象徴されるように、読売は高橋(前監督)体制3年目で若手育成への方針転換の兆が見えたものの、高橋の退任、原元監督の再就任で、以前のFA制度依存体質に戻ってしまった。2018オフシーズンのFAで炭谷捕手(西武)、そして超大物の丸外野手(広島)を獲得。オリックスを自由契約になった中島内野手、MLBパドレスで20本塁打の実績を誇るビヤヌエバ(内外野手)も獲得した。
阿部が捕手復帰を表明しているから、読売が想定する野手陣のレギュラー(先発)候補と序列は以下のように予想される。
捕手=炭谷→小林→阿部(1塁)→大城(捕手)
1塁=ビヤヌエバ→阿部(捕手)→岡本(三塁)→大城(捕手)
2塁=中島→吉川尚→田中俊→山本
3塁=岡本→中島→吉川大
遊撃=坂本→吉川尚→山本
左翼=ゲレーロ→(ビヤヌエバ→亀井→重信)
中堅=丸→(ビヤヌエバ→陽→亀井→重信)
右翼=長野→(ビヤヌエバ→亀井→陽→重信)
一軍ベンチ入りが微妙なのが炭谷に押し出される大城、宇佐美。大城は打撃センスを買われて一塁の練習に取り組んでいるようだから、宇佐美よりは一軍出場機会が残されているかもしれない。中島に押し出されるのが吉川大、山本。ビヤヌエバに押し出されるのが阿部になるが、阿部も捕手復帰と代打でベンチ外というのは考えられない。
読売が補強した丸、ビヤヌエバ、炭谷、中島の4選手と2年目のゲレーロは年俸1億円を超える選手たち。8枠のうち5枠が補強選手及び外国人選手で占められる。次いで、坂本、岡本の2枠がレギュラー確約だから、空席は1。その一席も長野、亀井、陽との争いに勝たなければならない。読売の若手の出場機会は、前出のレギュラーに故障者が出た場合か、不調に陥った場合に限られる。
読売の爆買い効果は微々たるもの
読売の爆買い補強はチーム強化につながるのだろうか。もちろん答えは「NO」。2018シーズンの1点差ゲーム勝率 をみると(読売はチーム防御率リーグ1位なのにもかかわらず)、セリーグの最下位で他の5球団に比べて著しく低い。
その主因はセットアッパー、クローザーの人材不足。クローザーとして期待された澤村の防御率が4.64(49登板)、カミネロが同5.79(20)、セットアッパーとして期待された上原が3.63(36)、マシソンが2.97(34)とこちらも芳しくない。
リリーフ陣となると、池田4.07(27)、谷岡5.76(25)、田原2.56(29)、中川5.02(30)、宮國1.97(29)、吉川光4.26(22、先発登板を含む)となり、防御率1点台は宮國ただ一人。読売が強化すべきは、投手陣しかも中継ぎ、抑えであった。
しかるに、今シーズンオフ(2018/11/30)時点において、読売が投手陣強化のための補強情報は伝えられていない。来シーズン開幕前までに読売フロントが行わなければならない第一の仕事は、外国人を含めたクローザー及びセットアッパー探しだ。頭数だけでも上原、カミネロの抜けた穴を補修しなければならない。
丸のFA移籍について
FA宣言した丸(広島)が本日(11/30)、読売入団を公表した。この結果は驚くに当たらない。彼がFA宣言した時点で、その行き先が読売であろうことはだれもが予想し得た。契約金、契約年数、引退後の待遇等において、金満・読売に勝てるところはない。心情的には広島残留してほしいが、選手生命は短い。稼げるときに稼ぐべきだ。
丸は読売で活躍できるのか
丸が2019シーズン、新天地・読売で活躍できるのか。筆者は、ある程度の成績を残すだろうが、2018を下回ると予想する。
その理由は、彼の打撃フォームが変則であること。丸の打撃フォームの特徴は、バットの先端を揺らせてタイミングをとる点。このフォームはタイミングを狂わせると、長期スランプに陥る難点をもっている。極めて微妙な動きをインパクトの前に取り入れる。ボールを打つ前に一段階余分の動作をとる。そこにリスクが生じる。好調時のタイミングをひとたび失うと、一気に崩れる。崩れの要因は、①加齢による体力の衰え及び動体視力低下、②精神面の変調及び環境変化、③相手投手の研究――などによる。どれか一つというよりも、複合的要因として丸を襲う。丸が打撃フォームを崩せば当然、打率は下がるし打点も上がらなくなる。読売という人気球団のプレッシャー及び広島退団の後悔などが丸を襲い、心労が重なる。打撃不振は長期に及ぶだろう。彼の成績は2018シーズンを頂点として、以降、下り坂に向かう。
丸は読売との試合でよく打った。ところが、その読売に入団したのだから、得意球団が減ったことになる。広島(投手陣)は丸の弱点を知り尽くしているから、広島投手陣はそこをついてくる。他球団も広島の攻め方を真似るから、その結果だけでも、丸の打撃成績は落ちる。丸も広島投手陣を知り尽くしているが、読売投手陣と同程度打ち崩せるかというと、そうはいかない(と筆者は思う)。
読売・阿部の捕手再転向
これは論ずるに値しない。まず成功はない。阿部が捕手にすわれば、他球団に盗塁のチャンスが生まれる。
今シーズンの日本シリーズでソフトバンクの甲斐捕手が広島の足を封じMVPに選ばれ、「甲斐キャノン」という新語を生んだ。
甲斐が強肩の持ち主であることは間違いないが、それ以上に下半身が素晴らしい。捕球してから投球動作に至るフットワーク(わずか1歩半程度だが)と、腰を下ろした姿勢から投球動作をつくる立ち上がるスピードがすごい。その基盤となっているのが下半身の安定、強さ、速さだ。
二塁投球の正確なコントロールを支えているのは甲斐の強い体幹だ。天性の身体の強さと適正なトレーニングの結果だろう。阿部が甲斐のような捕手に復活することは、奇跡が起きない限り無理だ。
セは1強(広島)、5弱が継続
セリーグが広島、パリーグは西武が優勝した。CSはセが広島、パはソフトバンクが制し、日本シリーズはソフトバンクが優勝した。
筆者のリーグ戦セリーグ順位予想は3月14日付の拙Blogにて示したとおり、1.広島、2.阪神、3.読売、4.DeNA、5.中日、6.ヤクルト の順であった。
結果は、1.広島、2.ヤクルト、3.読売、4.DeNA、5.中日、6.阪神となり、ヤクルトと阪神の順位がそっくり入れ替わっていた。ほかの4球団の順位は予想どおりで、なんとも奇妙な順位となった。筆者の予想が当たったわけではないが、それなりの結果だったと思う。要するに2018シーズンのセリーグは昨年と同様、1強(広島)5弱(ほか5球団)の構図に変化がなかった。
金本(阪神前監督)に采配のキレなし
5弱の分析をしても意味はないと思うが、2位と予想した阪神が最下位にまで沈んだのは意外だった。その第一の要因は金本采配。筆者及びメディアが阪神の戦力を過大評価したこともあるが、それ以上に金本采配に疑問が多かった。
加えて2018年は夏季に猛暑が続き、野球界全体に打高投低傾向が著しかった。阪神打線は糸井、福留のベテラン頼り。とうとう彼らにも衰えが顕著になった。しかるに、若手が伸び悩んだ。要するに、ベテラン頼みで若手育成に失敗したまま、シーズンを迎えてしまったわけだ。金本采配も疑問だらけ・・・最下位は必然だった。
分厚い選手層で、読売3位を死守
ペナントレースで3位となった読売。分厚い選手層でどうにかAクラスに踏みとどまった。この球団も故障者に泣かされた。投手陣ではマシソン、カミネロ(退団)、ヤングマン、桜井、畠、西村(引退)、杉内(引退)が戦力にならなかった。打線も坂本、吉川尚、陽、長野、ゲレーロ(体調不良?)、石川らが長期間、戦列を離れた。これだけの選手が戦列を離れながら3位をキープできたのは繰り返すが、ぶ厚い選手層ゆえだ。2球団分の選手を抱えている。
岡本(読売)の成長は筆者には大サプライズ
読売の、というよりもNPB最大のサプライズは岡本の大活躍。入団一年目(2015年)はともかくとして、彼の2年目(2016年)の成績は、打率.100(3試合、10打数、1安打、0本塁打、打点0、三振2)。続く2017年は、打率.194(15試合、31打数、6安打、0本塁打、打点0、三振10)にとどまった。
ところが今シーズンにはなんと、打率.309(143試合、540打数、167安打、33本塁打、100打点、120三振)の強打者に大変身した。3年間の平均打率が1割台の選手が4年目にして、これだけ打撃成績が向上した事例については覚えがない。大変身、大サプライズ、大驚愕という表現でも足りない。アスリートとはこんなものか。
爆買い再開した読売
岡本の活躍に象徴されるように、読売は高橋(前監督)体制3年目で若手育成への方針転換の兆が見えたものの、高橋の退任、原元監督の再就任で、以前のFA制度依存体質に戻ってしまった。2018オフシーズンのFAで炭谷捕手(西武)、そして超大物の丸外野手(広島)を獲得。オリックスを自由契約になった中島内野手、MLBパドレスで20本塁打の実績を誇るビヤヌエバ(内外野手)も獲得した。
阿部が捕手復帰を表明しているから、読売が想定する野手陣のレギュラー(先発)候補と序列は以下のように予想される。
捕手=炭谷→小林→阿部(1塁)→大城(捕手)
1塁=ビヤヌエバ→阿部(捕手)→岡本(三塁)→大城(捕手)
2塁=中島→吉川尚→田中俊→山本
3塁=岡本→中島→吉川大
遊撃=坂本→吉川尚→山本
左翼=ゲレーロ→(ビヤヌエバ→亀井→重信)
中堅=丸→(ビヤヌエバ→陽→亀井→重信)
右翼=長野→(ビヤヌエバ→亀井→陽→重信)
一軍ベンチ入りが微妙なのが炭谷に押し出される大城、宇佐美。大城は打撃センスを買われて一塁の練習に取り組んでいるようだから、宇佐美よりは一軍出場機会が残されているかもしれない。中島に押し出されるのが吉川大、山本。ビヤヌエバに押し出されるのが阿部になるが、阿部も捕手復帰と代打でベンチ外というのは考えられない。
読売が補強した丸、ビヤヌエバ、炭谷、中島の4選手と2年目のゲレーロは年俸1億円を超える選手たち。8枠のうち5枠が補強選手及び外国人選手で占められる。次いで、坂本、岡本の2枠がレギュラー確約だから、空席は1。その一席も長野、亀井、陽との争いに勝たなければならない。読売の若手の出場機会は、前出のレギュラーに故障者が出た場合か、不調に陥った場合に限られる。
読売の爆買い効果は微々たるもの
読売の爆買い補強はチーム強化につながるのだろうか。もちろん答えは「NO」。2018シーズンの1点差ゲーム勝率 をみると(読売はチーム防御率リーグ1位なのにもかかわらず)、セリーグの最下位で他の5球団に比べて著しく低い。
その主因はセットアッパー、クローザーの人材不足。クローザーとして期待された澤村の防御率が4.64(49登板)、カミネロが同5.79(20)、セットアッパーとして期待された上原が3.63(36)、マシソンが2.97(34)とこちらも芳しくない。
リリーフ陣となると、池田4.07(27)、谷岡5.76(25)、田原2.56(29)、中川5.02(30)、宮國1.97(29)、吉川光4.26(22、先発登板を含む)となり、防御率1点台は宮國ただ一人。読売が強化すべきは、投手陣しかも中継ぎ、抑えであった。
しかるに、今シーズンオフ(2018/11/30)時点において、読売が投手陣強化のための補強情報は伝えられていない。来シーズン開幕前までに読売フロントが行わなければならない第一の仕事は、外国人を含めたクローザー及びセットアッパー探しだ。頭数だけでも上原、カミネロの抜けた穴を補修しなければならない。
丸のFA移籍について
FA宣言した丸(広島)が本日(11/30)、読売入団を公表した。この結果は驚くに当たらない。彼がFA宣言した時点で、その行き先が読売であろうことはだれもが予想し得た。契約金、契約年数、引退後の待遇等において、金満・読売に勝てるところはない。心情的には広島残留してほしいが、選手生命は短い。稼げるときに稼ぐべきだ。
丸は読売で活躍できるのか
丸が2019シーズン、新天地・読売で活躍できるのか。筆者は、ある程度の成績を残すだろうが、2018を下回ると予想する。
その理由は、彼の打撃フォームが変則であること。丸の打撃フォームの特徴は、バットの先端を揺らせてタイミングをとる点。このフォームはタイミングを狂わせると、長期スランプに陥る難点をもっている。極めて微妙な動きをインパクトの前に取り入れる。ボールを打つ前に一段階余分の動作をとる。そこにリスクが生じる。好調時のタイミングをひとたび失うと、一気に崩れる。崩れの要因は、①加齢による体力の衰え及び動体視力低下、②精神面の変調及び環境変化、③相手投手の研究――などによる。どれか一つというよりも、複合的要因として丸を襲う。丸が打撃フォームを崩せば当然、打率は下がるし打点も上がらなくなる。読売という人気球団のプレッシャー及び広島退団の後悔などが丸を襲い、心労が重なる。打撃不振は長期に及ぶだろう。彼の成績は2018シーズンを頂点として、以降、下り坂に向かう。
丸は読売との試合でよく打った。ところが、その読売に入団したのだから、得意球団が減ったことになる。広島(投手陣)は丸の弱点を知り尽くしているから、広島投手陣はそこをついてくる。他球団も広島の攻め方を真似るから、その結果だけでも、丸の打撃成績は落ちる。丸も広島投手陣を知り尽くしているが、読売投手陣と同程度打ち崩せるかというと、そうはいかない(と筆者は思う)。
読売・阿部の捕手再転向
これは論ずるに値しない。まず成功はない。阿部が捕手にすわれば、他球団に盗塁のチャンスが生まれる。
今シーズンの日本シリーズでソフトバンクの甲斐捕手が広島の足を封じMVPに選ばれ、「甲斐キャノン」という新語を生んだ。
甲斐が強肩の持ち主であることは間違いないが、それ以上に下半身が素晴らしい。捕球してから投球動作に至るフットワーク(わずか1歩半程度だが)と、腰を下ろした姿勢から投球動作をつくる立ち上がるスピードがすごい。その基盤となっているのが下半身の安定、強さ、速さだ。
二塁投球の正確なコントロールを支えているのは甲斐の強い体幹だ。天性の身体の強さと適正なトレーニングの結果だろう。阿部が甲斐のような捕手に復活することは、奇跡が起きない限り無理だ。
2018年11月28日水曜日
『江戸東京の聖地を歩く』
●岡本亮輔〔著〕 ●ちくま新書 ●940円+税
聖地というと、一昔前までは聖人の生誕地やその遺物が保管されているところ、あるいは、奇跡の起こったところ、超人的霊力が発せられるところ、特別な事件等が起きたところ…だと思われていた。ところが最近では、アニメや映画のファンにとっての〈聖地〉は、その中に描かれた「印象的シーン」の現場であり、呑み助の親父にとっての〈聖地〉は粋な「居酒屋」であり、野球好きの青少年にとっての〈聖地〉は「甲子園」…といった具合である。このような聖地の変化を換言すれば、聖地とはある者にとっての特別な場所といった意味にまで拡張される。
聖地を個人の体験・意識レベルまで還元すれば、恋愛を成就し結ばれた男(女)にとって、はじめてデートした場所を聖地と見做すこともできる。しかし、それを聖地とはとても呼ぶことができない。個人レベルにおける特別な場所が〈聖地〉となるためには、そこに物語性が付加され、世間一般に認知される必要がある。一対の恋人同士が結ばれたデートスポットの情報が多数の者に共有され、神聖視されなければならない。そこで初めて、無名のデートスポットが聖地へと変容する。
聖地とは何か
著者(岡本亮輔)は聖地を次のように定義する。
聖地の条件――場所・物語・伝達
・聖地に紐づく物語を紡ぐ者
聖地を構成する要素は、〈場所〉〈物語・神話化=作家〉〈伝達する者〉となる。場所はいうまでもない。が、物語、伝達はだれがどのようにつくりあげるのか。口コミも無視できないものの、それだけでは聖地として広域化するのは不可能だ。古代、中世、近世までは、芸能者が素朴な言い伝えを人々が関心を寄せる面白い話に創作した。
・史学と詩学の融合
近世・近代・現代では、マスメディアの発達と平行して、聖地に紐づく物語を量産化したのが作家である。著者(岡本亮輔)は、聖地=近藤勇墓所(東京・板橋区)を論ずる箇所(第6章)において、新選組頭目・近藤勇の神話化に果たした司馬遼太郎の「功績」について次のように書いている。
近代・現代に入ると、九州日報主幹の福本日南が著した『元禄快挙録』、浪曲師・桃中軒雲衛門が演じた『義士銘々伝』が人気を博し、続いて昭和になると、大佛次郎作の『赤穂浪士』をNHKテレビが大河ドラマに仕立て、赤穂浪士人気を不動のものにした。その大河ドラマは、驚異的視聴率を稼いだという。こうして泉岳寺は赤穂浪士の霊が祀られた聖地として、今日でも人気の場所である。
・物語を伝達する者
伝達する者にも変遷がみられる。古代・中世・近世前期において物語の伝達を担ったのは非農業民であった。一般に移動の自由が制限された時代に日本各地を遊行できたのは漂泊の民である。彼らの出自は古代、平民に対し職人と呼ばれた者に由来する。みずからの身につけた職能を通じて、天皇家、摂関家、民仏神と結びつき、供御人(くごにん)、殿下細工、寄人(よりうど)、神人(じにん)などの称号を与えられて奉仕するかわりに、平民の負担する年貢・公事課役を免除されたほか、交通上の特権などを保証された。その一部は荘園・公領に給免田畠を与えられたのである。中世社会には農業以外の生業に主として携わる非農業民(原始・古代以来の海民,山民,芸能民,呪術的宗教者,それに商工民など)が台頭し、全国を移動する自由をもった彼らが情報伝達の役を担ったと思われる。(参考:平凡社世界大百科事典)
近世の中後期になると、瓦版、絵本、図鑑、書物等の紙のメディアが都市を中心に発達した。その結果、非農業民の口伝に加えて、都市を中心にそれらも情報伝達の役を担った。近代、現代ではいうまでもなく、新聞、雑誌、ラジオ、テレビといったマスメディアであり、ポストモダンのいまではマスメディアとともに、SNSが聖地形成の重要な手段となっている。
帝国主義権力と聖地
本題にある江戸東京は、大雑把には4つの時代に区分される。
(1)古代、中世まで、この地は京(中央)から遠い辺境の地。とはいえ、中央の文化(文学、芸能、宗教等)は当然のことながら、この地にも移入されていた。
(2)近世からは、江戸幕府が置かれた中央に格上げされ、江戸は世界有数の規模を誇る都市に成長した。
(3)明治維新後は帝都・東京として発展を続けた。
(4)アジア太平洋戦争の日本帝国の敗戦で壊滅的打撃を受けた東京だが、奇跡の復活を遂げ、世界的メガシティとして繁栄を取り戻し今日に至っている。
なかで江戸東京の大転換は(3)の時代である。まず江戸幕府の聖地の破壊が進行した。たとえば、徳川家の菩提寺である寛永寺が上野戦争で焼失したことを機に、寛永寺という幕府の聖地は破壊され博覧会の会場となり、その後、恩賜公園として整備された。(P122~)
明治維新後の日本は日清、日露、第一次世界大戦、中国侵略、アジア太平洋戦争と、帝国主義戦争の時代であった。そして、帝国主義戦争を継続した体制によって、その維持に資するための「聖地」が体制の手によってつくられた。
1868年(明治維新)から1945年(アジア太平洋戦争敗戦)までの期間につくられたいわば官製の「聖地」は、本書に書かれたほかの聖地のどれとも異なる。生活者が塗炭の苦しみから助けを求めてすがった神社仏閣、偉人、聖人とはかけ離れた、「軍神」と呼ばれる者(に関係する地)が帝国主義国家の「聖地」とされた。彼らの「偉業」を物質化するために銅像や慰霊碑が建立され、その「偉業」を讃えるための「教育」が修身の名のもとに児童生徒に施された。このような聖地(そこに建てられた銅像や慰霊碑を含む)は、国体護持のためのアイコンにすぎない。
本書は取り上げていない聖地を二つほど紹介しよう。その第一は二宮尊徳の像だ。この像はかつて、日本のいたるところの小中学校に建てられていたという。薪を背負いながら本を読んで歩く姿(「負薪読書図」と呼ばれる)から聖なる感覚は呼び起こされるには至らないが、そこには権力側が望む人間像――休むことなく労働と勉学に勤しむ奴隷的労働者を奨励する帝国主義国家の意図――が透けて見える。帝国主義国家が人民に強制する道徳観である。
二宮尊徳もまた、修身の教科書に取り入れられた。その像が学校に建立されるということは、尊徳(像)というアイコンにより、学校という空間の聖地化及び当時の軍国主義教育という観念の聖域化が帝国主義国家によって目指された結果である。
東京・渋谷駅前に建てられた「忠犬ハチ公」もその類である。今日「忠犬ハチ公」の像は待ち合わせ場所の目印となっていて、それを聖地と見做す人はいない。そもそもハチ公とは、死去した飼い主の帰りを東京・渋谷駅の前で約10年間のあいだ待ち続けた犬(ペット)にすぎない。
ハチ公も帝国主義戦争のイデオロギーと無関係ではない。忠犬の「忠」は、上に素直に従う人格を象徴する語で、戦時下、上官の命令に忠実に従う兵士、及び、帝国主義政府の方針に文句を言わない人心――を醸成する物語として、修身の教科書に載せられ、広く国民の思想教育の具となった。
本書で取り上げられた「広瀬中佐像」(高山→東京・万世橋)、乃木神社(東京・港区)、東郷神社(東京・神宮前)も華々しい軍功が物語として語られ(もちろん事実ではない)、教科書に載せられ、臣民教育の一助とされた。それだけではない。これら「軍神」の像は彼らの故郷ではなく、帝都(東京)に建立されたことも忘れてはいけない。
聖地マーケティング
今日の「聖地」には、神社仏閣の経営戦略によって、大衆レベルに認知されたものが散見される。恋愛成就(縁結び)、健康志向等を背景にして、それらの祈願成就事例を創作し、それに関連するグッズを開発し、大量集客を求めて祈祷料、賽銭等を得ようとするものである。その結果、ほんらいの縁起と無関係の「聖地」が誕生している。その成功を意図的とするか、偶然によるものかの論議の余地はあるとしても。
・神前結婚という商品開発(東京大神宮)
文金島田の花嫁と羽織袴の花婿が神主の立会いのもと、三々九度を上げる神前結婚。日本古来の風習と思いきや、わずか100年前に東京大神宮(東京・千代田区富士見)で整備された儀礼だったとは(筆者は本書で初めて知った)。やがて全国の神社で一般化し、結婚式場の建設と平行して一般化し、今日に至っているという。筆者(岡本亮輔)は「重要なのは、神前結婚式が合理的な婚礼形式とみなされたことである。」(P200)と指摘するが。
・パワースポット・ブーム
新たな聖地がパワースポットと名を変えて形成されようとしている。アニメ、コミック、ラノベ(ライトノベル)等の若者向け表現が、LINE、フェイスブック、ツイッター、インスタグラム等のSNSによって拡散され、人々が集まりだした結果の新聖地の誕生である。知名度を得た新聖地は、グッズ(絵馬、御神籤、お守り等)や体験型商品(滝行、祈祷等)の開発に乗り出し、経営の一助としている。これら新聖地の事業の是非は論じない。聖地として信じる者には、そこが聖地なのだから。
聖地のいかがわしさ
“いかがわしい”という表現が適当かどうか迷ったが、ほかに適切な言葉が見つからなかったので使用する。本書に取り上げられた「縁切榎」という聖地についてである。「縁切榎」は現在の東京・板橋区にある。この榎に念ずれば、縁切りが可能だと信じられ大衆的支持を集め、聖地として今日に至っている。
江戸期、女性からの離縁は不可能だった。どんなに不幸な結婚生活を強いられようと、相手と縁が切れない。そのため離縁を果たそうとする女性の信仰を広く集めた。また、男が娼妓にはまって普通の生活ができなくなったことを憂えた家族が、娼妓との縁切りを願ったという事例もある。やがて縁切りは男女関係に限定されず、難病・悪病との縁切り、過度な飲酒の縁切り(=断酒)にまで拡張された。
さて、「縁切榎」にまつわる負(と筆者が感じた)事例を著者(岡本亮輔)が取り上げている。“1934年6月の朝日新聞には、恨みは「縁切榎」 縁談破れて娘服毒 という記事がある(P66)”と。
この事件は破談された22才の女性が揮発油を飲んで自殺未遂したというもの。義兄がもってきた縁談が途中までうまくいっていたが、破談にあう。その理由は男性側が、「縁切榎」の近くを通った女性を嫁にもらいたくないと言い出したせいだ。女性の実家が埼玉県の沼影にあり、帰郷するたびに「縁切榎」の横を通る。そのことを男性側が嫌がって破談にしたのだという。わずか80余年前にそんな迷信がと思うかもしれないが、それが事実なのだから仕方がない。
筆者は、この男性側の言い分を信じない。筆者の推測にすぎないが、女性が「縁切榎」を通ったというのは破談の真の理由ではなかろう。おそらく男性が別の良縁を得て、この縁談を破談にしたがったのだろう。ところが適当な理由が見つからない。そこで「縁切榎」を利用したのだ(と思う)。
男性からの一方的な破談の申し出なのだから、女性側に対して謝罪と慰謝があって当然なのだが、男性側がそれを回避して「縁切榎」という聖地を持ち出すとは、なんと卑劣な理由付けだと思うが、女性の一方的な泣き寝入りである。服毒自殺未遂とは気の毒というほかない。聖地の悪用事例だと筆者は信ずる。
(おわりに)
聖地は、生活者のギリギリの願いや祈りによって形成されたものばかりとは限らない。近年、安易で手軽な聖地(化)もなくはない。体制側による民衆コントロールの具や、帝国主義イデオロギーの醸成のための聖地もある。権力の暴力的移行に伴い犠牲となった敗者の死――荒ぶる魂――を恐れた聖地もある。怨霊信仰に基づく勝者側の保身と畏怖でつくられた聖地である。近年では、寺院、神社の経営(マーケティング)のためにつくられた新しい聖地もある。先述のように、「縁切榎」という聖地を悪用したと思われる事例もある。
本書は江戸東京に限定された聖地の紹介であるが、読みごたえがあり、信頼のおける聖地論となっている。筆者の住まいに近い聖地が多数紹介されていて、一度は訪れてみたいと思わせる情報の質と量を備えている。本書の帯に記された「東京を味わう」というコピーはうってつけ――まさに良質の料理に例えられよう。
聖地というと、一昔前までは聖人の生誕地やその遺物が保管されているところ、あるいは、奇跡の起こったところ、超人的霊力が発せられるところ、特別な事件等が起きたところ…だと思われていた。ところが最近では、アニメや映画のファンにとっての〈聖地〉は、その中に描かれた「印象的シーン」の現場であり、呑み助の親父にとっての〈聖地〉は粋な「居酒屋」であり、野球好きの青少年にとっての〈聖地〉は「甲子園」…といった具合である。このような聖地の変化を換言すれば、聖地とはある者にとっての特別な場所といった意味にまで拡張される。
聖地を個人の体験・意識レベルまで還元すれば、恋愛を成就し結ばれた男(女)にとって、はじめてデートした場所を聖地と見做すこともできる。しかし、それを聖地とはとても呼ぶことができない。個人レベルにおける特別な場所が〈聖地〉となるためには、そこに物語性が付加され、世間一般に認知される必要がある。一対の恋人同士が結ばれたデートスポットの情報が多数の者に共有され、神聖視されなければならない。そこで初めて、無名のデートスポットが聖地へと変容する。
聖地とは何か
著者(岡本亮輔)は聖地を次のように定義する。
・・・内容が事実かどうかは関係なく、特別な物語と紐づけられて語られ続けられるのが聖地なのである。(P10)
物理的空間に物語が上書きされて意味を与えることで聖地になるのだ。聖地とは、虚構と現実を重ね合わせることでしか立ち上がってこない拡張現実なのである。誰かがその場所の物語を語り伝えなければ、聖地は持続しない。したがって、聖地を考える際に鍵となるのは、いかにして場所に物語が紐づけられるか、誰がそれを伝達しているのかを読み解くことなのである。(P12)
聖地の条件――場所・物語・伝達
・聖地に紐づく物語を紡ぐ者
聖地を構成する要素は、〈場所〉〈物語・神話化=作家〉〈伝達する者〉となる。場所はいうまでもない。が、物語、伝達はだれがどのようにつくりあげるのか。口コミも無視できないものの、それだけでは聖地として広域化するのは不可能だ。古代、中世、近世までは、芸能者が素朴な言い伝えを人々が関心を寄せる面白い話に創作した。
・史学と詩学の融合
近世・近代・現代では、マスメディアの発達と平行して、聖地に紐づく物語を量産化したのが作家である。著者(岡本亮輔)は、聖地=近藤勇墓所(東京・板橋区)を論ずる箇所(第6章)において、新選組頭目・近藤勇の神話化に果たした司馬遼太郎の「功績」について次のように書いている。
新選組ほどフィクションの力によって評価の一変した存在も珍しい。(略)新選組イメージは、長い時間をかけてメディアの中で作られてきたものだ。当然ながら、維新直後、新選組の評価は最悪だった。(略)新選組は京で志士たちを捕縛殺害してきたからである。(略)新選組復権の先駆となったのが、子母澤寛『新選組始末記』(1928)の刊行だ。(略)そして現在まで続く新選組のイメージを決定づけたのが、1960年代に連載刊行された司馬遼太郎の『新選組血風録』と『燃えよ剣』である。著者(岡本亮輔)は詩学と史学の融合は、赤穂浪士(泉岳寺)、鼠小僧(両国回向院)、四谷怪談(お岩稲荷)などにも共通する物語化の典型だという。赤穂浪士については、討ち入り事件という史実を土台にして、歌舞伎や浄瑠璃が創作を加えて演じられることによって大衆レベルに浸透した。
續谷真紀は、司馬作品では、虚構があたかも史実であるかのように巧みに織り込まれていることに注目する。(略)司馬が確立した虚構と史実を織り交ぜるスタイル、つまり、詩学と史学の融合が新選組人気の理由の一つだ。(P253~255)
近代・現代に入ると、九州日報主幹の福本日南が著した『元禄快挙録』、浪曲師・桃中軒雲衛門が演じた『義士銘々伝』が人気を博し、続いて昭和になると、大佛次郎作の『赤穂浪士』をNHKテレビが大河ドラマに仕立て、赤穂浪士人気を不動のものにした。その大河ドラマは、驚異的視聴率を稼いだという。こうして泉岳寺は赤穂浪士の霊が祀られた聖地として、今日でも人気の場所である。
・物語を伝達する者
伝達する者にも変遷がみられる。古代・中世・近世前期において物語の伝達を担ったのは非農業民であった。一般に移動の自由が制限された時代に日本各地を遊行できたのは漂泊の民である。彼らの出自は古代、平民に対し職人と呼ばれた者に由来する。みずからの身につけた職能を通じて、天皇家、摂関家、民仏神と結びつき、供御人(くごにん)、殿下細工、寄人(よりうど)、神人(じにん)などの称号を与えられて奉仕するかわりに、平民の負担する年貢・公事課役を免除されたほか、交通上の特権などを保証された。その一部は荘園・公領に給免田畠を与えられたのである。中世社会には農業以外の生業に主として携わる非農業民(原始・古代以来の海民,山民,芸能民,呪術的宗教者,それに商工民など)が台頭し、全国を移動する自由をもった彼らが情報伝達の役を担ったと思われる。(参考:平凡社世界大百科事典)
近世の中後期になると、瓦版、絵本、図鑑、書物等の紙のメディアが都市を中心に発達した。その結果、非農業民の口伝に加えて、都市を中心にそれらも情報伝達の役を担った。近代、現代ではいうまでもなく、新聞、雑誌、ラジオ、テレビといったマスメディアであり、ポストモダンのいまではマスメディアとともに、SNSが聖地形成の重要な手段となっている。
帝国主義権力と聖地
本題にある江戸東京は、大雑把には4つの時代に区分される。
(1)古代、中世まで、この地は京(中央)から遠い辺境の地。とはいえ、中央の文化(文学、芸能、宗教等)は当然のことながら、この地にも移入されていた。
(2)近世からは、江戸幕府が置かれた中央に格上げされ、江戸は世界有数の規模を誇る都市に成長した。
(3)明治維新後は帝都・東京として発展を続けた。
(4)アジア太平洋戦争の日本帝国の敗戦で壊滅的打撃を受けた東京だが、奇跡の復活を遂げ、世界的メガシティとして繁栄を取り戻し今日に至っている。
なかで江戸東京の大転換は(3)の時代である。まず江戸幕府の聖地の破壊が進行した。たとえば、徳川家の菩提寺である寛永寺が上野戦争で焼失したことを機に、寛永寺という幕府の聖地は破壊され博覧会の会場となり、その後、恩賜公園として整備された。(P122~)
明治維新後の日本は日清、日露、第一次世界大戦、中国侵略、アジア太平洋戦争と、帝国主義戦争の時代であった。そして、帝国主義戦争を継続した体制によって、その維持に資するための「聖地」が体制の手によってつくられた。
1868年(明治維新)から1945年(アジア太平洋戦争敗戦)までの期間につくられたいわば官製の「聖地」は、本書に書かれたほかの聖地のどれとも異なる。生活者が塗炭の苦しみから助けを求めてすがった神社仏閣、偉人、聖人とはかけ離れた、「軍神」と呼ばれる者(に関係する地)が帝国主義国家の「聖地」とされた。彼らの「偉業」を物質化するために銅像や慰霊碑が建立され、その「偉業」を讃えるための「教育」が修身の名のもとに児童生徒に施された。このような聖地(そこに建てられた銅像や慰霊碑を含む)は、国体護持のためのアイコンにすぎない。
本書は取り上げていない聖地を二つほど紹介しよう。その第一は二宮尊徳の像だ。この像はかつて、日本のいたるところの小中学校に建てられていたという。薪を背負いながら本を読んで歩く姿(「負薪読書図」と呼ばれる)から聖なる感覚は呼び起こされるには至らないが、そこには権力側が望む人間像――休むことなく労働と勉学に勤しむ奴隷的労働者を奨励する帝国主義国家の意図――が透けて見える。帝国主義国家が人民に強制する道徳観である。
二宮尊徳もまた、修身の教科書に取り入れられた。その像が学校に建立されるということは、尊徳(像)というアイコンにより、学校という空間の聖地化及び当時の軍国主義教育という観念の聖域化が帝国主義国家によって目指された結果である。
東京・渋谷駅前に建てられた「忠犬ハチ公」もその類である。今日「忠犬ハチ公」の像は待ち合わせ場所の目印となっていて、それを聖地と見做す人はいない。そもそもハチ公とは、死去した飼い主の帰りを東京・渋谷駅の前で約10年間のあいだ待ち続けた犬(ペット)にすぎない。
ハチ公も帝国主義戦争のイデオロギーと無関係ではない。忠犬の「忠」は、上に素直に従う人格を象徴する語で、戦時下、上官の命令に忠実に従う兵士、及び、帝国主義政府の方針に文句を言わない人心――を醸成する物語として、修身の教科書に載せられ、広く国民の思想教育の具となった。
本書で取り上げられた「広瀬中佐像」(高山→東京・万世橋)、乃木神社(東京・港区)、東郷神社(東京・神宮前)も華々しい軍功が物語として語られ(もちろん事実ではない)、教科書に載せられ、臣民教育の一助とされた。それだけではない。これら「軍神」の像は彼らの故郷ではなく、帝都(東京)に建立されたことも忘れてはいけない。
聖地マーケティング
今日の「聖地」には、神社仏閣の経営戦略によって、大衆レベルに認知されたものが散見される。恋愛成就(縁結び)、健康志向等を背景にして、それらの祈願成就事例を創作し、それに関連するグッズを開発し、大量集客を求めて祈祷料、賽銭等を得ようとするものである。その結果、ほんらいの縁起と無関係の「聖地」が誕生している。その成功を意図的とするか、偶然によるものかの論議の余地はあるとしても。
・神前結婚という商品開発(東京大神宮)
文金島田の花嫁と羽織袴の花婿が神主の立会いのもと、三々九度を上げる神前結婚。日本古来の風習と思いきや、わずか100年前に東京大神宮(東京・千代田区富士見)で整備された儀礼だったとは(筆者は本書で初めて知った)。やがて全国の神社で一般化し、結婚式場の建設と平行して一般化し、今日に至っているという。筆者(岡本亮輔)は「重要なのは、神前結婚式が合理的な婚礼形式とみなされたことである。」(P200)と指摘するが。
・パワースポット・ブーム
新たな聖地がパワースポットと名を変えて形成されようとしている。アニメ、コミック、ラノベ(ライトノベル)等の若者向け表現が、LINE、フェイスブック、ツイッター、インスタグラム等のSNSによって拡散され、人々が集まりだした結果の新聖地の誕生である。知名度を得た新聖地は、グッズ(絵馬、御神籤、お守り等)や体験型商品(滝行、祈祷等)の開発に乗り出し、経営の一助としている。これら新聖地の事業の是非は論じない。聖地として信じる者には、そこが聖地なのだから。
聖地のいかがわしさ
“いかがわしい”という表現が適当かどうか迷ったが、ほかに適切な言葉が見つからなかったので使用する。本書に取り上げられた「縁切榎」という聖地についてである。「縁切榎」は現在の東京・板橋区にある。この榎に念ずれば、縁切りが可能だと信じられ大衆的支持を集め、聖地として今日に至っている。
江戸期、女性からの離縁は不可能だった。どんなに不幸な結婚生活を強いられようと、相手と縁が切れない。そのため離縁を果たそうとする女性の信仰を広く集めた。また、男が娼妓にはまって普通の生活ができなくなったことを憂えた家族が、娼妓との縁切りを願ったという事例もある。やがて縁切りは男女関係に限定されず、難病・悪病との縁切り、過度な飲酒の縁切り(=断酒)にまで拡張された。
さて、「縁切榎」にまつわる負(と筆者が感じた)事例を著者(岡本亮輔)が取り上げている。“1934年6月の朝日新聞には、恨みは「縁切榎」 縁談破れて娘服毒 という記事がある(P66)”と。
この事件は破談された22才の女性が揮発油を飲んで自殺未遂したというもの。義兄がもってきた縁談が途中までうまくいっていたが、破談にあう。その理由は男性側が、「縁切榎」の近くを通った女性を嫁にもらいたくないと言い出したせいだ。女性の実家が埼玉県の沼影にあり、帰郷するたびに「縁切榎」の横を通る。そのことを男性側が嫌がって破談にしたのだという。わずか80余年前にそんな迷信がと思うかもしれないが、それが事実なのだから仕方がない。
筆者は、この男性側の言い分を信じない。筆者の推測にすぎないが、女性が「縁切榎」を通ったというのは破談の真の理由ではなかろう。おそらく男性が別の良縁を得て、この縁談を破談にしたがったのだろう。ところが適当な理由が見つからない。そこで「縁切榎」を利用したのだ(と思う)。
男性からの一方的な破談の申し出なのだから、女性側に対して謝罪と慰謝があって当然なのだが、男性側がそれを回避して「縁切榎」という聖地を持ち出すとは、なんと卑劣な理由付けだと思うが、女性の一方的な泣き寝入りである。服毒自殺未遂とは気の毒というほかない。聖地の悪用事例だと筆者は信ずる。
(おわりに)
聖地は、生活者のギリギリの願いや祈りによって形成されたものばかりとは限らない。近年、安易で手軽な聖地(化)もなくはない。体制側による民衆コントロールの具や、帝国主義イデオロギーの醸成のための聖地もある。権力の暴力的移行に伴い犠牲となった敗者の死――荒ぶる魂――を恐れた聖地もある。怨霊信仰に基づく勝者側の保身と畏怖でつくられた聖地である。近年では、寺院、神社の経営(マーケティング)のためにつくられた新しい聖地もある。先述のように、「縁切榎」という聖地を悪用したと思われる事例もある。
本書は江戸東京に限定された聖地の紹介であるが、読みごたえがあり、信頼のおける聖地論となっている。筆者の住まいに近い聖地が多数紹介されていて、一度は訪れてみたいと思わせる情報の質と量を備えている。本書の帯に記された「東京を味わう」というコピーはうってつけ――まさに良質の料理に例えられよう。
2018年11月4日日曜日
登録:
投稿 (Atom)